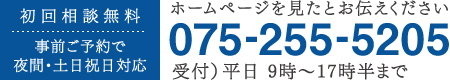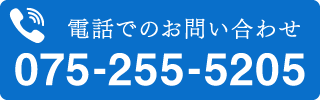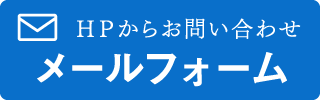コラム
メタバースと法律(1)~そもそもメタバースとは~
最近、「メタバース」が注目されています。
フェイスブック社(Facebook, Inc.)が社名を「META(Meta Platforms, Inc.)」に変更するなどして大きな話題を呼んだことから、「メタバース」という言葉だけであれば、知っている方も多いのではないでしょうか。
実は、メタバースには法的な課題もたくさんあります。
この記事では、メタバースとは何か、定義や歴史、検討すべき法的な課題などをご説明します。
メタバースと法律について連載をしていきますので、関心のある方はぜひお読みください。
1 メタバースとは
メタバースとは、 英語で「高次」を意味する「Meta」(メタ)と「世界」を意味する「Universe」(ユニバース)が組み合わさった言葉です。
直訳すると「高次な世界」となります。
実際には、メタバースは「ネット上に構築された仮想の三次元空間」を意味します。
ネット上に構築された世界は現実世界とは異なり高度な技術を用いた仮想空間なので「高次の」という「Meta」という単語が使われています。
2 メタバースの歴史
メタバースという言葉が扱われ出したのは、1992年に出版されたSF小説です。
ここでは、VRゴーグルをつけて三次元オンライン仮想世界を体験するのですが、その世界をあらわす単語として、メタバースが用いられています。
アメリカの会社が2003年に開始した仮想空間「セカンドライフ」は、本格的なメタバース空間の先駆けです。
セカンドライフとは、ネット上に自分の分身であるアバターを作り出して他のユーザーとチャットをしたり音声で話をしてコミュニケーションをとったりできるサービスです。
セカンドライフでは、「リンデンドル」というゲーム内の通貨が流通しています。リンデンドルは実際のお金を使って購入するもので、換金もできるものです。
つまり、セカンドライフ内でビジネスをすることも可能となっているのです。
また、セカンドライフの内部では、参入した企業が新製品発表会やプロモーション活動なども盛んに行っていました。
その後、ネット環境が向上したことなどから、仮想空間で実現できる事項が増え、体験価値が飛躍的にアップしました。
現代の技術発展はめざましく、ブロックチェーン技術やNFTなども活用されるようになり、仮想空間で経済活動を行う基盤が整ってきているといえます。
そういった現代社会におけるメタバースは、未来を担う中核的な技術として非常に注目されています。
Facebook社がmeta社へと社名変更したのも、こういったメタバースへの期待をあらわしたものといえます。
3 メタバースの7要素
具体的に、メタバースとはどういったものなのでしょうか?
この点、VR(バーチャルリアリティ)の分野で有名なマシュー・ボール氏(投資家)が、運営するブログにおいて「メタバースの7要素」を挙げているので参照しましょう。
(1)永続性
まずは、永続性が必要です。
リセットや停止、終了などがなく現実世界と同様の連続性が求められます。
(2)リアルタイム性
リアルタイムに仮想世界にいる他者と同じ体験を共有できる状態です。
(3)ユーザーに「存在する」感覚を与える
ユーザーには、仮想世界内に「存在する」感覚を与えなければなりません。
ただし、現実世界のように物理的な制約はなく、現実世界と完全に同じというわけではありません。
(4)経済性がある
メタバースの世界では、実際にビジネスができます。
デジタル空間であっても商品やサービスを売買できるのがメタバースの特徴の1つです。
(5)垣根がない
仮想世界と現実世界、プライベートとパブリックなどの垣根をなくして連続した空間を提供します。
(6)異なるベンダー間の相互運用を実現
異なるベンダーによって提供される製品であっても互換可能で運用できる状態です。
(7)幅広い人や企業によって貢献されている
企業でも個人でも誰でも参加できて、多種多様な物やコンテンツが提供されるのがメタバースの特徴です。
なお、上記の要素をすべて備えた完璧なメタバースを実現するのは現代の技術をもってしても困難です。
今後、メタバースが発展していけば、実現される日も来るのではないでしょうか。
4 メタバースの実例
メタバースの実例としては、以下のようなものがあります。
- メタ社のHorizon worlds(アバターを作成して仮想空間へ参加する)
- VRChat社のVRChat(他のユーザーと音声やジェスチャーなどによってコミュニケーションを楽しむ)
- Metaverse Holdings社のDecentraland(NFTによって土地などを売買できる)
- Roblox社によるRoblox(ゲーム)
- クラスター株式会社によるcluster(日本企業が提供するメタバースのサービス。バーチャル上で音楽ライブを行ったりイベントに参加したりできる)
5 メタバースのカテゴリー
現時点で存在するメタバースをあえてカテゴリー別に分けると、以下のようになります。
(1)ソーシャル型
相互に交流するサービスです。VRChatやclusterなどが該当します。
(2)デジタル資産型
デジタル資産を保持したりやり取りしたりするサービスです。DecentralandやRobloxなどが該当します。
(3)コンテンツ提供型
コンテンツを提供するサービスです。FortniteやMinecraftなどが該当します。
(4)Eコマース型
商品販売するサービスです。バーチャルマーケットなどです。
(5)ビジネス型
人が集まってビジネスを行ったりするサービスです。Meta Horizon Workroomsなどが該当します。
メタバースについては、法律的な問題もたくさんあります。
次の記事では、メタバースに関連する法律について解説していきます。
訴訟により交通事故の損害賠償額を約300万円増額することに成功した事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、人身、訴訟
・ご相談内容
ご依頼者は、自動車で交差点を直進して走行中、相手方が一時停止線で停車することなく交差点に進入してきたために衝突し、頭部打撲、頸椎捻挫等の怪我をしてしまいました。事故後、ご自身による対応となると不安もあるとのことで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
示談交渉では、過失割合及び損害賠償額について折り合いがつかなかったため、訴訟を提起しました。訴訟では、主に、過失割合と後遺障害逸失利益が争点となりました。過失割合については、具体的な事故状況、参考となる裁判例等を、後遺障害逸失利益については、後遺障害によってご依頼者が仕事を行うにあたって生じる具体的な不利益、参考となる裁判例等を丁寧に主張し、最終的に、当初の相手方保険会社提案の金額より300万円増額した金額での和解を成立させることができました。
・コメント
訴訟によって、損害賠償額の大幅な増額に成功した事案です。
訴訟においては、当方の主張について丁寧に主張して、裁判所から当方の主張に近い和解案を提案してもらうことができました。訴訟となると、示談交渉での解決よりも時間がかかってしまうことが多いですが、今回の事案では、約300万円という大幅な増額に成功したため、ご依頼者には大変喜んで頂けました。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
交通事故の過失割合についてはこちらのページで、後遺障害についてはこちらのページで詳しく解説しています。
レピュテーションリスクとは 具体例や回避策を弁護士が解説
レピュテーションリスクとは、世間に企業へのネガティブな評判が広まることによって、企業の社会的な信用が低下することをいいます。
近年では、中小企業においても、自社情報のコントロールの重要性が高まっており、レピュテーションリスクへの対策が求められます。
自社の評判や信用が低下すると、商品やサービスが売れなくなる、取引が難しくなる、株価が低下するなどして、企業が大きな不利益を被ってしまうでしょう。
今回は、レピュテーションリスクとはなにか、具体例や回避策を京都の弁護士がお伝えします。
自社の情報をコントロールして安全に経営を進めるため、ぜひ参考にしてみてください。
1 レピュテーションリスクとは
レピュテーションリスクとは、企業の評判に関するリスク(危険性)です。
レピュテーション(reputation)は英語で「評判」を意味しており、それについてのリスクなのでレピュテーションリスクといいます。
現代では、SNSやレビューサイト、ブログなどが急速に普及し、簡単に企業の評判を調べることができます。
SNSでの「炎上」などが起こってしまうと、一瞬で全国に悪評が広まってしまうケースも少なくありません。
企業に対する評判が落ちると、売上が低下したり資金調達にも悪影響が及んだりする可能性があります。
現代社会において、安全に企業経営をするには、自社のレピュテーションリスクについて対策を行い、情報をコントロールすることが必須といえるでしょう。
2 レピュテーションリスクの具体例
実際に、レピュテーションリスクが発生すると企業にどういった悪影響が及ぶのか、具体例を示します。
(1)アルバイト店員の不適切な行動
コンビニエンスストアのアルバイト店員が、店内の冷蔵ケースのなかに寝そべった写真をSNSに投稿し、全国に広まったという事例です。
当該コンビニは、当該店舗とのフランチャイズ契約を解除しました。
コンビニ以外でも、寿司屋やピザ屋、牛丼チェーン店などでアルバイト店員による不祥事は数多く発生しています。
(2)居酒屋で産地偽装
居酒屋チェーンで、看板メニューだった鶏の産地を偽装していたという事実が明らかになったケースです。
使用している鶏肉を「宮崎地鶏」と公表していましたが、実際には一部にタイ産のブロイラーが含まれていました。メニューやホームページなどに「地鶏一筋」と表記していたことなどから、大きな問題となりました。
景品表示法違反により、消費者庁から運営会社に対して900万円を超える課徴金の納付命令が出されました。
3 レピュテーションリスクの回避策
(1)正確な情報発信
まず、発信する情報は正確なものでなければなりません。
産地や成分、サービス内容や料金など、誤認させるような表現は控えるべきです。
HPやSNS、ブログなどで情報発信するときにも、過大な表現は慎みましょう。
(2)従業員教育
従業員教育も極めて重要です。
具体例でご紹介したように、アルバイト店員による不祥事が原因のレピュテーションリスクも多数発生しています。
正社員だけではなくアルバイトやパート、契約社員などの行動によっても評判は低下するので、法令や社内規則の遵守、ネットリテラシーの向上の重要性を伝えることが必要となります。
(3)ネット情報をモニター
自社に対するネット上の評判は、常に気を配っておくべきです。
問題が発生したとき、SNSなどで「炎上」する前に適切に対応することができれば、リスクを最小限にとどめることができるからです。
社内での対応に限界がある場合には、専門業者へモニターを依頼して対策する方法もあります。
4 レピュテーションリスク対策として弁護士がサポートできること
弁護士にレピュテーションリスク対策を任せることもできます。
以下では、弁護士が具体的にどういったサポートをできるのか、お伝えします。
(1)組織体制の整備をサポート
社内でしっかりリスク管理ができるように、組織の内部体制作りも弁護士がサポートします。
各企業の実情に応じた方法を提案し、試行錯誤を行って最適な組織体制に整えていきます。
(2)社内研修を行う
レピュテーションリスクについての従業員向けの社内研修を行うことも、レピュテーションリスク対策として有効な方法です。
弁護士が従業員向けの研修を行い、従業員の意識付けをするサポートも可能です。
(3)不祥事が起こったときの対応
レピュテーションリスクが現実化して不祥事が起こってしまった場合に、弁護士がアドバイスを行う等の対応を行うことも考えられます。
不祥事対応では法律上、監督官庁への報告が必要なケースもありますし、顧客や社会に対する謝罪や説明を求められるケースもあるでしょう。
弁護士は、その時の状況に応じて、企業にとって必要な対処方法を相談し、早期に火消しができるようにつとめます。
京都の益川総合法律事務所では、各業種の企業への法務サポートに力を入れております。
レピュテーションリスクについての対策の必要性を感じている企業の方は、ぜひとも一度ご相談ください。
弁護士の交渉により養育費を月額5万円減額することに成功した事案【解決事例】
・キーワード
養育費、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、養育費を支払う側です。当事者間で合意した養育費の金額が高額に過ぎるため、生活に支障が出ており、大変に困っているということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方に対して速やかに連絡をして、当方の希望について伝えるとともに、相手方の意見についても聴き取りを行いました。相手方としては、婚姻中の債務の取扱い等についても不満があり、それに伴う主張をしていましたが、ご依頼者の生活状況や法的な観点から丁寧に説明をすることにより、一定の譲歩を引き出すことに成功し、最終的に月額5万円を減額することができました。
・コメント
養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用であり、当事者間で話し合って取り決めをすることもありますが、その金額が妥当であるかについては注意をする必要があります。
示談交渉にあたり、相手方は、弁護士に依頼することはなく、本人の対応でした。ご依頼者の生活状況や法的な主張について理解をしてもらうことが難しい部分もあったのですが、できる限り丁寧に説明をして、粘り強く交渉をすることにより、何とか減額をすることができました。
本件では、養育費の減額について、法的に難しい部分もありましたが、交渉に力を入れることによりご依頼者の希望を実現することができ、弁護としても、嬉しい事案となりました。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
養育費の増減額については、こちらのページで詳しく解説しています。
採用内定を取り消したい企業の方へ
いったん採用内定を出しても、さまざまな事情により取り消したいケースがあるものです。
しかし、採用内定を出すと「雇用契約」が成立するので、企業側の都合で簡単には取り消しができません。
今回は、採用内定を取り消せる場合や取り消す方法について、京都の弁護士がお伝えします。
採用内定の取り消しによるトラブルを防止するため、ぜひ参考にしてください。
1 採用内定で雇用契約が成立する
いったん採用内定を出してしまったら、会社側の都合で簡単に取り消すのが困難となります。
採用内定通知を出した時点で一種の雇用契約が成立する、と考えられているためです。
採用内定によって成立するのは、「始期付解約権留保付労働契約」とされています。
「始期付解約権留保付労働契約」とは、雇用の開始について入社日等の始期が定められていて、そのときまでは、一定の場合には会社側に労働契約を解約する権利が認められるタイプの雇用契約です。
内定を出したことによって、契約そのものは成立しているため、会社側が一方的に自由に取り消せるわけではありません。
2 内定取消が認められる条件
内定取り消しは、絶対に認められないというわけではありません。
採用内定も雇用契約の一種である以上、一般の雇用契約と同等の要件を満たせば解除ができます。
具体的には以下の2つの要件を満たさねばなりません。
- 客観的かつ合理的な理由がある
- 社会通念上相当な方法で解雇した
内定取り消しが認められやすいケース
たとえば、以下のような場合であれば、採用内定の取り消しが認められやすいといえるでしょう。
- 内定者に重大な経歴詐称が発覚した
- 採用内定時には大学在籍中で卒業が条件とされていたが、卒業できなかった
- 内定者が犯罪行為を行って、有罪判決が確定した
3 業績悪化による内定取消が認められる条件
会社の業績が悪化して採用が困難となった場合にも内定取り消しが認められる可能性があります。
ただし、業績が悪化しただけでどのようなケースでも取り消しができるわけでもありません。
一般的なリストラのケースと同様に、「整理解雇(リストラ)の4要件」を満たす必要があります。
- 人員削減の必要性がある
- 解雇回避のために会社が尽力した
- 被解雇者の選定方法に合理性がある
- 整理解雇の対象労働者や労働組合へ説明を行い、適正な手続きを履践した
人員削減のために内定取り消しをする場合、上記の要件を満たすかどうかについて、しっかり検討しましょう。
4 不当な内定取り消しをした場合のリスク
企業が不当な内定取り消しをすると、以下のようなリスクが発生します。
(1)法的トラブルになる
不当に内定取り消しをすると、内定者側が不満を感じて「取り消しは無効」と主張してくる可能性があります。
ときには労働審判となったり、訴訟を起こされたりするので、企業側にも対応コストが発生するでしょう。
(2)経済的な損失
採用内定を取り消してトラブルになると、従業員から訴訟などを起こされて解決金や未払い賃金等を払わねばならない可能性があります。
訴訟になると訴訟費用もかかり、企業の経済的な損失は少なくありません。
(3)風評被害が起こる
不当な内定取り消しをすると、内定者側がネット掲示板や情報サイトに書き込むなどして風評被害が生じる可能性もあります。
そうなると、企業が新たに優秀な人材を集めるのも難しくなってしまうでしょう。
5 企業が円満に内定取消を行うためのポイント
企業が円満に内定取り消しを行うには、以下のような対応を心がけましょう。
(1)誠実に対応する
まず、対象となる内定者に対し、誠意を持って対応することが重要です。
たとえば、可能な限り取消理由を丁寧に説明するなどです。
単に集団説明会を開催するだけではなく、個別に対応するのが望ましいでしょう。
場合によっては、金銭的な補償も検討しましょう。
(2)再就職の支援をする
採用内定を取り消す際、対象者に対してはできるだけ再就職の支援を行いましょう。
別に就職先が見つかれば、内定者側もあえてトラブルを起こそうとはしないものです。
自社と関係のある企業を紹介するなど、相手方が不利益を受けないように誠意をもった対応をしましょう。
(3)内定取消の通知は早めに行う
内定取消の通知が遅れると、内定者にとって不利益が大きくなる可能性が高まります。
企業側の誠意を示すためにも、内定取消事由が明らかになった時点で、早めに内定取消の通知を送ることが望ましいといえるでしょう。
(4)合意書を作成する
内定を取り消す際、単に口約束をしただけでは、後にトラブルになるリスクが高いままになってしまいます。
後で蒸し返されてしまうことを防止するために、「合意書」を作成しましょう。
合意書があれば、内定者が取り消しに納得した事実が明らかになりますし、取り消しの条件も明確になります。
京都の益川総合法律事務所は、中小企業の支援に積極的に取り組んでいます。
従業員との雇用関係などでお悩みの企業の方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。
交通事故の過失割合の修正要素とは
交通事故の過失割合には、「修正要素」があります。
修正要素による修正が認められる場合、基本となる過失割合が修正されて、お互いの過失割合が変わります。
正しく過失割合を算定するには、修正要素について理解しておく必要があります。
今回は、交通事故の過失割合の修正要素について、京都の弁護士が解説します。
交通事故に遭われた方は是非参考にしてみてください。
1 過失割合の修正要素とは
(1)過失割合と過失相殺
交通事故の過失割合とは、交通事故の発生に対する当事者それぞれの責任の割合です。
たとえば、加害者と被害者の過失割合が「80%:20%」「60%:40%」などとなり、双方の割合を足すと100%になります。
損害賠償の際には、こちらの過失割合の分、相手に請求できる金額が減額されます。たとえば、100万円の損害が発生していても、被害者の過失割合が20%であれば請求できる金額は80%になってしまいます。
このような過失割合による減額に関するルールを「過失相殺」といいます。
過失相殺がされると、相手から受け取ることができる賠償金の額が減ってしまうので、交通事故被害者にとって、過失割合や過失相殺は非常に重要といえるでしょう。
(2)過失割合には基準がある
交通事故の過失割合には一定の基準があります。
個々の事故態様に応じて、裁判所が参考とする過失割合が決まっているのです。
示談で解決する際にも、基本的に過失割合の基準に従います。
(3)修正要素とは
過失割合の基準には、基本の過失割合と修正要素があります。
基本の過失割合は、その事故態様において適用される基本的な過失割合です。
一方、修正要素は、個別的な事故の特徴を反映して、より適切に過失割合を算定するための事情です。
基本の過失割合が高くても修正要素が適用されると最終的な過失割合は減って、相手に請求できる金額が大きくなるケースが少なくありません。
被害者にとって、修正要素を正しく当てはめることは、極めて重要といえるでしょう。
2 修正要素の例
よくある修正要素として、以下のようなものがあります。
(1)スピード違反
一方がスピード違反していると、違反した車両の過失割合が上がります。
(2)歩行者が子どもや身体障がい者、高齢者
自動車と歩行者が接触した事故の場合、被害者が子どもや身体障がい者、高齢者などであれば被害者の過失割合が下がります。
(3)事故時間が夜間
事故時間が夜間の場合、車はライトをつけているので歩行者側からは発見しやすくなりますが、車からは被害者を認識しにくくなります。
そこで、車両側の過失割合が下がります。
(4)事故現場が住宅地
事故現場が住宅地の場合、歩行者がどこから出てくるかわからないので車は通常以上に注意して運転しなければなりません。
そこで、車側の過失割合が上がります。
(5)事故現場が幹線道路
事故現場が幹線道路の場合、車は歩行者が出てくるとは考えないものです。反面、歩行者としてはより注意を払って横断すべきでしょう。
そこで、車の過失割合が下がって歩行者の過失割合が上がる可能性があります。
(6)著しい過失
著しい過失とは、通常想定されている程度を超えるような過失です。
たとえば、脇見運転等の著しい前方不注視、著しく不適切なハンドルブレーキ操作、時速15キロメートルを超える速度違反などが該当します。
著しい過失があると、その車両の過失割合が上がります。
(7)重過失
重過失とは、故意にも匹敵するほどの重大な過失です。
酒酔い運転や無免許運転、居眠り運転などが該当します。
重過失があると著しい過失以上に該当車両の過失割合が上がります。
3 修正要素を確認する方法
事故ごとの正しい修正要素を確認するには、自分で本を調べる方法と弁護士に相談する方法等があります。
(1)自分で本を調べる方法
過失割合に関する法的な考え方は「判例タイムズ」という法律雑誌の別冊特集にまとまっています。
その本を買い求め、自分で事故状況に当てはめて正しく検討すれば、修正要素を確認できるでしょう。
(2)弁護士に確認する方法
自分で本を見ても判断を誤ってしまう可能性があります。
そこで、より確実なのは弁護士に相談し、過失割合を算定してもらう方法といえます。
弁護士であれば事故の状況をもとに基本の過失割合と修正要素を適切に認定できます。
弁護士に相談すれば、自分で本を買ったり読み解いたりする必要もなく手間がかからないので、基本的にはこちらの方法で修正要素を確認するのが良いでしょう。
4 過失割合を定めるときの注意点
交通事故の過失割合を定める際、被害者が自分で保険会社と示談交渉していると、通常は保険会社側から過失割合の提示があります。
この場合、必ずしも適切な修正要素が適用されていないケースも多いので、鵜呑みにしないように注意しましょう。
ときには、被害者側の過失割合が高めに算定されている事例もあります。
そのまま合意すると、受け取れる保険金が減額されてしまう可能性があります。
示談交渉で保険会社から過失割合の提示があったら、なるべく早めに弁護士へ相談しましょう。
もし、保険会社から提示された過失割合が不当であれば、話し合って再度取り決めをやり直すことも可能です(ただし示談が成立する前の段階で相談する必要があります)。
京都の益川総合法律事務所では、交通事故の被害者を積極的にサポートしております。
過失割合や修正要素について疑問がある場合にはお気軽にご相談ください。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
夫や妻が不倫した場合、不倫相手や配偶者本人に慰謝料請求できます。
慰謝料請求は、自分自身で行うよりも、弁護士に依頼した方が効率が良く、有利に解決しやすいというメリットがあります。
相手と直接話さなくても良いので、ストレスも軽減されるでしょう。
今回は、不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットをお伝えします。
弁護士に相談しようかどうか迷われているという方は、参考にされてください。
1 証拠について相談できる
不倫の慰謝料請求をするときには、証拠を持っているか否かが重要です。
特に、「配偶者と不倫相手の肉体関係」をある程度証明できないと、慰謝料請求に応じてもらうことが難しくなります。
もっとも、ご本人ではどういった証拠が有効なのか判断しがたいケースも多いでしょう。
弁護士に相談すると、どのような証拠が必要であるかについて、具体的にアドバイスを受けられます。
証拠不足のために慰謝料請求に失敗するというリスクを抑えられるのは、大きなメリットとなるでしょう。
2 相当な慰謝料額を設定できる
不倫の慰謝料請求をするとき、「具体的にいくらの慰謝料額を請求すれば良いのか?」と迷ってしまう方が少なくありません。
不倫の慰謝料額には「相場」があります。相場からあまりにも外れた金額を請求するのは非現実的です。
基本的には、相場を知った上で請求額を定めるのが良いでしょう。
ただし、示談交渉の場合、相場とおりの金額にしなければならないわけではありません。
相手さえ了承すれば、相場より高い金額にしても良いですし、こちらが了承すれば、低い金額にすることもできます。
弁護士に相談すると、個別の事案に応じた妥当な請求額を設定できるというメリットがあります。
3 不倫相手を調査できる可能性がある
配偶者に不倫されたとき、不倫相手がどこの誰であるかがわからないケースが多くあります。
その場合、まずは不倫相手の氏名や住所などの情報を調べなければなりません。
もっとも、個人では不倫相手の情報を調べるのは困難でしょう。
弁護士であれば、相手の電話番号や車のナンバーなどから不倫相手を特定できる可能性もあります。
不倫相手の調査ができる可能性がある点も、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
4 時間や労力を減らすことができる
不倫相手へ慰謝料請求を行うについては、大変な労力が必要とされます。
まずは慰謝料を請求する書面を作成しなければなりません。
相手に書面を送った後は交渉を行い、合意書も作成する必要があります。場合によっては、合意の内容を公正証書にしておく必要性もあるでしょう。
自分自身ですべてに対応しようとすると、膨大な労力と時間がかかってしまいます。
弁護士に依頼すれば、請求書の作成や相手方との交渉、合意書の作成などを任せることができます。
ご自身の貴重な労力や時間を減らすことができるのも、弁護士に依頼するメリットとなります。
5 有利な条件で解決しやすくなる
不倫相手に慰謝料請求をするときには、できるだけ有利な条件で解決したいものです。
もっとも、自分で交渉すると、必ずしもうまくいくとは限りません。
特に、相手が弁護士に依頼すると、相手の弁護士から言いくるめられて、不利な条件で和解してしまうケースが多々あります。
そんなときには、こちらも弁護士をつけましょう。
弁護士が交渉すると、ご自身で対応するよりも有利な条件で解決しやすくなるからです。
弁護士の活動により、ご本人が期待していた以上に慰謝料を獲得できるケースも少なくありません。
有利な条件で解決しやすくなる点も、弁護士に依頼するメリットの1つです。
6 ストレスを減らすことができる
不倫の慰謝料請求をするときには、大変なストレスがかかるものです。
相手からの返答を受けるたびに精神的ダメージを受ける方が少なくありません。
相手が真剣に対応しなかったり、開き直って「払わない」などと言ってきたりした場合にもストレスになるでしょう。
弁護士に依頼すると、相手とのやり取りは弁護士がすべて行うのでストレスが大きく軽減されます。
慰謝料請求に疲れてしまった場合や自分で相手と直接やりとりしたくない場合、早めに弁護士に依頼しましょう。
7 相手が支払わない場合も対応できる
不倫相手によっては、慰謝料請求をしても「払わない」と開き直るケースがあります。「不倫なんかしていない」と言われて「不倫を否定される」事例も少なくありません。そんなときには、訴訟をして慰謝料請求する必要があります。
もっとも、ご自身で訴訟を提起することは難しいでしょう。
弁護士に依頼すると、示談が決裂して訴訟を提起する段階になっても安心です。
訴訟を避けるために、無理に不利な条件で示談に応じる必要もありません。
弁護士に依頼すると、相手が支払わない場合にも効果的に対応できるメリットがあります。
8 差し押さえがやりやすい
訴訟で判決が出たり慰謝料の合意書を公正証書にしたりしていると、相手が払わないときに、相手に差押えの対象となる財産がある場合には、強制執行(預金や給料などの差し押さえ)ができます。
もっとも、法律知識がなければ、どのように差し押さえを進めてよいかわからない方も多いでしょう。
弁護士に依頼すると、スムーズに差し押さえができて不払いとなった慰謝料を回収しやすくなります。
差し押さえがやりやすいことも、弁護士に依頼するメリットの1つです。
京都の益川総合法律事務所では、不倫の慰謝料請求についても取り扱ってきました。配偶者に不倫されてしまったという方は、お気軽にご相談ください。
弁護士の交渉により交通事故の過失割合を40%から20%に下げることに成功した事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、物損、過失割合、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、自動車で走行中、後方を走行していたバイクがご依頼者の自動車を右側から追い越そうとして衝突してきたため、ご依頼者の自動車に損傷を受けました。相手方保険会社より、ご依頼者の過失割合について40%と提示されたところ、事故状況等をふまえて納得がいかないということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
受任後、相手方保険会社に対して、過失割合を40%とする根拠について詳細に聴き取りをしました。その根拠について、事故状況と照らして不合理である部分を指摘するとともに、ご依頼者の心情についても丁寧に説明を行い、粘り強く交渉して過失割合の引き下げを求めたところ、最終的に20%に引き下げることに成功しました。
・コメント
事故状況について、ドライブレコーダーなどの証拠が存在せず、ご依頼者のご希望を実現できるかについては難しい見通しがあった事案でした。弁護士の見通しについても丁寧にお伝えしたところ、ご依頼者からは、このまま示談するのは納得ができないので、もし、結果的に過失割合の引き下げができなかったとしても、お願いしたいと言って頂き、ご依頼を受けました。
保険会社との示談交渉では、ご本人から事故状況について丁寧な聴き取りを行ったことで、相手方保険会社の過失割合の根拠について、不合理である部分を正確に指摘することができ、最終的に過失割合を40%から20%に引き下げることに成功しました。
ご依頼者は、本件の難しさを理解してくださっていたため、過失割合の引き下げに成功したことについて、大変お喜びになり、「依頼して良かったです。」という言葉を頂きました。
交通事故の過失割合については、過去の判決等の蓄積によって定められた基準が存在します。過失割合に納得がいかない場合、この基準を正確に把握し、基準を修正する要素の有無についても検討することが必要となりますが、ご自身でこれを行うことは難しいように思います。
本件のご依頼者のように、過失割合について納得がいかない方は、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談頂いたからといって、ご依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
交通事故の過失割合については、こちらのページで詳しく解説しています。
相続トラブルの解決を弁護士に依頼した方が良い理由
相続トラブルが発生したら、できる限り早い段階で弁護士へ依頼しましょう。
自己判断で対応してしまうと、トラブルが拡大するリスクがあります。
今回は、相続トラブルの解決を弁護士に依頼すべき理由をお伝えします。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 預金を使い込まれた(使い込んだと言われている)
- 遺言書の有効性を争いたい(争われている)
- 遺留分侵害額請求をしたい、された
上記のような状況に陥った方は、ぜひ参考にしてみてください。
1 適切な解決方法がわかる
遺産相続時に発生するトラブルにはさまざまなものがあります。
- 遺産分割協議のトラブル
- 遺留分侵害額請求のトラブル
- 遺言書の有効性に関するトラブル
- 遺産の範囲に関するトラブル
- 相続人の地位に関するトラブル
- 預金使い込みに関するトラブル
巻き込まれてしまえば、貴重な労力も時間もとられますし、精神的ストレスも軽くはありません。
早期に解決するのが得策といえるでしょう。
ただし、ひと言で「相続トラブル」といっても、それぞれ適切な対処方法は異なります。
法的な知識がない状態では、どういった状況でどのような対応をすれば良いか判断しにくいでしょう。
間違った対応をしてしまうと、ご自身の意向に沿った解決にはつながりません。
弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な解決方法をアドバイスしてもらえるので、直接的に解決に向けて進んでいけます。
状況に応じた最適な解決方法がわかる点は、弁護士に相談・依頼する大きなメリットです。
2 感情を抑えてスムーズに解決しやすい
相続トラブルでは、どうしても当事者が感情的になりやすい傾向があります。
相続人同士が親族だからという点が大きいでしょう。
弁護士が間に入れば当事者同士で直接話し合う必要がありません。
弁護士が間に入ることで、当事者が直接的に感情をぶつけ合うことがなくなるので、落ち着いて話をしやすくなり、余計ないさかいを避けて解決しやすくなるというメリットがあります。
3 労力と時間を節約できる
相続トラブルに対応するには、大変な労力と時間がかかります。
知識がなければ、まずは相続に関する法律や税務上の取り扱いを調べなければなりません。
相手と話し合ったり、書面を作成したりする手間も発生するでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が相手と話をしますし、必要な作業はほとんど任せられます。
貴重な労力や時間を別のことに割けるのも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
4 ストレスがかからない
相続トラブルへの対応は非常にストレスのかかるものです。
たとえば、遺産分割協議で相手ともめてしまったら、相続のことを考えるだけで気分が滅入ってしまうという方も少なくありません。
弁護士に対応を依頼すると「法律の専門家が味方になってくれている」という安心感を得られます。
自分で直接対応しなくてすむことから、ストレス軽減につながるでしょう。
遺産相続トラブルが精神的ストレスとなっている方も、早めに弁護士に任せるのが得策です。
5 有利に解決しやすくなる
遺産相続トラブルが発生した場合、どのような解決方法になるのかが重要です。
できれば自分にとって有利な条件で解決したいと考えるでしょう。
もっとも、法的な知識がない状態で対応しても、良い条件で解決できるとは限りません。
自分なりに考えて決断した内容が、後になって、自分にとって最適な解決ではなかったことが発覚するという可能性もあります。
弁護士に依頼をしていれば、将来を見越して「ベストな選択」ができますし、相手方との交渉も有利に進めやすいものです。
より良い選択をして、後悔をしない解決を実現するためにも、ぜひ弁護士に依頼しましょう。
6 調停、審判や訴訟対応も安心
相続トラブルが悪化すると、調停や審判、訴訟などの裁判所の手続きが必要となってしまいます。
これらの裁判手続は複雑なので、自分自身では対応できない方も多いでしょう。
弁護士に依頼していれば、相手との協議や示談交渉などが決裂して審判や訴訟になっても安心です。
7 遺産相続トラブルを弁護士に依頼すべき状況
以下のような状況に陥ったら、遺産相続問題を弁護士に相談しましょう。
- 相続人調査や遺産調査で手間取っている
- 遺産相続の流れがわからない、何から手を付けてよいかわからない
- 遺言書が無効だと思う
- 相手が弁護士をつけたので困っている
- 遺産分割協議で他の相続人と合意できない
- 不公平な遺言や贈与があったので遺留分侵害額請求をしたい
- 相続放棄や限定承認をしたい
- 被相続人の生前や死後に一部の相続人によって預金が使い込まれた(使い込んでいないのに使い込まれたといわれている)
8 相続に関する情報はこちら
こちらに遺産相続に関する情報をまとめていますので、よければ参考にしてみてください。
9 遺産相続を相談する弁護士の選び方
遺産相続トラブルを相談・依頼するなら、相続に力を入れていて、過去の相談・解決実績も高い弁護士を選びましょう。
京都の益川総合法律事務所では、遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、相続関係の事件に力を入れて取り組んでいます。
ともに悩み、ともに解決策を考えて、あなたに最適な選択をするお手伝いをします。
相続トラブルにお困りの場合には、お早めにご相談ください。
高額所得者の養育費、婚姻費用について
年間の給与額が2000万円、あるいは自営収入が1567万円を超える高額所得者の方が養育費や婚姻費用を負担する場合には、養育費や婚姻費用を算出する際に一般的に用いられる算定表の上限額を超えるため、算定表から養育費や婚姻費用の金額が明らかになりません。
養育費や婚姻費用を請求する側もされる側も、正しい算定方法を押さえておく必要があります。
今回は、高額所得者の養育費や婚姻費用についての法的な考え方を、京都の弁護士が解説します。
離婚や別居を検討している方や交渉中の方はぜひ参考にしてみてください。
1 養育費や婚姻費用の算定表には上限がある
一般的に、養育費や婚姻費用を計算する際には、算定表を用います。
算定表とは、お互いの収入額や子どもの人数、年齢に応じて妥当な婚姻費用や養育費の金額をまとめた表です。
ケースごとに算定表にあてはめると、たいていの事案で適切な養育費や婚姻費用の金額を算定できます。
ただし、養育費や婚姻費用の算定表には「上限額」があります。
上限を超える収入を得ている場合、算定表をあてはめて適切な養育費や婚姻費用を算定できません。
具体的には、給与所得者の場合には2000万円、自営収入の場合には1567万円が上限の金額となっています。
2 算定表を超える場合の考え方
養育費や婚姻費用の算定表を超える収入を得ている場合、いくらに設定するべきなのでしょうか。
この問題については、一律の解決方法はありません。
家庭裁判所でも事案に応じた個別的な対応がとられています。
以下のような方法をとるケースが多数です。
(1)算定表の上限とする方法
支払義務者の収入が算定表の上限額を超える場合、基本的には「上限額」を用いるべきという考え方です。
収入が増えたからといって、生活費や子どもにかける費用が無尽蔵に増加し続けるわけではないためです。
年収2000万円程度の場合の養育費が払われれば子どもの養育には十分足りるでしょうし、生活にも困らないでしょう。
この考え方であれば、相手と話し合ったとき、算定表の上限額を採用して養育費や婚姻費用を取り決めて解決できます。
(2)基礎収入割合を下げて個別計算する
家庭裁判所で上限額を超える養育費や婚姻費用を定める際、事情に応じて個別計算するケースもよくあります。
その場合、支払義務者の「基礎収入割合」を一般的な事例より減額し、金額が高くなりすぎないように調整します。
基礎収入割合とは、養育費や婚姻費用の基礎となる部分の割合です。これを減らすことにより、収入が上がったからといって養育費や婚姻費用が無尽蔵に増えていかないように調整できるのです。
ただし、この方法でも上がり方が緩やかなだけで、収入が上がると養育費や婚姻費用が高額になることに違いはありません。
妥当な養育費と婚姻費用の金額はこれまでのご家族の生活状況や子どものおかれた状況などによっても異なります。迷ったら弁護士まで相談しましょう。
3 相手に支払いを求める方法
高額所得者へ養育費や婚姻費用を請求するときには、「基礎収入割合」を減らしてでも個別計算した方が金額は上がります。
請求側としては、できるだけ個別計算を求めるのが得策といえるでしょう。
もっとも、養育費や婚姻費用の計算は簡単ではありません。
自分で計算すると間違ってしまう可能性も高いので、個別計算した金額を払ってほしいなら、弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
4 支払い請求を受けたときの対処方法
年収2000万円を超える高額所得者が養育費や婚姻費用の支払いを求められたとき、相手の言ったとおりの金額を払うべきではありません。
相手は過大な請求をしている可能性があるためです。
相手に弁護士がついていても、養育費や婚姻費用の金額を減額できるケースが少なくありません。
自己判断で請求に応じる前に、弁護士までご相談ください。
5 高額所得者が弁護士に依頼するメリット
高額所得者の離婚を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
(1)婚姻費用や養育費を適正にできる
1つは、婚姻費用や養育費の金額を適正に計算できることです。
ご自身で対応すると、高額になりすぎたり、反対に安くしすぎたりして不利益を受けるリスクが発生します。
不利益を避けるため、弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
(2)財産分与を適正に算定できる
高額所得者の方は、財産分与の金額も高額になりがちです。
当事者同士でもめてしまい、話し合いが難しくなるケースも多いでしょう。
弁護士に依頼すると、法律の考え方に従って財産分与額も正しく計算できます。
払いすぎや不当な減額を防げるのはメリットといえるでしょう。
(3)ストレスの軽減
離婚問題に対応するのは非常にストレスのかかる作業です。
弁護士に任せてしまえば、自分で直接相手方と交渉する必要がないのでストレスも軽減されます。
忙しく働いている方の場合、交渉の手間や時間を削減できるメリットも大きくなるでしょう。
京都の益川総合法律事務所では、離婚案件に力を入れて取り組んでいます。
当事務所は、1983年の創業以来、年収2000万円を超える高額所得者の離婚についての事件についても取り扱ってきており、専門的な知識や対応スキルを有しています。
養育費や婚姻費用、財産分与などにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
高額所得者と離婚するときの知識については、こちらのページで、高額所得者との離婚の解決事例については、こちらのページで詳しく解説しています。
« Older Entries Newer Entries »