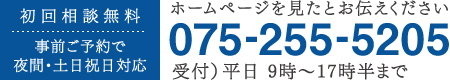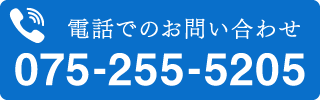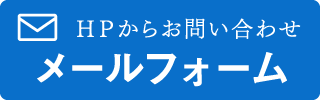コラム
交通事故の素因減額とは
交通事故に遭い示談交渉を進めていると、保険会社から「素因減額」を主張されるケースが少なくありません。
素因減額とは、被害者に身体や精神の疾患があって損害が拡大した場合、賠償金額が減額されることをいいます。
ただし、保険会社の言い分は常に正しいとは限りません。素因減額すべきでないケースにおいても減額を主張されるケースも多々あります。
今回は、交通事故の素因減額がどういったケースで認められるのか、減額を主張されたときの対処方法をお伝えします。
1 素因減額には2種類がある
素因減額は、被害者の身体や精神に原因があって損害が拡大した場合において、被害者にも責任を負わせるために賠償金を減額することです。
具体的には以下の2種類に分かれます。
- 身体的な疾患や既往症がある(身体的素因)
- 性格や精神疾患などがある(心因的素因)
それぞれについての考え方や典型例をみてみましょう。
2 身体的素因でよくある事例
(1)椎間板ヘルニア
被害者に椎間板ヘルニアがあると、保険会社から素因減額を主張されるケースが多々あります。
椎間板ヘルニアとは、背骨にある「椎間板」という組織の一部が飛び出してしまい、手足などに痛みやしびれが出る傷病です。
交通事故以外の日常の動作や加齢によっても生じますが、椎間板ベルニアがある方の場合、追突事故などに遭った際の被害が拡大するケースが少なくありません。
そこで、椎間板ヘルニアがあると、保険会社は素因減額を主張してくるケースが多々あるのです。
ただ、椎間板ヘルニアがあるからといって必ず素因減額すべきとはいえません。
時には椎間板ヘルニアと事故後のケガに因果関係がまったくない事案もあるでしょう。
因果関係があるとしても、どの程度の割合の減額を認めるかはケースバイケースで判断すべきです。
保険会社から素因減額を求められたとき、適切な考え方がわからなければ弁護士へ相談しましょう。
(2)骨粗鬆症の場合
被害者に骨粗鬆症の既往症がある場合にも、素因減額を主張されるケースが多々あります。
確かに被害者が骨粗鬆症の場合、骨折のリスクが高まるのである程度の素因減額を認めるべきとも考えられます。
ただし、骨粗鬆症だからといって、すべてのケースで素因減額すべきではありません。
この点、高齢者の場合には、骨粗鬆症による素因減額は容易に行うべきではないという考え方もあります。
骨粗鬆症が「疾患」と評価される場合には素因減額が行われることになり、事案に応じた判断が重要となります。
(3)身体的な特徴では素因減額されない
被害者が「一般の人よりも首が長い」「一般より太っている」などの身体的特徴を持っている場合、素因減額されるのでしょうか?
判例では、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないというべきである」と判断されています(最判平成8年10月29日)。
したがって、病気ではない単なる身体的な特徴があったとしても基本的には素因減額できないと考えましょう。
保険会社がそういった主張をしてきたら、応じるべきではありません。
3 心因的素因について
心因的素因とは、賠償金を減額すべき事情の中でも被害者の精神的な要因をいいます。
たとえば、事故後に被害者が「うつ病」になって治療意欲を持てなかったために治療期間が長引いたケースなどで、心因的素因による素因減額が行われる可能性があります。
ただし、被害者が「うつ病」だからといってすべての事案で素因減額されるわけではありません。
また、単に一般とは異なる「変わった性格」というだけでも素因減額は行われません。
保険会社から心因的な素因減額を主張されたとき、実際には減額すべきでないケースも多々あります。
どの程度素因減額を適用すべきかについてもケースバイケースの判断が必要です。10%程度の減額が認められた例もあれば、50%の減額が認められた例もあります。
保険会社の提示する減額割合が適正とは限りません。
迷われたら、示談書に署名押印をする前に弁護士へご相談ください。
4 素因減額を主張されたときに弁護士に依頼するメリット
(1)適切に反論できる
保険会社から素因減額を主張されて納得できなくても、法的な知識がなければ反論が難しくなってしまいます。
弁護士であればこれまでの裁判例などをもとに適切に反論できるので、保険会社の言い値による不当な減額を防げるメリットがあります。
(2)賠償金が増額される
弁護士が示談交渉に対応すると、保険会社基準よりも高額な弁護士基準が適用されるので賠償金の金額が大きくアップする例が多々あります。
(3)ストレスが軽減される
ご自身で保険会社と対峙すると大きなストレスがかかります。
うつ病になっている方などにとっては、過大な負担となるでしょう。
弁護士に任せてしまえば、ご自身が保険会社の担当者と話す必要がなくなり、精神的負担も軽減されます。
京都の益川総合法律事務所では、交通事故被害者のサポートに力を入れています。
相手方から素因減額を主張されて納得できない方、示談交渉でお困り事がある方は、お気軽にご相談ください。
入通院慰謝料とは 計算方法や高額な慰謝料を受け取る方法について
交通事故の中でも「人身事故」に遭うと「入通院慰謝料」を請求できるケースが多数です。
後遺症が残らない事案でも、ケガをして入通院治療を受ければ入通院慰謝料を請求できます。
ただし、入通院慰謝料の計算方法には複数の基準があり、ケースによっては減額されてしまう可能性もあります。
今回は入通院慰謝料とはどういったものなのか、計算方法や減額されるパターン、なるべく高額な入通院慰謝料を払ってもらう方法を弁護士が解説します。
1 入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者がケガをしたときに請求できる慰謝料です。
入通院した期間が長くなると金額が上がり、傷害を負ったら発生するので「傷害慰謝料」ともよばれます。
人身事故の被害に遭ったら、基本的に入通院慰謝料を請求できると考えましょう。
ただし、請求するには「入通院治療」を受けなければなりません。
事故でケガをしても病院に行かずに済ませてしまうと入通院慰謝料を請求できなくなるので、忙しくても軽傷でも必ず通院しましょう。
2 入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料には3種類の計算方法があり、それぞれ金額が異なってきます。
ここでは、主に自賠責保険の計算基準である「自賠責基準」と弁護士や裁判所が採用する「弁護士基準」における入通院慰謝料計算方法をお伝えします。
(1)自賠責基準
自賠責基準の場合、入通院慰謝料の金額は「1日あたり4300円」です。
入院でも通院でも違いはありません。これを日数分請求できます。
入通院の日数については、基本的に「入通院治療を受けていた期間」に相当する日数です。
ただし、実通院日数が入通院治療を受けていた期間よりも減ると「実通院日数×2」が通院日数の基準となり、入通院慰謝料が減額されます。
入通院慰謝料=4300円×入通院日数
入通院日数は以下のどちらか少ない方の日数
- 入通院にかかった日数
- 実通院日数×2
計算の具体例
事故でむちうちとなり、3か月(90日間)通院したケース。通院日数は70日。
この場合、90日を基準にして計算するので、入通院慰謝料額は90日×4300円=387000円となります。
事故でむちうちとなり、3か月(90日間)通院したケース。通院日数は35日。
この場合、35日の2倍である70日を基準にして計算するので、入通院慰謝料額は70×4300円=301000円となります。
(2)弁護士基準
弁護士が示談交渉する際に適用する弁護士基準では、「軽傷」かそれ以外の「通常程度のケガ」かによって金額が変わります。
軽症の場合、通常程度のケガに比べて3分の2程度に入通院慰謝料が減額されます。
また、入院時には通院時よりも慰謝料が上がります。
軽傷の場合の入通院慰謝料(単位:万円)
| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
通常程度のケガをした場合の入通院慰謝料(単位:万円)
| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
| 6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
| 10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
また、弁護士基準でも、実通院日数が少ないと入通院慰謝料を減額される可能性があります。
軽傷の場合、実通院日数の3倍程度、通常程度のケガの場合には実通院日数の3.5倍程度として計算されます。
(3)任意保険基準
任意保険会社が示談交渉する際に用いるのが任意保険基準で、各任意保険会社により、計算方法が異なります。
ただし一定の相場はあり、だいたい自賠責基準より多少高い程度に設定されている例が多数となっています。
いずれにせよ、弁護士基準と比べると大幅に低くなると考えましょう。
3 高額な入通院慰謝料を払ってもらう方法
(1)自己判断で通院をやめない
入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて払われるものです。
自己判断によって途中で通院を打ち切ると、そこまでの分しか支払われず金額が減額されてしまうので注意しましょう。
医師が「症状固定」または「完治」と判断し、治療が終了するまできちんと通院を継続することが大切です。
(2)適切な頻度で通院する
通院期間が長くても、実通院日数が少ない場合には、入通院慰謝料は減額されます。
必要性があることが前提ですが、最低でも週に1、2回は通院するのがよいでしょう。
(3)弁護士基準で計算する
入通院慰謝料を弁護士基準で計算することも重要です。
他の基準をあてはめると大幅に減額されるので、人身事故の示談交渉は弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
京都の益川総合法律事務所では交通事故被害者のサポートに積極的に取り組んでいます。
交通事故でケガをされて慰謝料請求をしたい方、保険会社との示談交渉を有利に進めたいという方はお早めに弁護士までご相談ください。
会社が従業員へ損害賠償請求ができるケースと懲戒解雇について
従業員がミスをして会社に迷惑をかけた場合、会社は従業員へ損害賠償請求ができる可能性があります。
ただし、すべてのケースで損害賠償請求できるとは限りません。
今回は、従業員のミスに対する損害賠償請求の可否や従業員の責任の限度について、弁護士が解説します。
従業員から迷惑をかけられてお困りの経営者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
1 従業員に損害賠償請求できる2つの法的根拠
従業員が会社に迷惑をかけたとき、一定要件を満たせば会社は従業員へ損害賠償請求ができます。
法的根拠は、以下の2種類です。
(1)債務不履行
従業員と会社は、雇用契約を締結しています。
従業員は契約にもとづいて、会社へ労働力を適切な方法で提供しなければなりません。
それにもかかわらず、会社に迷惑をかける不適切な行動をとることは、「債務不履行」となります。
そこで、会社は従業員に対して債務不履行責任にもとづき損害賠償請求ができます。
(2)不法行為責任
従業員が故意や過失によって違法行為を行い、会社に損害を発生させると「不法行為責任」が成立します。
この場合にも、会社は不法行為にもとづく損害賠償請求として、従業員へ損害賠償請求できます。
2 従業員の賠償責任は制限される
従業員がミスによって会社に損害を発生させたとしても、すべてのケースで会社が損害賠償請求をできるとは限りません。
裁判例においては、「責任制限の法理」という考え方により、従業員の責任が軽減されるためです。
従業員は、会社の命令に従って仕事をしており、会社は従業員の労働によって利益を受けています。
また、従業員は会社の命令に従って危険業務につく可能性もあります。会社と従業員の経済力の差も重大であり、この点についても意識しなければなりません。
それにもかかわらず、ミスをした場合に限って従業員に全面的な損害賠償義務を負わせるのは信義則に反するといえるでしょう。
3 従業員に損害賠償責任が発生する基準とは
実際にどういったケースで従業員に損害賠償義務が発生するのか、みてみましょう。
(1)従業員の過失の程度が重い
従業員のミスが重大であれば、従業員側に責任が認められる可能性が高くなります。
一方、軽度なミスであれば責任は限定されます。
労働条件や施設の状況、会社による指導監督の方法なども考慮されます。
(2)会社の管理体制に問題がなかった
会社の管理体制に問題があったなら、会社が損害についての責任をとるべきです。
一方、管理体制に問題がなければ従業員側に問題があったと考えるべきでしょう。
業務の性質、業務の形態、長時間労働や深夜勤務がなかったか、保険加入の有無なども考慮されます。
(3)ミスを防止する措置をとっていた
会社が従業員のミスを防止する措置を適切にとっていたなら、従業員側に責任があると考えられます。
会社が過去の同じようなミスに注意をした経緯があるか、再発防止措置をとっていたのかなども考慮されます。
4 会社が従業員へ損害賠償請求できるケースの具体例
以下のような事例においては通常、会社側が従業員へ損害賠償請求できると考えましょう。
- 金融機関で従業員が自己判断で与信枠を超えて貸し付けた
- 従業員が会社のお金を横領した
- 従業員が相手と結託して架空の貸付を行った
- 検査員が支店長の横領や架空貸し付けを見抜けなかった
- 居眠りによって不良品を生じさせた
- 不注意で宝石類が入ったカバンを盗まれた
- 仕様と異なる注文書が提示されたのに見逃した
- 現場監督を怠って越境した伐採が行われてしまった
- 請求書を送り忘れて債権回収できなくなってしまった
5 損害の全てを賠償されるとは限らない
従業員に損害賠償責任が発生するとしても、全額の賠償が認められるとは限りません。
会社による管理が不十分だったケースなどでは、会社にも一定の責任を負わせるべきだからです。
発生した損害のうち、どの程度が賠償の対象になるかは個別に判断されます。
正確に算定するには過去の裁判例と照らし合わせる必要があるので、迷ったときには弁護士へ相談してみてください。
6 ミスをした従業員を懲戒解雇できる場合
従業員がミスをして会社に迷惑をかけた場合、懲戒解雇できる可能性があります。
ただし、常に懲戒解雇が有効になるとは限りません。以下の要件を満たす必要があります。
- 懲戒に関する就業規則の規定がある
- 会社へ損害を与えることが懲戒事由となっている
- 懲戒解雇が相当なほどの重大なミスである
そもそも、就業規則で懲戒に関する規定がなければ懲戒解雇はできません。
また、従業員の行為に対し、重すぎる処分も無効となってしまいます。
無効な懲戒解雇を行うと、後に従業員から「不当解雇」と主張されて労働審判や労働訴訟を提起されるリスクも発生します。
自己判断で懲戒解雇を行わず、まずは弁護士にアドバイスを求めましょう。
京都の益川総合法律事務所では、各業種、業態、規模の企業の労務管理対策に力を入れています。
従業員のミスや故意によって損害を与えられてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
能力の低い社員への対応方法
社内に能力の低い従業員がいると、経営の負担になるものです。
能力が低いからといって簡単に辞めさせることもできません。
この記事では、京都で企業法務に積極的に取り組む弁護士が、能力の低い「ローパフォーマー」社員への対応方法をお伝えします。
成績の振るわない社員やモチベーションの低い社員にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1 能力の低い社員(ローパフォーマー)とは
どのような会社にも、一定数は能力の低い社員がいるものです。
人は集団になると、上位2割が実績や生産性が高い優秀なグループとなり、6割は平均的、下位2割は実績も生産性も低く劣後するグループになるといわれています。
これを「2-6-2の法則」などともいいます。
いずれにせよ、どんなに注意して採用面接を行ったとしても、一定数の社員が能力不足になるのは避けようがないでしょう。
このように、会社にとって負担となる低能力社員のことを「ローパフォーマー」ともいいます。
2 能力の低い社員(ローパフォーマー)の具体例
- 本人は一生懸命に仕事をしているが、他の社員と比べて明らかに生産性が低い、失敗が多い、仕事が遅い
- 何度注意しても改善されない、注意の意味や目的をわかってくれない
- 本人のモチベーションが低い
- 本人の生産性やモチベーションの低さが周囲の従業員にも波及して悪い影響が及んでいる
3 ローパフォーマー社員を放置するデメリット
社内にローパフォーマー社員が増えるとさまざまなデメリットがあります。
(1)会社全体の生産性が低下
ローパフォーマーは成績が振るわず、何をさせてもうまくいかないケースが多数です。
能力が低い社員が増えると会社全体の生産性が低下してしまう可能性もあります。
(2)他のメンバーのモチベーション低下
社内にローパフォーマーがいると、他の社員にそのしわ寄せが来ます。
同じ給料をもらっているのに他の社員の負担が重くなってしまうと、他の社員が不満を抱くでしょう。
離職者が発生する可能性もありますし、組織全体のモラルダウンをもたらすケースも少なくありません。
(3)非効率的
ローパフォーマーの行う仕事を他の社員がカバーしなければならないので、業務の流れが非効率的になります。
(4)給料が高すぎて負担になる
ローパフォーマーに与えられる仕事は限定的であるにもかかわらず、簡単に給与カットできるわけではありません。
結果的に、本人の仕事に見合わない高額な報酬や処遇を与えることとなり、企業に負担になります。
4 能力の低い社員への対処方法
社内に能力の低い従業員がいる場合、以下のように対応しましょう。
(1)適正な人事評価制度の構築
まずは、適正な人事評価制度を構築することが重要です。
ローパフォーマーにはローパフォーマーなりの評価を行い、報酬や処遇を決定すれば会社にとっても過度な負担になりません。
他の従業員の待遇がローパフォーマーより良ければ、不満も溜まりにくいでしょう。
(2)指導や研修を積極的に行う
ローパフォーマーへの指導や教育研修を積極的に行うべきです。
能力不足の原因が単に未熟なだけであれば、指導や研修、改善行動の繰り返しによって徐々に状況が変化していく効果も期待できます。
(3)人事の変更で解決できることも
ローパフォーマーが生み出される要因が「上司」や「人間関係」「仕事内容」にあるケースでの対応です。
周囲の人間関係が悪かったり仕事内容が合っていなかったりして本人のモチベーションが上がらず生産性が悪くなっている状態であれば、本人と面談して問題点を把握したうえで、人事や部署を変更してみましょう。
パフォーマンスが改善される可能性があります。
(4)退職勧奨
どうしても状況を改善させられない場合には、本人へ退職勧奨するのも1つの方法です。
本人が退職を受け入れれば、解雇しなくても辞めさせることができます。
ただ、本人が会社に不満を抱いていなければ、退職に合意しにくいでしょう。
退職金を上乗せするなど、一定程度有利な条件を提示しなければ難しい可能性はあります。
(5)最終的には解雇も検討する
退職勧奨をしても受け入れられなかった場合、最終的にはローパフォーマー社員を解雇するしかありません。
ただし、能力が低いからといって簡単に解雇できないので、注意深く進める必要があります。
裁判例でも、能力不足を理由とした解雇については相当厳しい判断が行われています。
具体的には以下のような事情を考慮して、解雇の有効性が判断されるケースが多数です。
- 対象者との労働契約において、求められる能力の内容や程度
- 能力不足が労働契約を継続できないほど重大であるか
- 企業側が対象従業員に対し、改善矯正を促したり努力反省の機会を与えたりしたか、それでも改善されなかったのか
- 今後の指導教育によっても改善可能性の見込みがまったくないのか
解雇は慎重に進めないと後に「不当解雇」として会社側が訴えられるリスクが高いので、事前に弁護士へ相談しましょう。
京都の益川総合法律事務所では、多数の企業に対して、ローパフォーマー対策についての助言を行ってきました。
お悩みの経営者や人事担当者の方がおられましたらお気軽にご相談ください。
職務怠慢な社員への対応方法
社内に職務怠慢な従業員がいると、業務効率が落ちるだけではなく周囲の従業員の士気にも悪影響を与えてしまいます。
かといって、簡単に解雇することもできません。
今回は、職務怠慢な社員による悪影響や具体例、対応のポイントを弁護士がお伝えします。
1 職務怠慢な従業員の特徴、具体例
職務怠慢な従業員の特徴として、以下のようなものがあります。
(1)遅刻や早退、欠勤が多い
遅刻や早退、欠勤が多いのは職務怠慢社員の大きな特徴です。
無断欠勤を繰り返して周囲の従業員に迷惑をかける人も少なくありません。
本人だけではなく他の従業員の業務効率まで落ちてしまい、会社全体の問題になる事例もあります。
(2)与えられた仕事をしない
職務怠慢な社員は、可能な限り仕事をしないで済まそうと考えているものです。
十分に余裕をもって仕事を与えても、一向に仕上げてこない人が少なくありません。
なぜできなかったのか聞いても言い訳をするだけで、反省の態度はみられません。
(3)注意されても態度が悪い
あまりに勤務態度が悪いために上司が注意したとしても、態度が悪く聞き入れないのも職務怠慢社員の特徴です。
そのときだけは良い返事をしても、実際には改善されない怠慢社員のパターンもあります。
(4)副業に熱心
副業がすべて悪いわけではありませんが、副業に熱を入れすぎて本業を疎かにする人もいます。
こっそり業務時間内に副業をしている従業員も少なくありません。
(5)会社の備品を私物化する
会社で使っているPCやタブレットなどを持ち帰って私的な目的で使用する人もいます。
このような行動をされると会社の重要な情報が外部に漏れてしまうおそれもあり、会社の信用問題や責任問題になりかねません。
2 職務怠慢だからといって減給や解雇は難しい
労働契約を締結している以上、従業員は労働力を提供しなければなりません。
ただどこまでの労働力を提供すべきか、雇用時に詳細まで取り決めるのは極めて困難でしょう。
また、成績が悪い、多少遅刻や欠勤が目立つというだけでは解雇理由にならないケースが多数です。
減給についても、よほどのことがない限りはできません。
結局、本人が出勤してまがりなりにも仕事をしている以上、企業側としては懲戒や解雇は困難となりがちです。
3 職務怠慢な問題社員への対応のポイント
職務怠慢な社員に対しては、以下のように対応しましょう。
(1)適正な人事評価制度を構築する
まずは、適正な人事評価制度を導入することが重要です。
上司が主観的に評価するのではなく、より客観的な評価基準をもうけましょう。
職務怠慢な態度が待遇や役職などに適正に反映されるようになれば、無駄な給与を払う必要はなくなりますし、他の従業員の不満も抑えられやすくなります。
(2)注意や指導を行う
職務怠慢社員に遅刻や早退、欠勤、就業時間中に持ち場を離れる、仕事がいつまでも終わらないなどの問題行動が目につくなら、早い段階で注意や指導を行いましょう。
注意されて初めて問題点に気づくタイプの人もいます。
また、注意や指導を行っても改善されなかったという経過により、後に解雇が認められやすくなるケースもよくあります。
注意や指導を行う際には、書面に残したりメールなどのデータを取ったりして、証拠を残しましょう。
(3)懲戒を検討する
職務怠慢の程度がひどい場合には、懲戒処分も検討しましょう。
ただ、職務怠慢だからといって当然に懲戒できるとは限りません。
減給するとしても、法により上限が定められています。
問題行動とバランスのとれない懲戒処分を適用すると、不当な懲戒処分として争われるリスクが発生するので、慎重に進めましょう。
(4)退職勧奨する
職務怠慢社員の態度が行き過ぎており、注意しても改善の余地がないなら辞めてもらうしかありません。
ただ、その場合でも、いきなり解雇するのはおすすめしません。
解雇すると、後に「不当解雇」などと主張されて労働審判や訴訟を起こされる可能性もあるからです。
まずは、退職勧奨を行い、自主的な退職を目指しましょう。
退職勧奨を行う場合には、後に「退職を強要された」と主張されないために慎重に進めるべきです。
対象者を取り囲んで退職届を無理に書かせたりしないよう、注意しましょう。
(5)解雇する
退職勧奨を行っても改善しない場合、最終的に解雇を検討するしかありません。
ただ、解雇は必ずしも認められるとは限らないので、まずは法律上の解雇要件を満たすかどうか検討すべきです。
また、要件を満たすように思えても、後に不当解雇といわれないよう慎重に対応する必要があります。
解雇理由を明確にして解雇予告を行うか解雇予告手当を支給し、法律上問題のない方法で手続きを進めましょう。
職務怠慢社員に対応するには、状況に応じて段階的に手続きを進めていく必要があります。
自社のみで対応するとトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
お困りの際には、京都の益川総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
企業へ内容証明郵便が送られてきた場合の対処方法
従業員とのトラブルが生じると、企業宛に内容証明郵便が送られてくるケースが多々あります。
内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる手渡し式の郵便です。
差し押さえなどの法的な効力が生じるものではありませんが、発信者の強固な意思を伝える手段として用いられ、受け取った側に大きなプレッシャーがかかるケースも少なくありません。
今回は、企業が従業員や元従業員から内容証明郵便を受け取ったときの対処方法をお伝えします。
1 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に相手へ送付したものと同じ控えが残るタイプの郵便です。
郵便局には、一定期間控えが保管され、郵便に記載した内容や発信日などの情報を「日本郵便株式会社」が証明してくれます。
内容証明郵便自体には、差し押さえなどの法的効果はありません。
内容証明郵便の場合、普通郵便と違って「手渡し式」となるので、受け取らなければ相手へ返送されます。
2 内容証明郵便が利用されるケース
労働トラブルにおいて内容証明郵便がよく利用されるのは、以下のような場合です。
(1)不当解雇に対する未払い賃金請求や地位確認請求
企業が従業員を解雇すると、しばらくして内容証明郵便が送られてくるケースがよくあります。
解雇を無効と主張し、不払いとなっている給料の支払いを求めたり、地位の確認を請求したりするものです。
(2)未払い残業代請求
「残業代が適正に払われていない」と従業員側が考えている場合、未払い残業代の請求が内容証明郵便で行われる事例が多々あります。
(3)慰謝料請求や損害賠償請求
労災が発生した場合などには、従業員が会社側へ損害賠償請求してくるケースがあります。
その場合にも、慰謝料を含めた賠償金を内容証明郵便で請求される事例が多数です。
3 内容証明郵便と消滅時効の関係
内容証明郵便で請求すると、6か月間、時効の完成が猶予されます。
猶予されている間に裁判を起こせば、終了までの間は時効は完成せず、判決が確定したり、和解が成立したりすると、時効が新たに進行を始めます。
残業代を長期にわたって支払いをしていない場合、時効の成立間際になって内容証明郵便が送られてきたら要注意です。
引き続いて訴訟を起こされる可能性が高いと考えましょう。
4 内容証明郵便が送られてきたときの対処方法
(1)事実関係を確認
まずは、相手の言い分が正しいのか、確認しましょう。
たとえば、残業代請求をされた場合には、計算が間違っているケースも多々あります。
また、相手が「不当解雇」と主張していても、解雇が正当であるというケースが少なくありません。
自社の対応に問題があるといえるのか、法律的な視点から検証しましょう。
自社のみで判断がつきにくい場合、弁護士までご相談ください。
(2)返答する
事実関係の確認が終わったら、結果に応じて相手へ返答しましょう。
相手の言い分が明らかに間違っていたら、要求は断るべきです。
一方、相手の言い分に理由がある場合でも、どこまで妥協できるのか考えて書面で返事を出しましょう。
(3)交渉する
返答をしたら、具体的な解決方法について相手と交渉を進めましょう。
たとえば、未払い賃金がある場合、いくらをいつまでに支払うのかなどを決めます。
合意ができたら合意書を作成し、約束のとおりの支払いを行いましょう。
なお、相手の言い分にまったく理由がない場合、支払う必要はありません。
5 内容証明郵便への対応を弁護士に相談するメリット
従業員から内容証明郵便が届いたら、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。
以下では、弁護士に相談するメリットをお伝えします。
(1)適切な対処方法がわかる
内容証明郵便が送られてきたときにとるべき対応は、事案によって異なります。
そもそも、残業代請求なのか、解雇トラブルなのか労災関係なのかにより、調査や返答方法も変わってくるでしょう。
相手の言い分について、法的な観点から内容を精査する必要があります。
弁護士に相談すると、状況に応じた最適なアドバイスを受けられるので、不利益を最小限にとどめつつ早期解決が可能となるのでメリットがあるでしょう。
(2)交渉を任せられる
従業員や元従業員から内容証明郵便が送られてきたら、相手と交渉しなければならないケースが多数です。
従業員側が弁護士をつけている事例も少なくありません。
自社で対応すると不利になってしまう可能性がありますし、余計な労力を割かれてしまうでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士が窓口となって交渉に対応するので、依頼者である企業に余分な手間がかかりません。
相手に弁護士がついていても不利になる心配はなく、企業法務に詳しい弁護士に依頼するとむしろ有利に進められるケースも多々あります。
(3)訴訟や労働審判にも対応できる
労働者側とトラブルになると、訴訟や労働審判を申し立てられるケースも少なくありません。
自社のみで裁判手続に対応するのは大変ですが、弁護士に任せれば適正に対応できます。
弁護士は法律家としての専門的な見地から依頼企業にとって最大限に有利となる解決を目指すので、安心して任せることができるでしょう。
京都の益川総合法律事務所は企業法務に力を入れて取り組んでいます。
内容証明郵便が届いて困惑されている経営者やご担当者の方は、お気軽にご相談ください。
セクハラとは 定義、具体例と対策について
近年では、各企業に「はたらきやすい職場づくり」が求められています。
社内でセクハラが横行していると、こうした社会全体の流れに逆らうことになりますし、法律でも各企業へ向けてセクハラ防止のための措置が求められています。
この記事では、セクハラとはなにか、定義や具体例、企業がとるべき対策をお伝えします。
セクハラをはじめとしたハラスメント対策の担当者の方や社内セクハラをなくしたい経営者の方はぜひ参考にしてください。
1 セクハラの定義
まずは、セクハラの定義を確認しましょう。
厚生労働省によると、職場におけるセクシャルハラスメントについて、次のように定義づけられています。
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること。
セクハラに該当するには、①「職場」において行われること、②「労働者」の意に反すること、③「性的な言動」であることの3つの要件にあてはまる必要があります。
以下で、それぞれの要件について個別に検討しましょう。
なお、各企業には男女雇用機会均等法により、セクハラ対策が義務づけられています。
(1)「職場」とは
「職場」とは、労働者が業務を行う場所全般をいいます。
日常的に仕事をしているオフィスに限らず、取引先の事務所や出張先、顧客の自宅なども職場に該当します。
勤務時間外の接待や宴会などであっても、実質的に職務の延長といえる場合には「職場」に該当する可能性があります。
(2)「労働者」とは
セクハラの対象となるのは「労働者」です。
正社員だけではなくパートタイマーやアルバイト、契約社員などの非正規労働者も労働者に含まれます。
事業者が雇用する労働者のすべてをいいます。
(3)「性的な言動」とは
性的な内容の発言や性的な行動を指します。
また、セクハラの行為者になり得るのは、事業主や上司に限りません。
同僚や部下、取引先や顧客なども広くセクハラの加害者となる可能性があります。
病院で患者が看護師や医師にセクハラする場合もありますし、学校において、生徒が先生へセクハラ行為をするケースも考えられます。
また、セクハラは男性から女性に対して行われるものだけではなく、女性から男性に行う場合、女性から女性に対して行う場合、男性から男性に行う場合についても含まれます。
2 セクハラの2類型
セクハラは「対価型」と「環境型」の2種類に分類されます。
対価型とは、性的な言動に対して労働者が抵抗を示したことに起因して不利益を与えるものです。
たとえば、経営者が女性従業員をホテルに誘ったところ、断られたので解雇する場合などが該当します。
環境型は、職場内で性的な言動を行って職場環境を悪化させ、労働者が労働意欲を減退させている状態をいいます。
たとえば、女性の裸のポスターを貼って女性労働者が苦痛に感じ、仕事が手につかない場合などが該当します。
セクハラの分類については、こちらの記事に詳しく説明しているので、よければご参照ください。
3 セクハラの具体例
以下のような行為はすべてセクハラに該当します。
- 労働者の意に反して胸や腰などの体を触る
- 労働者が明確に拒否しているのに食事に誘う、ホテルに誘う
- 上司が派遣社員の女性をデートに誘い、断られたので労働契約の更新を拒否した
- 同僚が取引先で女性労働者に関する性的な噂を流したので、女性労働者が苦痛に感じて仕事に手がつかなくなった
- 女性労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚がパソコンでアダルトサイトを閲覧しているので、女性労働者が苦痛を感じて業務に専念できない状態になっている
妊娠や出産、育児休暇や介護休暇の取得に関する妨害や嫌がらせもハラスメント行為の一種として禁止されるので、やってしまわないように注意しましょう。
4 セクハラの対策方法
企業がセクハラを防止するため、以下のような行動をとるべきです。
(1)経営者が率先してセクハラを認めない態度をとる
まずは、経営者本人が率先してセクハラを認めない態度を明らかにしましょう。
朝礼の席でセクハラを認めないことについて言及したり、広報誌などの社内報に掲載したりする方法が考えられます。
(2)社員研修を行う
社員に対し、どういった行動がセクハラになるのか明らかにするための研修を行いましょう。
(3)専門の相談窓口をもうける
セクハラやマタハラなどのハラスメント被害について、気軽に相談できる窓口をもうけましょう。相談担当者の養成も必要となります。
(4)相談に対して調査を行い、適切な措置をとる
従業員からセクハラの相談を受けたら、事実関係を調査して適切に対応しなければなりません。
聞き取りや調査の際には、被害者や関係者のプライバシーにも配慮して、協力をきっかけに不利益を受ける結果とならないように注意しましょう。
(5)再発防止策をとる
対応が済んだら再発防止策をとる必要があります。実際にセクハラが起こっていた場合はもちろん、セクハラを確認できなかった場合でも「なぜ相談が持ち込まれたのか」検証し、再発防止策をとらねばなりません。
京都の益川総合法律事務所では、企業に対する法務サポートに力を入れています。
セクハラ対策にお悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
パワハラとは 定義、具体例と対策について
社内でパワハラが横行すると、従業員のモチベーションが低下したり世間の信用が失われたりして、会社に大きなリスクが発生するでしょう。
パワハラを防止するにはどういった行為がパワハラになるのか、定義や具体例、放置するリスクを理解しておく必要があります。
今回は、パワハラとはなにか、パワハラを予防するための対処方法を弁護士がお伝えします。
経営者やご担当の方はぜひ参考にしてみてください。
1 パワハラの定義
厚生労働省によると、パワハラは以下のように定義されています。
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの。
「職場」とは、労働者が業務を行う場所です。
勤務時間外の懇親、接待の場や社員用の寮などであっても職場に該当する可能性があります。
「労働者」とは、正規雇用労働者のみならず、パートタイマーやアルバイト、契約社員などの非正規雇用者も含まれます。
「優越的な関係」については、上司部下の関係のみとは限りません。同僚同士や部下から上司へのパワハラもありえます。
「業務として必要かつ相当な範囲を超えたもの」でなければならないので、客観的に業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラになりません。
「労働者の就業環境が害される」とは、加害者の言動によって労働者が身体的や精神的苦痛を与えられて就業環境が不快となったために能力を十分発揮できなくなるなどの支障が生じることをいいます。
2 パワハラの類型と具体例
厚生労働省によると、パワハラは以下の6類型に分類されます。類型ごとの具体例も合わせてみてみましょう。
(1)身体的な攻撃
殴られる、蹴られる、胸ぐらをつかまれるなど
(2)精神的な攻撃
同僚の前で侮辱された
皆の前で、ささいなミスについて大声で叱責された
必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱られたなど
(3)人間関係からの切り離し
先輩や上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない
(4)過大な要求
終業間際なのに、とうてい終わらない質量の仕事を毎回押しつけられる
常に達成不可能な営業ノルマを課される
(5)過小な要求
事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ
コピーするだけの仕事しか与えられないなど
(6)個の侵害
休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる
パワハラの類型や具体例についてはこちらで詳しく解説していますので、よければご覧ください。
3 パワハラを放置するリスク
社内におけるパワハラを放置していると、以下のようなリスクが発生します。
(1)モチベーション低下
就業先でパワハラが横行していると、従業員としては仕事へのモチベーションを失ってしまうでしょう。
生産性が落ち込んでしまうリスクが発生します。
(2)離職者の発生
パワハラの被害者がうつ病などの精神病になると、仕事を続けられなくなるケースが少なくありません。
周囲の従業員も会社に見切りをつけてやめてしまう可能性があります。
(3)被害者からの損害賠償請求
パワハラの被害者がうつ病になったり自殺したりすると、被害者側から会社へと損害賠償請求されるリスクも発生します。
(4)信用低下、レピュテーションリスク
社内でパワハラが横行していると、従業員がSNSなどへ投稿する可能性もあります。
情報が世間へ拡散されると企業への信用が低下してしまい、レピュテーションリスクが発生するでしょう。
商品やサービスが売れにくくなったり、新規採用が難しくなったりするリスクがあります。
4 パワハラへの対策方法
(1)パワハラを許さない態度を表明
まずは、経営者として、社内全体へ「パワハラを許さない」という態度を明らかにすべきです。
経営者が率先してパワハラを認めない風土を作ることで、従業員も「パワハラ行為をしてはならない」と意識付けられます。
(2)社内研修を行う
どういった行為がパワハラとなるのか、パワハラにどういったリスクがあるのか社員へ教育指導しましょう。
折に触れて研修を開くのも効果的です。
(3)相談窓口の設置
パワハラ専門の相談窓口を設置して、問題が発生したときに気軽に相談できる環境を用意しましょう。セクハラやマタハラなどのハラスメント問題と同じ窓口にしても構いません。
ただし、相談内容は漏えいしないように注意すべきです。
相談を受けたらプライバシーへも配慮したうえで、速やかに事実関係の調査を進めましょう。
(4)対応と再発防止
パワハラの事実関係調査が終わったら、被害者や加害者への対応をしなければなりません。
実際にパワハラが起こっていたら、被害者を保護して加害者へ何らかの処置を行いましょう。
ただし、懲戒解雇などの厳しい処分を適用すると問題になるケースも多いので、法律上の要件を満たすかどうか慎重に検討すべきです。
問題が発生していた場合もしていなかった場合にも、原因を究明して再発防止の措置を取りましょう。
京都の益川総合法律事務所は、企業法務に積極的に取り組んでいます。
パワハラ対策に関心をお持ちの企業の方はお早めにご相談ください。
パワハラ防止法により企業に求められる対策
2022年4月から、中小企業もパワハラ防止措置の義務化の対象となりました。
中小企業もパワハラ対策をきちんと行わないと、法律違反となってしまうリスクが生じるため、法律の内容を知って慎重に対応しましょう。
今回は、パワハラ防止法の概要と企業に求められる対応について、弁護士が解説します。
社内のパワ-ハラスメント対策にお役立てください。
1 パワハラ防止法とは
「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)は、企業内のパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために定められた法律です。
大企業については、すでに2020年6月1日から施行されました。
中小企業については、約2年の猶予が与えられ、2022年4月1日に施行されました。
パワハラ防止法により、企業はパワハラ防止対策をとらねばなりません。
パワハラ防止法の目的、制定された理由
パワハラ防止法の目的は、日本企業における深刻なパワハラ問題を解消するためです。
パワハラ問題は、数ある労働問題の中でも相談件数が多く、パワハラを理由にうつ病になったり離職したりする労働者が少なくありません。
時には、自殺に至る痛ましいケースもあります。
貴重な人材が失われることは企業にとってもマイナスとなるでしょう。
そこで、働き方改革の一環として「パワハラ防止法」を定め、パワハラを撲滅しようとしているのです。
2 パワハラに該当する行為
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職務上の地位や人間関係などの「優位性」を背景として、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、あるいは職場環境を悪化させる行為をいいます。
以下の6つの類型があります。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
企業がパワハラを防ぐには、まずは「どういった行動がパワハラになるのか」経営者側が正確に理解すべきといえるでしょう。
3 パワハラが生じたときの会社の責任
社内でパワハラが発生すると、加害者だけではなく企業にも責任が発生する可能性があります。
パワハラ加害者は通常、会社の被用者なので、使用者である会社には「使用者責任(民法715条)」が発生するケースが多数です。
また、職場環境をきちんと整備しなかったことにより、安全配慮義務違反による債務不履行責任が発生する可能性もあります。
社内でパワハラが発生すると、他の従業員のモチベーションも低下するでしょうし、離職者が発生する可能性も高まります。
社会での評判が低下すると、新規採用にも影響が及ぶでしょう。
パワハラ防止法により、企業には従業員の訴えに対して適切に対応するよう求められます。
現代の日本企業において、パワハラ対策は必須といえるでしょう。
4 企業がパワハラ防止法に対応する方法
パワハラ防止法に対応するため企業として具体的に何をすればよいのか、お伝えします。
(1)経営者がパワハラを許さない態度を明示、従業員への教育や啓蒙を行う
まずは経営者サイドとして、パワハラを許さない態度を明らかにしましょう。
朝礼や広報誌などにおいて「パワハラを認めない」と明言したり、折に触れてパワハラ防止に言及したりするのも有効です。
また、従業員に対してはパワハラを行わないよう教育や啓蒙を行いましょう。
たとえば、就業規則でパワハラを禁止する、研修を行ってパワハラについての理解を深めるなどの対応方法があります。
(2)相談窓口の設置
パワハラ被害に遭った従業員が利用できる相談窓口を設置する必要があります。
いつでも気軽に相談できる体制を整えて、従業員に相談窓口の存在を知らせましょう。
相談したことや相談内容の秘密が守られる必要もあります。
(3)事実調査と加害者・被害者への適切な措置
実際に相談を受けた場合には、実際にパワハラが起こったのか事実関係を調査しなければなりません。
関係者のプライバシーや被害者の精神状態などにも配慮しながら、慎重に聞き取りなどの調査を進めましょう。
調査の結果、パワハラが発生したと明らかになれば、人事配置の見直しや加害者への措置を検討すべきです。
ただし、パワハラ行動の内容に対して加害者への処分が重すぎると違法となってしまう可能性があるので、加害者への懲戒処分を適用する際には慎重に対応しなければなりません。
特に、懲戒解雇までできるケースは限定されるので、迷ったときには弁護士に相談する方がよいでしょう。
一方、パワハラの事実を確認できない場合には加害者とされた労働者へ不利益な措置をとってはなりません。
(4)再発防止措置
パワハラ相談があった場合、企業は再発防止措置をとらねばなりません。
なぜパワハラ問題が生じてしまったのか、原因を明らかにして取り除く努力をしましょう
実際にパワハラがあったという認定にならなかった場合であっても、相談が行われたら再発防止措置をとるべきです。
同じようなトラブルが起こらないように対策を練り、実行しましょう。
(5)プライバシー保護と不利益取扱禁止
パワハラ相談への対応方法にも慎重さが求められます。
被害者や関係者などのプライバシーを守る必要がありますし、相談や調査への協力をしたことで不利益を受けるようなことがあってはなりません。
5 パワハラ対策は弁護士へ相談を
企業が法的リスクを避けて適正に労働安全管理を進めるには、労働実務に長けた弁護士によるサポートが必要不可欠です。
企業側の労働法務に詳しい弁護士の意見を聞きながら対応していれば法律違反にならず、パワハラ対策も十分にできるでしょう。
京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働相談に力を入れて取り組んでいます。パワハラやセクハラなどのハラスメント対策、労務管理に詳しい弁護士をお探しの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
退職勧奨とは 進め方について弁護士が解説
問題社員を解雇したい場合には、解雇通知を送る前に「退職勧奨」をするようにお勧めします。
退職勧奨に成功して従業員が自主的に退職すれば、解雇トラブルのリスクを大きく軽減できるからです。
今回は、退職勧奨とはどういった手続きなのか、適切な進め方も合わせて弁護士が解説します。退職させたい問題社員を抱えている企業の方はぜひ参考にしてみてください。
1 退職勧奨とは
退職勧奨とは、雇用者が従業員に対して自主的な退職を促すことです。
あくまで退職を勧めるだけであり、強制はできません。
解雇と退職勧奨の違い
解雇は企業側が一方的に労働契約を打ち切るのに対し、退職勧奨の場合には従業員側から自主的に退職するものです。
企業側が労働者を解雇するには労働契約法上の厳しい要件を満たさねばなりません。
一方、退職勧奨であれば解雇の要件がなくても問題社員を辞めさせることができます。
解雇トラブルを防ぎつつ問題社員を退社させるのが、退職勧奨の目的といえるでしょう。
2 退職勧奨のメリット
退職勧奨には、以下のようなメリットがあります。
(1)解雇の要件がなくても退社させられる
労働法により労働者は強く保護されています。雇用者側が解雇するには、労働関係法令の定める厳格な要件を満たさねばなりません。
一般的な普通解雇であれば、解雇の客観的合理的理由や社会的相当性が必要です。
また、法律上解雇できないケースもありますし、解雇予告または解雇予告手当の支給もしなければなりません。
退職勧奨による自主退職であれば、そういった法律上の規定は適用されず、退社を実現しやすいメリットがあります。
(2)不当解雇と主張されるリスクが低い
解雇をすると、後に従業員が「不当解雇」として訴えてくる可能性があります。
裁判で「解雇要件を満たしていない」と判断されると解雇が無効となり、未払い賃金などの支払いを命じられてしまいます。
未払い賃金には遅延損害金も付加されるので、予想外に高額になるケースも少なくありません。
退職勧奨によって従業員が自主的に退職すると、不当解雇と主張されるリスクは大きく軽減されます。
労働審判や労働訴訟に巻き込まれる手間もかからず、不利な審判や判決が出てしまうおそれもありません。
3 退職勧奨の手順
STEP1 退職勧奨の方針を固める
まずは、退職勧奨の対象者や退職を促す理由、スケジュールなどについて方針を固めましょう。
その上で経営者や役員、直属の上司などの関係者において退職勧奨の方針を共有します。
STEP2 対象社員に退職を促す
計画を立てたら対象の従業員に対し、退職を促しましょう。
別室に呼び出して面談を行い、退職を勧めるのが一般的です。
従業員から退職勧奨する理由を尋ねられるケースも多いので、答えられるように事前に理由を検討してまとめておきましょう。
STEP3 退職届を作成させる
従業員が退職に納得したら、退職届を作成させましょう。
書面化しておかないと、後に気が変わって退職させられなくなってしまう可能性があるので、その場で署名押印してもらいましょう。
STEP4 退社後の諸手続きを行う
従業員が退社したら、労働保険や社会保険などの諸手続きをしなければなりません。
社会保険の場合には退社後5日以内、雇用保険は退社後10日以内に資格喪失の届出が必要なので、早めに対応しましょう。
離職票を受け取ったら従業員の分を本人へ送付し、退職金や未払い賃金の支払いなども必要に応じて行う必要があります。
4 退職勧奨を行う際の注意点
退職勧奨の方法を間違えると「違法」となり、退職が無効となってしまう可能性があります。
以下では、退職勧奨を法的に正しい方法で進めるための注意点をお知らせします。
(1)拒否しているのにしつこく退職を勧めない
従業員が退職を拒否しているにもかかわらず、しつこく退職を勧めてはなりません。
従業員が退職勧奨に応じない姿勢を明確に示したことが、違法性の判断について大きな指標となるからです。
(2)暴力的、脅迫的な退職勧奨をしない
対象者が退職しないからといって、暴力的、脅迫的な退職勧奨をしてはなりません。
仕事を与えない、過剰な仕事を与えるなどの嫌がらせをして退社に追い込んでも違法となる可能性があります。
(3)「退職届を作成するまで帰さない」のは違法となる可能性が高い
従業員を別室に呼び出して「退職届を作成するまで帰さない」などと告げて監禁すると、退職強要となって違法と認定される可能性が高まります。
「退職はあくまで任意」という基本を忘れてはなりません。
(4)長時間、頻繁な退職勧奨はしない
1回の面談における説得時間や退職勧奨の頻度についても、注意が必要です。
2時間以上に及ぶ長時間の退職勧奨や頻繁過ぎる退職勧奨が行われると、違法と認定される可能性が高くなります。
合法的に退職勧奨を行い、解雇トラブルを防いで円満退社させるには、法的な知識が必要です。
自己判断で退職を強要してしまい、後に退職が無効になっては意味がありません。
京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働法務への支援体制を整えています。
問題社員の解雇や退職勧奨についても、お気軽にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »