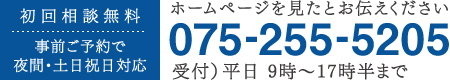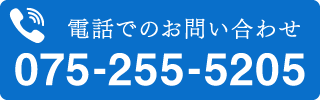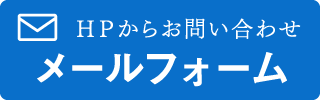コラム
労働問題を未然に防止するためには
過去に、労働トラブルで裁判になったことがある経営者の方の中には、もう従業員との労働問題は発生させたくないと仰る方も多いです。
これは、想像以上に、従業員との裁判が、企業にとって負担だったからでしょう。
今回は、労働問題を未然に防ぐための方法などについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説いたします。
1.なぜ労働問題を未然に防ぐ必要があるのか
企業の目的は、企業活動を通じて、社会に貢献し、利益を生み出すことにあります。
しかし、従業員との間で労働問題が発生しても、この目的には合致しません。
それどころか、従業員との労働問題が発生して、労働審判や裁判になると、これらの準備にかかる会社の負担も大きいです。また、この労働問題が他の従業員に波及したり、士気低下を防ぐためにも、会社としても費用対効果のみを考えて安易に妥協することができないこともあります。
そのため、紛争が発生してから、裁判が終わるまでに2年~3年ほどかかる事案もあるのです。
このように、労働問題が発生すると、会社にとっても大きな負担になってきます。
2.労働問題を未然に防ぐために
2-1.就業規則等の整備や見直し
まずは、就業規則等の整備や見直しを行うことが重要です。
企業の中には、そもそも就業規則がなかったり、昔もらったひな形をそのまま使っているという会社もあります。
しかし、就業規則がなければ、従業員に対する懲戒処分さえ行えないという事態にもなりかねません。
また、労働関係法令は、時代の変化に伴い改正が繰り返されている上、新しい判例も出てきており、これらに合うように就業規則の規定を見直していく必要があります。
2-2.従業員に誓約書の提出を求める
もし、退職後の従業員による、自社の顧客や従業員の引き抜き、秘密の漏洩を懸念されるのであれば、従業員に誓約書を提出してもらうことを検討すべきです。これは、退職後の従業員に対して、競業行為の一部制限を設けたい場合にも同じです。
これらの場合には、従業員の入社時及び退職時に、誓約書を作成してもらいましょう。
この誓約書については、裁判例で無効とされるケースも多いので、無効にされないように弁護士と協議しながら慎重に作成することをお勧めいたします。
3.弁護士と社労士の違い
「労働問題を弁護士と社労士のどちらに相談すれば良いですか?」と聞かれることがありますので、簡単に説明いたします。
社労士は、社会保険の手続きや給与計算、年金相談、労務管理についての専門家です。
社労士も労働関係についての専門化ですが、弁護士との大きな違いは、社労士では労働審判や裁判という紛争には対応できない点にあります。逆に言えば、弁護士は、労働審判や裁判に対応しているからこそ、これらになった時に不利にならないようにアドバイスを行うことが可能です。
そのため、少なくとも、将来の紛争予防も踏まえてアドバイスが欲しい時は、弁護士に相談して頂くのが良いです。
実際に、顧問弁護士と顧問社労士の双方を抱えている企業も多く、弁護士の立場からしても、社労士の先生方と共に、企業発展に貢献しています。
4.最後に
京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働法務への支援体制を整えております。
労働問題を未然に防ぎたいとお考えの企業経営者の方やご担当者の方は、お気軽にご相談ください。
従業員の引き抜きに対する防止策
本ページでは、従業員の引き抜きに対する防止策について、紹介します。
特に、自社の元役員や元従業員、在職中の役員や従業員が転職先に、自社の従業員を引き抜いてくることへの防止策になります。
これまでの記事でも、従業員の引き抜きについて、解説してきましたので、是非参考になさってください。
■これまでの記事
②「従業員の引き抜きを違法と評価した裁判例について、企業側の弁護士が解説」
③「派遣スタッフの引き抜きを違法と評価した裁判例について、会社側の弁護士が解説」
1.誓約書の提出を求める
まずは、従業員の入社時及び退職時に、自社の従業員の引き抜きを行わないとの誓約書の提出を求めることが考えられます。
但し、誓約書もその内容次第では、裁判所から無効とされてしまいますので、誓約書の作成の際には、弁護士に相談の上、作成されてください。
2.就業規則に記載する
次に、就業規則にて、従業員の引き抜きを制限することが考えられます。
退職後も従業員に制限を課す就業規則の効力については、退職後の従業員の自由を不当に制限しない範囲で認められています。
そのため、就業規則の規定の仕方については、気を使う必要がありますが、就業規則にて引き抜きを規制する方法も考えられます。
なお、誓約書と就業規則については、どちらか一方のみではなく、双方で規律しておくことをお勧めしております。
なぜなら、誓約書だけの場合、提出を拒否されてしまったら、引き抜き防止策が打てなくなりますし、就業規則だけの場合には、そもそも従業員が就業規則の内容を理解しているかが分からないためです。就業規則については、作成手続きに不備があるとして、裁判所から効力を否定されている例も見受けられます。
3.引き抜きの計画が判明した場合
自社の元役員や元従業員による引き抜きの計画が判明した場合には、その者(企業)に対して、通知書を送付することが考えられます。この通知書は、弁護士に依頼の上、内容証明郵便の形で送付することが効果的です。
また、実際に、引き抜き行為がされてしまった場合には、相手方に対して、損害賠償請求をしていくことが考えられます。この辺りは、弁護士に相談の上、損害賠償請求が認められるかの見通しも含めて、対応するのが良いです。
4.顧問弁護士の活用も
従業員の引き抜きに対する防止策を打ちたい企業様は、顧問弁護士の活用もご検討ください。顧問弁護士が入れば、当該企業様に合わせて、適切に従業員の引き抜きに対する防止策を講じることができます。
また、当事務所の経験上、顧問弁護士がいた場合には、従業員を引き抜かれることが少なくなります。
これは、上記のような防止策に加えて、引き抜く側も、実際に引き抜き行為をした場合には、その顧問弁護士が活動してくることが分かるためです。
5.最後に
今回は、従業員の引き抜きに対する防止策について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
以前の記事でも解説しましたが、引き抜きに対する損害賠償請求が認められたとしても、その金額は、多くの経営者の方にとっては、割に合わないものになっています。
そのため、可能な限り、従業員の引き抜きを事前に防止する措置を講じた方がよいです。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
従業員の引き抜きについて、お困りの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
裁判所が認める従業員が引き抜かれた際の損害額について
企業運営をしていると、自社の従業員が引き抜かれることもあります。
これまでの記事では、従業員の引き抜きが違法と評価される場合などについて、解説してきました。
■これまでの記事
②「従業員の引き抜きを違法と評価した裁判例について、企業側の弁護士が解説」
③「派遣スタッフの引き抜きを違法と評価した裁判例について、会社側の弁護士が解説」
今回は、従業員の引き抜きが違法と評価された場合に、裁判所が、どのくらいの損害額を認めているのかについて、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説します。経営者の方や、担当者の方は、是非参考になさってください。
1.売上減少分全額が認められるわけではない
従業員を違法に引き抜かれた場合、売上減少分全額を、損害として認めて欲しいと考えるのが通常でしょう。
しかし、裁判例上、売上減少分全額を、損害として認めてくれるわけではありません。
この理由について、裁判例は、下記の理由を挙げています。
①従業員には、退職・転職の自由が認められており、従業員の自由意思による退職・転職によって、企業に発生する損害については、企業が甘受し、その従業員に賠償を請求することができないのが原則であること
②企業としては、適宜の方法で従業員を補充し、その損失を最小限にすべく努めるのが通例であるが、元の状態に業績が回復するまでの期間が長く、またそれまでの経費が多かろうと、企業としてはこれを甘受しなければならないこと
2.裁判例上認められている損害額
裁判例上、従業員の引き抜きが違法と評価された場合には、下記の①から②を差し引いた金額を、損害として認めることが多いです。
■計算式
①引き抜かれた従業員が上げていた粗利益の1か月から3か月分
※粗利益とは、売上高から売上原価(製造原価)を差し引くものです。
②引き抜かれた従業員の給与+各種保険料(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等)のうち原告が負担している部分
・具体例
引き抜かれた従業員が、月150万円の粗利益を上げており、当該従業員の給与と、各種保険料の会社負担分の合計額が月40万円だったとします。
この場合に、裁判所が、3か月分の粗利益を基準に損害額を認定した場合には、330万円の損害賠償請求が認められることになります。
①粗利益の3か月分→月150万円×3か月=450万円
②引き抜かれた従業員の経費→月40万円×3か月=120万円
①450万円-②120万円=330万円
3.7200万円の損害賠償請求を認めた裁判例も
裁判例上、従業員の引き抜きも問題になった事例で、7200万円もの損害賠償請求を認容したケースもあります。
この事例は、クリニックの院長であり、医療法人の理事であった者が、クリニックに極めて近い場所に診療施設を開設して、従業員の引き抜きを行うとともに、患者に対しても転院を働きかけた事例です。
裁判所は、クリニックの経営を左右するほど重大な損害を発生させたとして、当該院長に対して、7200万円もの損害賠償請求を認めました。
この事例では、クリニックが行っていたのが、人工透析であり、人工透析を受ける者という患者の性質上、ある診療施設に通院可能な地域の患者数はおのずから限られているのであるから、クリニックに極めて近い場所に診療施設を開設し、クリニックの患者に転院を働きかければ、クリニックの患者が減少し、その経営に影響を与えることは明らかであったという点が重視されています。
4.最後に
今回は、従業員の引き抜きが違法と評価された場合に、裁判所が、どのくらいの損害額を認めているのかについて、企業側の弁護士が解説しました。
7200万円のケースはさておき、多くの経営者の方にとっては、裁判所が認める損害額は割に合わないものだと思います。
そのため、可能な限り、従業員の引き抜きを事前に防止する措置を講じた方がよいです。
この辺りについては、次回の記事で解説いたします。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
従業員の引き抜きについて、お困りの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
派遣スタッフの引き抜きを違法と評価した裁判例について、会社側の弁護士が解説
企業運営をしていると、自社の元幹部社員が自社の従業員を引き抜いてきたり、同業他社が自社の従業員を引き抜いてくることもあります。
これまでの記事では、①従業員の引き抜きが違法と評価されるか否かの判断基準や、②従業員の引き抜きを違法と評価した実際の裁判例について、解説してきました。
■これまでの記事
②「従業員の引き抜きを違法と評価した裁判例について、企業側の弁護士が解説」
今回は、在職中の幹部社員による、派遣スタッフの引き抜き行為を違法と評価した裁判例について、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説します。経営者の方や、担当者の方は、是非参考になさってください。
1.派遣スタッフの引き抜きが違法か否かの判断基準
まず、どのような場合に、派遣スタッフの引き抜きが違法と評価されるのかについて、簡単に解説します。
引き抜き行為をしてきた相手方が、①自社に在職中の取締役や従業員、②自社を退職した元取締役や元従業員、③同業他社のいずれかで、判断基準は少し変わることになりますが、概ね、下記の場合には、派遣スタッフの引き抜きが違法と評価されることになります。
■判断基準
単なる勧誘の範囲を超えて、社会的相当性を逸脱した方法で引き抜き行為が行われた場合には、引き抜き行為が違法となる。
引き抜き行為が違法と評価された場合には、実際に引き抜き行為をしてきた相手方に対する損害賠償請求が認められることになります。
引き抜きが違法となるか否かの判断基準については、「従業員の引き抜きが違法と評価される場合とは?」の記事で、詳しく解説しています。気になる方は、参考になさってください。
2.派遣スタッフの引き抜きを違法と評価した裁判例
フレックスジャパン・アドバンテック事件(大阪地裁平成14年9月11日判決)では、会社に在職中の幹部社員が、転職先の同業他社に、自身が担当する派遣スタッフを大量に引き抜いた行為の違法性が、問題となりました。
この裁判例では、同業他社への派遣スタッフの大量の引き抜きが、計画的かつ極めて背信的であるとして、①当該引き抜き行為をした幹部社員、及び、②転職先の同業他社への損害賠償請求を認めました。
(1)引き抜き行為をした幹部社員の責任
この裁判例では、幹部社員による引き抜き行為が、「計画的かつ極めて背信的」なものであり、「単なる転職の勧誘にとどまらず、社会的相当性を著しく逸脱した違法な引き抜き行為である」と判断し、幹部社員の損害賠償責任を認めました。
裁判所は、違法性の判断に際して、以下の事実を重視しました。
■裁判所が重視した事実
①引き抜き行為をした者が、会社営業所の責任者という地位にあり、営業活動において中心的な役割を果たすいわゆる幹部社員であったこと
②引き抜き行為をした者も、突然自身が会社を退職すれば、派遣スタッフが一斉に会社を退職することとなり、その結果、会社の業務運営に支障が生じることを認識していたこと
③引き抜き行為をした者が、同業他社への転職が内定していながら、これを会社に隠して引き抜き行為をしていたこと
④引き抜き行為をした者が、突然会社に対して退職届を提出した上、退職に当たって何ら引継ぎ事務も行わなかったこと
⑤引き抜き行為をした者が、派遣スタッフに対して、会社の営業所が閉鎖されるなどと虚偽の情報を伝えて、引き抜き行為をしたこと
⑥引き抜きに際して、転職先への入社祝い金として、派遣スタッフ1人当たり3万円を支給していること
⑦引き抜いた派遣スタッフに対して、会社在職中と同じ派遣先企業への派遣を約束するなどして、会社が受ける影響について配慮していないこと
この裁判例では、上記①から⑦の引き抜き行為の態様が、計画的かつ極めて背信的であったと評価して、幹部社員の損害賠償責任を認めています。
(2)引き抜き行為に加担した同業他社の責任
この裁判例は、引き抜き行為に加担した新雇用主の行為についても、「単なる転職の勧誘の範囲を越え、社会的相当性を著しく逸脱した引き抜き行為を行ったものというべきである」と判断し、新雇用主の損害賠償責任を認めました。
裁判所は、同業他社による下記のような行為を重視して、違法である旨の判断をしました。
■裁判所が重視した事実
①引き抜き行為をした者に対して、自社への入社以前に自社の名刺を作成して渡していること
②会社を退職した派遣スタッフが、同業他社に入社した後は、直ちにこれらの者を元の会社在職時と同様の派遣先企業に派遣していること
③同業他社において、派遣スタッフが自社に入社することを予想して、会社の派遣先であった企業と、派遣に関する契約を締結していたこと
④同業他社において、会社が顧客である派遣先企業と人材を失うことを当然に認識していたこと
⑤派遣スタッフと引き抜き行為をした者との間で、会合が開かれた際に、同業他社の支配下にある会社の代表者を同席させ、その席上で、同業他社への入社祝い金名目の3万円の支給の話があったこと
⑥実際に、引き抜き行為をした者が、派遣スタッフに3万円を支給しており、かかる金員の供与についても、同業他社が承知していたといえること
⑦引き抜き行為をした者が、派遣スタッフに対して転職を勧誘する際に、賃金のベースアップに言及しており、このような発言は同業他社の承認ないし関与がなければできないこと
⑧同業他社は、幹部社員である引き抜き行為をした者が、会社を退職して自社に入社すれば、会社の派遣スタッフもこれに伴って、自社に入社するであろうとの期待を抱いていたこと
⑨同業他社は、引き抜き行為をした者に続く、派遣スタッフではない他の従業員3名の採用については、人件費の点で厳しいと認識していたが、結局、人材派遣業の営業拡大のためこれらの者を雇用したこと。
この裁判例では、上記①から⑨の事情を、総合的に判断すると、同業他社は、引き抜き行為をした者と共謀して、社会的相当性を著しく逸脱した引き抜き行為を行ったものというべきである旨判断されました。
3.最後に
今回は、派遣スタッフの引き抜きを違法と評価した裁判例について、企業側の弁護士が解説しました。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
従業員や派遣スタッフの引き抜きについて、お困りの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
従業員の引き抜きを違法と評価した裁判例について、企業側の弁護士が解説
企業運営をしていると、元役員が自社の従業員を引き抜いてきたり、競合他社が自社の従業員を引き抜いてくることもあります。
前回の記事では、従業員の引き抜きが違法と評価されるか否かの判断基準について、詳細に解説しました(「従業員の引き抜きが違法と評価される場合とは?」)。
今回は、実際に従業員の引き抜きが違法と評価された裁判例について、会社側で労働問題に注力している弁護士が解説します。経営者の方や、担当者の方は、是非参考になさってください。
1.従業員の引き抜きが違法か否かの判断基準
まず、どのような場合に、従業員の引き抜きが違法と評価されるのかについて、簡単に解説します。
引き抜き行為をしてきた相手方が、①在職中の取締役や従業員、②自社の元取締役や元従業員、③競合他社のいずれかで、判断基準は少し変わることになりますが、概ね、下記の場合には、従業員の引き抜きが違法と評価されることになります。
■判断基準
単なる勧誘の範囲を超えて、社会的相当性を逸脱した方法で引き抜き行為が行われた場合には、引き抜き行為が違法となる。
引き抜き行為が違法と評価された場合には、実際に引き抜き行為をしてきた相手方に対する損害賠償請求が認められることになります。
より詳しい内容については、「従業員の引き抜きが違法と評価される場合とは?」の記事にて解説しています。気になる方は、参考になさってください。
2.従業員の引き抜きを違法と評価した裁判例
ラクソン事件(東京地裁平成3年2月25日判決)では、会社に在職中の幹部社員が自身の部下の大多数を、転職先の競合他社に引き抜いた行為の違法性が、問題となりました。
この裁判例では、競合他社への大量の引き抜きが計画的、背信的であるとして、①当該引き抜き行為をした幹部社員、及び、②転職先の競合他社への損害賠償請求を認めました。
この裁判例は、少し古い裁判例にはなりますが、今なお重要な価値がある裁判例ですので、以下では、詳細に、この裁判例を解説していきます。
(1)引き抜き行為をした幹部社員の責任
この裁判例では、幹部社員による引き抜き行為が、「計画的かつ極めて背信的」なものであり、「もはや適法な転職の勧誘に留まらず、社会的相当性を逸脱した違法な引き抜き行為であり、不法行為に該当するものと評価せざるを得ない」と判断し、幹部社員の損害賠償責任を認めました。
裁判所が、違法性の判断に際して、以下の事実を重視しました。
■裁判所が重視した事実
①引き抜き行為をした者が、会社の営業において中心的な役割を果していた幹部社員で、しかも引き抜き行為の直前まで会社の取締役でもあったこと
②引き抜き行為をした者が、部下とともに会社の社運をかけたプロジェクトを任されていたこと
③引き抜き行為をした者も、自身とともに部下が一斉退職すれば、会社の運営に重大な支障が生じることを熟知していたこと
④引き抜き行為の方法も、まず役職者の部下たちに対して移籍を説得したうえ、その説得が成功した後に、会社に知られないように、内密にその下の部下であるセールスマンらの移籍を計画・準備したこと
⑤セールスマンらが移籍を決意する以前から、移籍した後の営業場所を確保したばかりか、あらかじめ営業場所に備品を運搬するなどして、移籍後直ちに営業を行うことができるように準備していたこと
⑥慰安旅行を装って、事情を知らないセールスマンらをまとめて連れ出し、ホテル内の一室で移籍の説得を行ったこと
⑦その翌日には、打合せどおりホテルに来ていた、転職先の会社役員に、移籍先の会社の説明をしてもらったこと
⑧役員に会社説明をしてもらった、その翌日から、早速競合他社の営業所で営業を始め、その後にセールスマンらに被害会社への退職届けを郵送させたこと
この裁判例では、上記①から⑧の引き抜き行為の態様が、計画的かつ極めて背信的であったといわねばならないと評価して、幹部社員の損害賠償責任を認めています。
(2)引き抜き行為に加担した競合他社の責任
この裁判例は、引き抜き行為に加担した新雇用主の行為についても、「単なる転職の勧誘を越えて社会的相当性を逸脱した引抜行為であるといわざるを得ない」と判断し、競合他社の損害賠償責任を認めました。
裁判所は、競合他社の下記のような行為を重視して、違法である旨の判断をしました。
■裁判所が重視した事実
①事前に引き抜き行為をした幹部社員に接触し、被害会社における幹部社員やその部下の役割と、それらが抜けた場合の被害会社の受ける影響を十分認識していながら、幹部社員と集団的移籍のための方法を協議していたこと
②従業員の大量移籍が、あくまで被害会社に内密に行われることを前提にして、いわば不意打ち的な集団移籍の計画であったこと
③セールスマンらに移籍の勧誘がされる前に、被害会社の幹部社員とその部下たちが移籍することを前提として、あらかじめ30坪の広さを有する事務所を被害会社の幹部社員に提供したこと
④慰安旅行先に出向いて、セールスマンらに対し自社の会社の説明をすることを、旅行の前から、被害会社の幹部社員と打合せていたこと
⑤慰安旅行が被害会社の代表者に発覚したとの報告を幹部社員から受けると、急遽、当初と異なるホテルを手配したり、バスをチャーターし、しかもこのホテル宿泊費及びバスチャーター料をすべて負担するなど、移籍の勧誘のための場所作りに積極的に関与したこと
⑥慰安旅行の2日目には、実際にホテルの会議室で、被害会社のセールスマンらに自社(新雇用主)の会社の説明会を開催したこと
⑦振興会の準会員として、セールスマンリクルートを自粛するという振興会の統一見解を遵守しなければならない立場にあったにもかかわらず、それに違反する、引抜行為を実行したこと
この裁判例では、上記①から⑦の事情を、総合判断すると、競合他社の行為は、単なる転職の勧誘を越えて社会的相当性を逸脱した引抜行為であるといわざるを得ない旨判断されています。
3.最後に
今回は、従業員の引き抜きが違法と評価された裁判例について、企業側の弁護士が解説しました。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
従業員の引き抜きについて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
従業員の引き抜きが違法と評価される場合とは?
企業運営を行っていると、自社の元役員が自社の従業員を引き抜いてきたり、競合他社が自社の従業員を引き抜いてきたりすることもあります。
もし、自社の従業員が引き抜かれた場合、引き抜き相手に対する損害賠償請求は認められるのでしょうか。引き抜き行為が違法と評価される場合には、引き抜き相手に対する損害賠償請求が認められることになります。
そこで、今回は、従業員の引き抜きが違法と評価される場合について、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説いたします。自社の従業員が引き抜かれた経営者の方や、企業担当者の方は、是非参考にしてみてください。
1.引き抜きが問題となる3つのケース
自社の従業員が引き抜かれた場合、おおよそ、下記の3つのケースが考えられます。
(1)在職中の取締役や従業員が、自社の従業員を引き抜くケース
意外と多いのが、在職中の取締役や従業員が、自社の従業員を引き抜くケースです。
在職時に引き抜き行為をした取締役や従業員は、通常、その後に自社を辞めて、競合他社に転職するか、競合の会社を設立します。
この場合、引き抜き行為をした取締役や従業員への損害賠償請求とともに、競合他社への損害賠償請求も検討することになります。
(2)自社の元取締役や元従業員が、自社の従業員を引き抜くケース
既に、自社を辞めた取締役や従業員が、競合他社に転職したり、競合の会社を設立しており、自社の従業員を引き抜いてくるケースです。
実務上、このパターンが特に多い印象です。このケースの場合、引き抜き行為をしてきた元取締役や元従業員は、自社を辞める際に自社と揉めていることも多いです。
この場合には、引き抜き行為をした元取締役や元従業員への損害賠償請求とともに、競合他社への損害賠償請求も検討することになります。
(3)競合他社が、自社の従業員を引き抜くケース
最後は、競合他社が、自社の元従業員などを介在させずに、単独で引き抜いてくるケースです。
このケースの場合には、上の2つのケースほど、強引に引き抜いてくることは少ない印象です。
2.引き抜きが違法と評価される場合について
自社の従業員が引き抜かれた際に、会社が損害賠償請求を行うことを検討する相手方は、下記の3者になります。
①在職中に引き抜き行為をしてきた取締役や従業員
②退職後に引き抜き行為をしてきた自社の元取締役や元従業員
③引き抜き行為をしてきた(又は①や②に加担した)競合他社
引き抜きが違法と評価されるか否かの基準については、下記にて詳しく解説しますが、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱したと認められる場合には、違法との評価を受けることになります。
(1)基本的な考え方
労働者には、職業選択の自由があり、労働者には転職の自由が認められています。それゆえ、労働者が新たな就職先と雇用契約を締結することも自由です。
そのため、このような自由を有する労働者を勧誘したり、情報提供などにより援助することも、原則として自由であるとされています。
裁判例においても、会社に在職中の社員が他の従業員に対して、自身の転職先の競合他社への引き抜き行為をした事例で、これが単なる転職の勧誘にどどまる場合には、違法ではないと判断しています。
■裁判所の判断(原則論)
従業員は、使用者に対し、雇用契約に付随する信義則上の義務として就業規則を遵守するなど雇用契約上の債務を誠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務を負い、従業員がこの義務に違反した結果、使用者に損害を与えた場合は、これを賠償すべき責任を負うというべきである。
そして、労働市場における転職の自由の点からすると、従業員が他の従業員に対して同業他社への転職のため引き抜き行為を行ったとしても、これが単なる転職の勧誘にどどまる場合には、違法であるということはできない。
仮にそのような転職の勧誘が、引き抜きの対象となっている従業員が在籍する企業の幹部職員によって行われたものであっても、企業の正当な利益を侵害しないようしかるべき配慮がされている限り、これをもって雇用契約の誠実義務に違反するものということはできない。
(2)引き抜きが違法と評価される場合
ア 在職中に取締役や従業員が引き抜き行為をした場合
しかし、当然ながら、引き抜き行為が、どのような場合にも適法となるわけではありません。
裁判例上も、会社に在職中の幹部社員が他の従業員に対して、自身の転職先の競合他社への引き抜き行為をした事例で、引き抜き行為が単なる勧誘の範囲を超え、著しく背信的な方法で行われ、社会的相当性を逸脱した場合には、引き抜き行為が違法になると判断されています。
■裁判所の判断(違法と評価される場合について)
企業の正当な利益を考慮することなく、企業に移籍計画を秘して、大量に従業員を引き抜くなど、引き抜き行為が単なる勧誘の範囲を超え、著しく背信的な方法で行われ、社会的相当性を逸脱した場合には、このような引き抜き行為を行った従業員は、雇用契約上の義務に違反したものとして、債務不履行責任ないし不法行為責任を免れないというべきである。
そして、当該引き抜き行為が社会的相当性を逸脱しているかどうかの判断においては、引き抜かれた従業員の当該会社における地位や引き抜かれた人数、従業員の引き抜きが会社に及ぼした影響、引き抜きの際の勧誘の方法・態様等の諸般の事情を考慮すべきである。
■弁護士の補足解説
自社に所属する者が他の従業員を引き抜いたことが問題になった際には、裁判所は、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱した場合には、違法になると判断します。
そして、多くの裁判例の傾向を見てみると、その判断にあたっては、概ね、下記の4つの事情を中心に、諸般の事情を総合考慮して判断されています。
①引き抜き行為をした従業員の当該会社における地位
引き抜き行為をした従業員が、会社の幹部社員であったり、会社の中で中心的役割を果たすものであった場合には、違法であるとの方向に傾くことになります。
②引き抜かれた従業員の当該会社における地位や引き抜かれた人数
引き抜かれた人数が多く、しかもその会社で重要な地位を担っている者を引き抜いた場合には、違法であるとの方向に傾くことになります。
③従業員の引き抜きが会社に及ぼした影響
引き抜きにより、会社の業務運営に重大な支障を及ぼす場合には、違法であるとの方向に傾くことになります。
④引き抜きの際の勧誘の方法・態様
下記の場合には、違法であるとの方向に傾くことになります。
・競合他社への就職が内定していながら、これを会社に隠して引き抜き行為をした
・引き抜き行為をした者や引き抜かれた者が、突然会社を退職した上、退職にあたって何らの引継ぎ事務を行っていない
・他の従業員に会社にとってマイナスな虚偽の情報を伝え、金銭供与をするなどして転職を勧誘した
・慰安旅行を装って、事情を知らない従業員をまとめて連れ出し、ホテル内の一室で移籍の説得を行った
イ 自社の元取締役や元従業員が引き抜き行為をしてきた場合
自社の元取締役や元従業員が引き抜き行為をしてきた場合、その引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法・態様で行われた場合には、違法な行為と評価されます。
そして、その判断にあたっては、①引き抜かれた従業員の当該会社における地位や引き抜かれた人数、②従業員の引き抜きが会社に及ぼした影響、③引き抜きの際の勧誘の方法・態様などの事情を中心に、諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。
判断基準については、概ね同じであるものの、在職中の取締役や従業員による、引き抜き行為のケースよりは、違法と評価されることが難しくなります。
■裁判所の判断
従業員が勤務先の会社を退職した後に当該会社の従業員に対して引き抜き行為を行うことは原則として違法性を有しないが、その引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法・態様で行われた場合には、違法な行為と評価されるのであって、引き抜き行為を行った元従業員は、当該会社に対して不法行為責任を負うと解すべきである。
ウ 競合他社が引き抜き行為をしてきた場合
競合他社が引き抜き行為をしてきた場合、単なる転職の勧誘の範囲を超えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いたといえる場合には、引き抜き行為が違法と評価されることになります。
裁判例で問題になるケースは、競合他社が単独で引き抜き行為をしてきた場合よりも、(1)や(2)の従業員の引き抜き行為に加担している場合が多いです。
■裁判所の判断
企業が同業他社の従業員に対して自社へ転職するよう勧誘するに当たって、単なる転職の勧誘の範囲を超えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合、当該企業は、同業他社の雇用契約上の債権を侵害したものとして、不法行為責任に基づき、引き抜き行為によって同業他社に生じた損害を賠償する義務があるというべきである。
3.最後に
今回は、従業員の引き抜きが違法と評価されるか否かの判断枠組みについて、解説しました。
次回は、実際に従業員の引き抜きが違法と判断されて、引き抜き相手に対する損害賠償請求が認められた裁判例について、詳細に解説していきたいと思います。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
従業員の引き抜きについて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
従業員から労働訴訟を起こされた時に会社が取るべき対応
近年、企業が(元)従業員から労働訴訟を起こされることも少なくありません。
そこで、今回は、企業が(元)従業員から労働訴訟を起こされた時に、会社が取るべき対応などについて、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説いたします。労働訴訟を起こされた経営者の方や、企業担当者の方は、是非参考にしてみてください。
1.企業が従業員から訴えられる内容
企業が(元)従業員から訴えられる労働訴訟の内容としては、下記の4つが代表的なものになります。
(1)解雇無効
1つ目は、解雇が無効であると訴えられるケースです。
これは、労働者の地位に関わる訴えになります。
この場合、解雇無効の訴えとともに、従業員から会社に対する賃金請求も加えられていることがほとんどです。この賃金請求においては、解雇が無効になった場合に、解雇期間中の賃金をさかのぼって請求されることになります。解雇してから判決が出るまでに、数年単位でかかることもあり、このような場合には、数年分の賃金請求が飛んでくることになります。
この訴えを企業が起こされた場合には、①解雇に合理的な理由があること、②解雇という手段を選択することが相当であることを、企業側が積極的に主張していく必要があります。
(2)セクハラやパワハラなどを理由とする損害賠償請求
2つ目は、セクハラやパワハラを理由に、企業が損害賠償請求を受けるケースです。
このケースの場合には、セクハラやパワハラをしたとされる従業員や役員とともに、企業も損害賠償を受けるケースになります。
会社内でセクハラやパワハラがあった場合、企業側の責任が認められてしまうことも多いです。
この訴えを企業が起こされた場合には、企業側は、主に下記のような反論をしていくことになります。
①そもそもセクハラやパワハラが存在しない
②セクハラやパワハラについて企業が適切に防止措置を取っていた
③セクハラやパワハラが発覚した後に企業が適切に対応している
(3)労働災害を理由する損害賠償請求
3つ目は、労働災害を理由に、企業が損害賠償請求を受けるケースです。
これは、労働が原因で従業員が死亡したり、障害を負った場合などに、企業が損害賠償を受けるものです。
代表的なものとしては、過労死や、長時間労働が原因で従業員が大きな障害を負う事例などが挙げられます。
この訴えを企業が起こされた場合には、企業側は、主に下記のような反論をしていくことになります。
①その従業員が労働者ではない(労働者性)
②従業員の死亡又は障害は、業務が原因ではない(業務起因性)
この②の中で、過重労働や長時間労働といった従業員側の主張には理由がないことを主張してくことになります。
③従業員側の主張する損害額が誤っていること(損害論)
もし、従業員側が障害を負って、後遺障害等級が付いている事案であれば、後遺障害等級についての反論も検討することになります。
(4)未払残業代請求
4つ目は、未払残業代請求などの、未払賃金を請求されるケースです。
未払残業代や未払給料については、元々2年で時効消滅していましたが、2020年4月1日から時効期間が3年に伸びました。そして、将来的には、時効が5年になる見込みです。
この消滅時効期間が伸びたことにより、未払残業代などの請求金額も大きくなってきています。
この訴えを会社が起こされた場合には、企業側は、主に下記のような反論をしていくことになります。
①従業員側の主張する労働時間が誤っている
②管理監督者に該当するため、未払残業代を支払う必要がない
③時効により消滅している
2.訴訟を起こされた際に企業が取るべき対応
(1)訴状と証拠の内容確認
企業が(元)従業員から訴えられた場合、裁判所を通じて、従業員側の訴状や証拠などが送られてくることになります。
この訴状の「請求の原因」と記載されている部分の中には、一体なぜ、当該従業員が企業を訴えているのかの理由が示されています。そして、相手方の主張を裏付ける証拠も添付されています。
まず、企業においては、相手方の主張の適否について、検討する必要があります。
(2)反論を検討する
相手方の主張を理解した後は、自社で反論を検討することになります。
労働訴訟において、通常、従業員側の訴状の内容が全て正しいということはありません。
企業において、訴状の誤っている部分についての反論を検討するとともに、企業側の主張を裏付ける証拠を収集していくことになります。
(3)企業側の労働訴訟に長けている弁護士を探す
企業が労働訴訟を起こされた場合、ほとんどのケースで、企業は弁護士に依頼をします。これは、自社で訴訟に対応することが、現実的にみて難しいためです。
そのため、当該訴訟を依頼するために、企業側の労働訴訟に長けている弁護士を探す必要があります。
もし、自社に顧問弁護士がいるのであれば、まずはその弁護士に相談することになるでしょう。
意外と、自社の顧問弁護士が労働訴訟に対応していないケースもあるようで、当事務所にも顧問弁護士がいるのに労働訴訟についてご相談やご依頼を頂くケースもあります。
裁判所から訴状が届いたタイミングですぐに弁護士にご相談頂ければと思います。
(4)答弁書を作成する
訴えられた場合、企業は答弁書を作成する必要があります。
この書面において、従業員側の主張が誤っている点や、企業側が認識している事実関係及びそれを裏付ける証拠を示していくことになります。
裁判官は早い段階で訴訟の見通しを立てることも多いため、初回の答弁書から、自社の主張を全て出し切るつもりで対応することが重要です。
3.顧問弁護士のすすめ
企業が訴えられた場合にも、顧問弁護士がいれば、すぐに相談をして対策を打てるため、安心です。
企業が訴えられると、必要以上に不安になる経営者の方もいらっしゃいます。これまで、訴えられたという事実を重くとらえて、1人で悩み、精神的に追い込まれた経営者の方も見てきました。
しかし、経営者の方の役割は、前を向いて会社を前進させることであり、訴訟を起こされたからといって必要以上に不安になられる必要はありません。
このような企業の防衛については、顧問弁護士に任せて頂くのがよいと考えています。
これまでの顧問先様からのご依頼案件の中には、対応を間違えると顧問先様が危機的状況に陥るような案件も多数ありましたが、当事務所では顧問先様にご満足頂く形で無事に案件を解決してきました。安心して、当事務所に顧問弁護士をお任せ頂ければと思います。
4.最後に
今回は、従業員から労働訴訟を起こされた時に企業が取るべき対応について、解説いたしました。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
当然、労働訴訟についても多数の対応経験を有しており、労働訴訟に関する企業側の対応方法を熟知していると自負しております。
従業員から労働訴訟を起こされて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
労働審判における企業側のメリット
労働審判においては、企業側の準備期間が短く、企業側が不利な手続きであると語られることも少なくありません。
では、労働審判における企業側のメリットはないのでしょうか?
今回は、労働審判における企業側のメリットについて、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説いたします。労働審判を起こされた経営者の方や、企業担当者の方は、是非参考にしてみてください。
1.紛争を早く解決できる
労働審判における企業側の一番大きなメリットは、紛争を早く解決できることです。
というのも、労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっており、迅速な解決が目指される手続きです。平均審理期間は81日であり、67%もの事件が申立てから3か月以内に終了しています。
令和4年の司法統計では、労働関係訴訟の平均審理期間は17ヶ月とされており、訴訟と比べて、労働審判がいかに早く紛争を解決できる手続きか、お分かりいただけるかと思います(労働訴訟は本当に時間がかかります。)
紛争の解決が長引けば、企業担当者の人件費というコストがかかる上、中小企業の場合には、経営者の方にとっても精神的な負担となることもあります。また、退職済みの従業員の場合、未払い賃金について、退職後の期間には年14.6%もの遅延損害金が発生するため、期間が伸びれば伸びるほど支払い金額が大幅に増額になってしまう可能性があります。
そのため、紛争を早く解決することは、企業にとって大きなメリットであり、これが労働審判における一番大きなメリットとなります。
2.従業員側の譲歩を引き出しやすい
労働審判においては、調停という話し合いにて事件が終了するケースが、全体の約7割になります。例えば、令和2年の司法統計では調停成立が68.1%、令和元年の司法統計では調停成立が71.2%となっています。
このように、実は労働審判では、多くのケースでは、調停という話し合いによって事件が解決しています。
この調停においては、基本的には、会社側と従業員側が互いに譲歩をして、解決に至るため、従業員側の譲歩が引き出しやすいです。
労働訴訟に移行した場合には、従業員側も徹底抗戦をしてくることが多いですが、従業員側としても、可能な限り事件を早く解決したいとの意向を持っていることが多いため、労働審判では、一定程度の譲歩をしてくることも多いです。
そのため、労働者側の譲歩を引き出しやすいというのも、労働審判における企業側のメリットとなります。
3.付加金をカットできる
付加金とは、未払残業代などを支払わなかった会社に対する制裁で、会社が支払うべき金額と同一金額の支払いを命じられるものです。
要は、裁判所において悪質性が高いと判断した場合に、判決において、未払残業代などを2倍支払うことを命じられる制度となります。
付加金は判決でこれを命じる制度になりますので、労働審判の時には、付加金の支払いが命じられません。
対して、労働審判にて解決せずに、紛争が訴訟に移行した場合には、判決により付加金が命じられる可能性がありますので、この点は頭の片隅にでも置いておいて頂ければと思います。
4.最後に
今回は、労働審判における企業側のメリットについて、解説いたしました。
上記の通り、一番大きなメリットは、紛争を早く解決できることになりますが、企業の状況によっては、他の従業員への波及を防止するために、徹底抗戦を選択する場合もあるかと思います。
その辺りの、個別具体的な事情に基づく決断については、依頼する弁護士と十分にご相談頂ければと思います。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
当然、労働審判についても多数の対応経験を有しており、労働審判に関する企業側の対応方法を熟知していると自負しております。
従業員から労働審判を起こされて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
■関連記事
従業員から労働審判を起こされた時に会社が取るべき対応
近年、企業と従業員との間で紛争が発生することも増えています。
そして、突然、企業が従業員や元従業員から、労働審判を起こされることもあります。
そこで、今回は、労働審判の流れや労働審判を起こされた際の企業側の対応方法などについて、企業側で労働問題に注力している弁護士が解説いたします。
労働審判を起こされた経営者の方や、企業担当者の方は、是非参考にしてください。
1.労働審判とは
労働審判とは、解雇や給料の不払いなど、個々の事業主と労働者との間の労働関係のトラブルを、迅速かつ実効的に解決するための手続になります。
労働審判の一番大きな特徴は、期日が3回以内で終わる迅速な手続きであるということです。
他にも、労働審判には、下記のような特徴があります。
①訴訟手続きとは異なり非公開の手続であること
②裁判官1名と労働審判員2名で組織される労働審判委員会が手続きを行うこと
(注)労働審判員は、雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から、最高裁判所により任命されることとなっています。
③裁判所の出す労働審判に対して不服のある当事者が異議申立てをすれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続きに移行すること
2.労働審判の流れ
以下では、実際の労働審判の流れについて、解説していきます。
(1)従業員側からの申立て
通常、労働審判は、従業員や元従業員が、地方裁判所に対して、労働審判の申立書を提出することによって始まります。
以前は、元従業員が申し立てることが多く、現在も働いている従業員が申し立てることはほとんどなかった印象なのですが、最近では、現従業員から申し立てられることも少しずつ増えてきた印象です。
(2)裁判所から企業への期日指定や呼び出し
次に、裁判所から会社に対して、申立書の写しや期日呼出状等が郵送されます。
労働審判では、申立てがされた日から40日以内に第1回期日が指定されます。
この第1回期日の日時は、会社の都合も聞かずに一方的に指定されますが、基本的には日時の変更は認められていません。
通常、裁判所から申立書などが届いてから、第1回期日までは、1ヶ月ほどの期間になっています。
(3)企業側による答弁書や証拠の提出
上記書面の郵送の際には、「答弁書催告状」と言われる書面も同封されており、企業側が答弁書の提出を求められるとともに、答弁書の提出締切も記載されています。
おおよそ、企業側に上記書面が届いてから、約3週間で答弁書や証拠の提出が求められることになります。
労働審判では、この答弁書の内容を前提にやり取りが進んでいくので、この答弁書の内容が極めて重要になります。
なお、実際の答弁書の提出締切は、初回の労働審判期日の約7日前から約10日前に設定されている印象です。
(4)初回の労働審判期日
労働審判期日は、裁判官1名と労働審判員2名で組織される労働審判委員会が手続きを行っていく形になります。
当事者の出席者としては、申立をした従業員とその代理人弁護士、企業側の担当者とその代理人弁護士になります。
初回期日の審理時間は、2時間から3時間ほどになります。
初回期日では、争点を整理した上で、裁判官や労働審判員から各当事者に対して、質問をしていくことになります。
既に提出済みの答弁書の内容と、初回期日での質問に対する企業側の回答で、解決の大体の方向性が決まるため、初回期日に向けてしっかり準備をすることが重要です。
(5)第2回及び第3回目の労働審判期日
第2回目と第3回目の期日では、主として、解決に向けての話し合いが進められていくことになります。
この話し合いがまとまれば、調停が成立し、手続きが終了することになります。
話し合いの方法としては、裁判所主導型で調停案が出されてそれを双方が検討していく方法と、当事者双方の解決案への希望を裁判所が間に入って調整していく方法の2パターンがあります。
裁判官によっても調停のまとめ方は異なりますが、印象としては、まずは当事者双方の解決への希望を聞いて、当事者主導では溝が埋まらなさそうな時は、裁判所主導型に切り替えて、調停案が出されるイメージです。
(6)労働審判
話し合いがまとまらなければ、各当事者の主張等を踏まえて、労働審判委員会(裁判所)が労働審判を出すことになります。労働審判とは、訴訟の判決のようなものです。
労働審判に対して、当事者から、2週間以内に異議の申し立てがなければ、労働審判は確定します。労働審判が確定すれば、従業員から企業への強制執行の申立もできるようになってしまいます。
対して、労働審判に対して、当事者から2週間以内に異議の申し立てがされれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続きに移行することになります。
労働審判の内容に不服があるのであれば、必ず異議の申し立てをしなければなりません。
なお、当事者の話し合いの様子を見て、労働審判を出しても確定することはないと裁判所が判断した場合などには、労働審判が出されないこともあります。
3.労働審判への企業側の対応方法
(1)答弁書を全力で作成する
申立人である従業員側は、時間制限もないため、入念に準備をして「申立書」を作成してきます。
しかも、労働審判の対象となる紛争は、元々、従業員側に有利な案件も多いです。
他方、企業側には答弁書提出までの準備期間は、3週間ほどしか与えられていません。
このように、労働審判は企業側には一見不利な条件ではありますが、企業は答弁書を全力で作成し、自社に有利な証拠は最初に出しきる必要があります。
なぜなら、労働審判においては、この答弁書や証拠の内容によって、裁判所において、どちらの当事者が有利かに関しておおよその心証を取ることになりますし、その後の書面提出や証拠の提出もあまり予定されていないためです。
労働審判では、最初の答弁書と証拠が決定的に重要になりますので、企業側は、答弁書作成に際して入念に準備をすることが必要になります。
なお、繁忙期に答弁書の提出が求められ、労働審判を無視したり、答弁書を適当に作成しようと考える企業経営者の方もたまにいらっしゃいます。
しかし、労働審判を無視することは裁判所に喧嘩を売っているに等しいですし、適当な答弁書を提出して、一度決まった裁判所の心証を覆すのは極めて困難ですので、これらは絶対にやめた方がよいです。
弁護士に丸投げをしてでも、答弁書は全力で作成した方がよいです。
(2)初回期日への準備
労働審判の初回期日では、裁判官や労働審判員から各当事者に対して、多数の質問がされます。
そして、答弁書の内容に加えて、この初回期日での質問に対する各当事者の回答で、労働審判委員会(裁判所)が解決の大体の方向性を決めることになります。
そのため、初回期日での裁判所からの質問に対する回答の準備をしっかりしておく必要があります。
労働審判では、初回期日まででおおよその決着がつくケースが多いので、ここまでで全力を出し切る必要があります。
(3)良い弁護士に依頼する
上記の通り、労働審判では、答弁書の作成が極めて重要ですが、提出締切までの時間も短いです。また、期日では、裁判所からの口頭での質問に対する回答も求められることになります。
このような労働審判の特性に対応するためには、企業側での労働紛争に慣れている弁護士に依頼することが重要です。
労働審判の申立書が届いた企業の方は、すぐに、良い弁護士を見つけて依頼する必要があるといえるでしょう。
4.最後に
今回は、従業員から労働審判を起こされた際の企業側の取るべき対応について、解説いたしました。
上記の通り、労働審判を起こされた時、企業側は本当に時間がないため、すぐに弁護士に依頼することが重要であると考えています。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
当然、労働審判についても多数の対応経験を有しており、労働審判に関する企業側の対応方法を熟知していると自負しております。
従業員から労働審判を起こされて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
パワハラでの労災認定を認めた裁判例について、企業側の弁護士が解説
近年、社会全体で、パワハラ防止に対する意識が高まっています。
そして、従業員がうつ病などを発症した際に、従業員側から、パワハラでの労災認定を主張されることもあります。
これまでの記事では、会社側の立場から、パワハラでの労災認定を否定した裁判例について、解説してきました。
もっとも、パワハラでの労災認定を否定した裁判例だけでは、一体どれぐらいのレベル感であれば、労災認定が認められるのかが分からないと思います。
そこで、今回は、パワハラによる労災認定を認めた裁判例について、解説していきます。
従業員からパワハラでの労災認定を主張されている、会社経営者の方や担当者の方は、参考になさって下さい。
1.パワハラの労災認定基準
まず、パワハラに関する労災認定基準を簡単に解説します。
下記3つの基準を満たす場合、パワハラが労災と認定されます。
①労災認定の対象となる精神障害を発病していること
②精神障害の発症前おおむね6か月間に、パワハラによる「強い心理的負荷」を受けたこと
③業務以外の心理的負荷やその人固有の要因により、精神障害を発病したとは認められないこと
より詳しい内容については、「パワハラで労災認定される?企業の対応方法についても解説」にて解説していますので、気になる方は、是非参考になさってください。
そして、パワハラが労災認定されるか否かが争いになる場合、多くのケースでは、②の、パワハラによる「強い心理的負荷」を受けた、に該当するか否かが問題になってきます。
2.パワハラによる労災認定を認めた裁判例
(1)国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
トヨタ自動車事件(名古屋高等裁判所令和3年9月16日判決)では、パワハラによる労災認定が認められています。一審である名古屋地方裁判所では、労災認定が否定されていたので、国側(実質的には会社側)の逆転敗訴判決になっています。
この事案では、うつ病により労働者が自殺したところ、この自殺は業務が原因でなされたものなのか否か、特に業務により、労働者が「強い心理的負荷」を受けたといえるのか否かが争いとなりました。
裁判所は、下記のようなパワハラを認定して、従業員が「強い心理的負荷」を受けたと判断し、労災認定を認めました。
・裁判所が認定したパワハラの内容
本件労働者が、業務の進捗状況の報告などをするたびに、グループ長から、他の従業員の面前で、大きな声で叱責されたり、室長からも、同じフロアの多くの従業員に聞こえるほどの大きな声で叱り付けられたりするようになっていたことは、軽視できない。その程度は、同様の叱責を受けていた他の従業員Aをして、後日、本件会社の退職を決意させる有力な理由となるほどのものであり、本件労働者も、これを苦に感じており、また、グループ長及び室長に対し、相談しにくさを感じていた。
グループ長による本件労働者への叱責及び室長による本件労働者への上記叱責は、いずれも業務に関するものではあるが、その態様は、本件労働者と従業員A以外に上記のような頻度、態様で叱責される者は、グループ長の場合は、他にはおらず、室長の場合も、本件労働者と従業員Aの他には1人しかいなかったと感じるほどのものであったから、「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」であり、その「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」と評価するのが相当である。
本件労働者は、グループ長から少なくとも週1回程度、室長から2週間に1回程度の「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」で、その「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」を受けていたと評価するのが相当である。
上記認定のとおり、これらの上司の言動は、「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」で「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」といえ、個々的にみれば、その心理的負荷は少なくとも「中」には相当する。
そして、それら精神的攻撃は、グループ長のみならず、室長からも加えられている。そして、これらのパワハラ行為は、平成20年末ころから本件労働者がうつ病の発症に至る平成21年10月中旬頃までに至るまで反復、継続されている。
したがって、上記期間を通じて繰り返される出来事を一体のものとして評価し、継続する状況は心理的負荷が高まるものとして評価するならば、上司からの一連の言動についての心理的負荷は「強」に相当するというべきである。
・裁判所が認定した自殺に至る経緯
本件労働者は、困難であった新型プリウス関連業務を、当初の目標を修正し、期限を延長してやり遂げた後、初めての海外業務を実質一人で担当することになり、中国の事情も機械の内容も分からない状況の中、平成21年9月24日から直ちに取り組み始め、直後から期限の迫った業務をこなしていき、この新たな負荷を契機として平成21年10月中旬までにはうつ病を発症したが、その後も休職することなく業務に当たっていた。
また、2020年ビジョン関連業務が同年12月まで延長されることになったため、本件労働者は、厳しい残業規制(原則残業禁止)の中を、海外業務と併行して2020年ビジョン関連業務を行うことになり、多くの会議に出席し、将来ビジョン及びそれに向けての道筋を示す「CVJ技術の棚」、「CVJロードマップ」を作成した。
本件労働者は、海外業務の現地担当者から、当時の会社の財務状況からして達成困難な要求をされ、また、会社からは、費用削減のためこれまで派遣していた専門家を派遣することなく現地担当者主体で改造するように指示されるなど、困難な課題が課せられ、板挟みの状態となっていた。
しかし、本件労働者に対する直属の上司からの支援はなく、かえって、本件労働者は、グループ長及び室長からは、平成21年1月からおよそ1年にわたり、継続したパワハラを受けていた。
こういった悩みが、本件労働者の「仕事が進まない」、「どうしよう」といった焦燥感を強め、うつ病の症状を増悪させていった。
そして、本件労働者は、平成22年1月11日に、平成21年6月1日以降原則残業禁止となって以降初めて、1時間の残業をし、同月19日にも資料を作成するために1時間の残業をしてから帰宅し、翌朝いつものとおり家を出たが、有給休暇を取得して出社せず、山林で本件自殺をしたと認められる。
・裁判所による総合評価
本件労働者は、新型プリウス関連業務により「達成は容易でないものの、客観的にみて努力すれば達成も可能であるノルマが課され、この達成に向けた業務を行った」といった心理的負荷を、2020年ビジョン関連業務により「軽微な新規事業等の担当になった」あるいは「仕事内容の変化が容易に対応できるものであり、変化後の業務の負荷が大きくなかった」といった心理的負荷を受け、新型プリウス関連業務が一段落したところで、海外関連業務により「仕事内容の大きな変化を生じさせる出来事があった」といった心理的負荷を受けた。
そして、この間、長期間にわたり反復継続して、上司から「必要以上に厳しい叱責で他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」といった心理的負荷を受けていたところ、上記海外関連業務はそれ自体も相当に困難な業務であり、上司の対応にも変化がなかったことから、同海外関連業務の担当となったことを契機として本件発病に至ったものと認めるのが相当である。
上記各出来事の数及び各出来事の内容等を総合的に考慮すると、平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度のある精神的負荷を受けたと認められ、本件労働者の業務と本件発病(本件自殺)との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。
したがって、労災認定が認められるべきである。
(2)国・津労基署長事件
国・津労基署長事件(名古屋高等裁判所令和5年4月25日判決)でも、パワハラによる労災認定が認められています。こちらの事件も、一審である名古屋地方裁判所では、労災認定が否定されていたので、国側(実質的には会社側)の逆転敗訴判決になっています。
この事案では、労働者が平成22年4月1日に新卒で入社し、その後、適応障害を発病して平成22年10月30日に自殺したところ、この自殺は業務が原因でなされたものなのか否か、特に業務により、労働者が「強い心理的負荷」を受けたといえるのか否かが争いとなりました。
・裁判所が認定したパワハラの内容等
本件労働者は、支店営業部に配属され、その業務を担当することになって以降、課長から、注意を受ける際、大きな声で怒鳴られ、『こんなんで大卒か』、『学卒も大したことないな』、『聞いたことがない大学』などと言われていた。
本件労働者は、これについて、友人に、『静かに言ってもらえればわかるのに』、『何かあると大きな声で怒鳴られる』などと述べ、仕事内容等については、『書類の作り方が分からへん』、『見よう見まねで作っている』、『作ってもあまり評価してもらえない』、『すぐ捨てられる』などと述べていた。
このような課長の指導等に対する本件労働者の受け止め方は、入社間際の平成22年の春から夏頃には、気持ちが外側に向いており、仕事が分からない自分や上司に対する怒りであったのが、平成22年の盆過ぎ以降は、気持ちが内側に向いて、仕事が分からない自分が悪いのかという様に変わってきた。
そのほか、本件労働者が所属する部署では、飲み会が多く、本件労働者がこれを断った次の日に無視されるなどしたため、非常に断り難い状況になっており、本件労働者は、飲み会では、周囲からいじられたり、強くあたられたりするなどもしていた。
さらには、本件労働者は、平成22年6月の職場の慰安旅行の際に、上司等のために風俗店の予約を取らされるなどし、その後も、風俗関係の予約を取らされることがあり、本件労働者は、理不尽に感じ、『こんな低俗なことをしている会社だとは思わなかった』、『これも仕事なんかなあ』、『これが仕事やったら、やってけやん』などと述べていた。
加えて、平成22年10月9日の休日出勤の際には、本件労働者は、課長から、『計算ミスはお前のせいや』、『おまえなんか要らん』、『そんなんもできひんのに大卒なのか』などと、業務指導の範囲を超える叱責をされた。
・担当案件により本件労働者が受けた心理的負荷の程度
本件労働者の担当案件は、そもそも新入社員にとっては難易度の高い業務であり、かつ、本件労働者が主担当を引き継いだ際には、当初(平成22年4月)予定されていたスケジュールから3か月程度遅れていたため、引き継いだ当初からタイトなスケジュールで業務を進めざるを得ない状況になっていたものであり、本件労働者としては、業務の進め方自体も分からずにいるところ、参考となり得る適切な前例等の資料もなく、主任らから見本等を示されることもなく、それ以前から見よう見まねで書類等を作成しても駄目出しをされ、本件労働者が真に理解できるような十分な説明や指導が必ずしもされていなかったという状況であったことを踏まえると、中間報告前までの段階においても、本件労働者が受けていた心理的負荷の程度は少なくとも『中』に該当するものであったと認められる。そして、下記のとおり、中間報告の前後を含めた一連の出来事を通じて本件労働者がさらに著しい心理的負荷を受けたと認められることを考慮すると、当該担当案件の業務に関して本件労働者が受けた心理的負荷の程度が『強』に該当することは明らかというべきである。
■裁判所が認定した中間報告の件
本件労働者は、平成22年10月19日の客先への訪問及び翌日の打合せを経て、提案に必要な情報を収集するため,同年10月28日に現場再調査を行う予定としていた。
しかし、平成22年10月26日に行われた感謝の集い(本件会社が得意先を招いて感謝の意を伝えるとともに情報交換を行う場)で、当該案件の他の担当者が客先から中間報告を求められたことから、急きょ、2日後の同月28日に中間報告を行うことになった。
本件労働者は、A4用紙1枚程度の中間報告書の作成を指示されこれを引き受けたものの、結局、作成できなかったことや、同月28日の客先に向かう車中で、報告書なしで中間報告をすることにつき、本件労働者が主任に対し『どんな風にすればよいか?』との質問を繰り返していたこと等からすれば、本件労働者は、中間報告で何をどのように報告したらよいかを理解できていなかったものと認められるが、中間報告を行うことになった上記の経緯に照らせばやむを得ないことであり、理解できていないまま自身が主となって中間報告を行わざるを得ない状況になったことは、本件労働者には相当に大きな心理的負荷になったと考えられる(このことは、本件労働者が、持参すべきメジャーやカメラを忘れ、事務所まで取りに戻ったこと、安全に自動車の運転ができる状態ではなかったことにも現れている)。
そして、客先から、中間報告書がないことについて、『今日はこれだけ?』と言われ、これを受けた他の担当者が、謝罪して、当日の聴き取り結果と現場再調査結果に基づき早急に資料を作成すると述べたことは、当該案件の主担当であり、上記のような状況であった本件労働者にいわば追い打ちをかけたに等しいものであり、心理的負荷が大きく増大することになったと考えられるのであって、上記のような経過とその後の課長や主任とのやり取りを受けて、本件労働者は担当案件の業務の進め方や目標等について大きく混乱し、予定どおりに進められなかったことに自信を失い、更なる心理的負荷を受けたものと認められる。
・裁判所による総合評価
以上検討したところによれば、本件労働者が上司からしばしば業務指導の範囲を超え人格等も否定するような発言をされており、それによる心理的負荷の程度が少なくとも『中』に該当することをベースとして、本件労働者が平成22年4月1日付けで本件会社に新卒入社してから、平成22年10月30日の本件自殺までの間に担当した業務のうち、上記以外のその他の担当案件により本件労働者が受けた心理的負荷の程度は『中』に、上記担当案件により本件労働者が受けた心理的負荷の程度は『強』にそれぞれ該当すると評価し得ることを総合考慮すれば、本件労働者が本件会社における業務により受けていた心理的負荷の程度は、全体評価としても『強』に該当することは明らかというべきである。
したがって、労災認定が認められるべきである。
3.労災認定が否定されるか否かの重要な要素
前回の記事で解説した裁判例では、会社代表者が従業員に対して、かなり強い暴言を吐いていましたが、労災認定が否定されていました。
対して、今回解説した裁判例では、従業員への労災認定が認められています。
労災認定が否定されるか否かで大きく差をわけたのは、①従業員がパワハラを受けた期間の長さ、②パワハラが業務指導の目的でなされたといえるか否かです。
①従業員がパワハラを受けた期間の長さについては、これまで解説してきた労災認定を否定した事例では、従業員がそもそも10日程度しか働いていなかったり、パワハラが継続された期間が全体で約1ヶ月程度にすぎませんでした。
対して、今回解説した労災認定を認めた事例では、1つ目の事例が、およそ1年にわたり継続したパワハラを受けていた事例です。また、2つ目の事例も、新卒入社から自殺に至るまで、約7か月もパワハラを受けていた事例です。
パワハラでの労災認定の場合には、パワハラの反復継続性が重視される傾向がありますので、①従業員がパワハラを受けた期間の長さが大きな要素になってきます。
次に、②パワハラ行為が業務指導の目的でなされたといえるか否かも、労災認定が否定されるか否かの大きな要素になっています。
労災認定を否定した事例では、業務指導の範囲を逸脱したものと評価されることはあったものの、上司や会社代表者の叱責や段ボールを蹴り上げるなどの言動が、少なくとも、従業員側の何らかの行為(ミスなど)に対する指導目的の意図が見受けられていました。
対して、今回解説した事例では、不必要に従業員を過剰に叱責しており、指導目的の意図が認定できない事例でした。誤解を恐れずに踏み込んで言うと、今回解説した事例は、裁判所が認定した事実だけを見ると、マネージメント能力の無いパワハラ上司が、有能な従業員を自殺に追い込んだように見受けられる事案でした。言い換えれば、従業員側が特段悪いことをしていない(むしろ、どちらの従業員とも仕事を前向きに取り組み、かなり能力の高い従業員に見えます)のに、上司がパワハラをして、部下を潰している案件に見えます。このように、上司による叱責等が、指導目的の意図が認定できない場合には、労災認定が認められやすくなってしまいます。
言い換えれば、社内でパワハラが行われても短期間でそれが改善される仕組みがあったり、指導目的の叱責なのであれば、それが多少過剰であっても、労災認定が否定されるように見受けられます。
なお、パワハラによる労災認定を否定した裁判例については、「パワハラによる労災認定を否定した裁判例について、企業側の弁護士が解説」、「暴言でのパワハラの労災認定を否定した裁判例について、企業側の弁護士が解説」などで、詳細に解説していますので、気になる方は参考になさってください。
4.最後に
今回は、パワハラの労災認定が認められた裁判例について紹介しました。
パワハラ問題に関しては、その性質上、自社のみでの対応が難しいことも多いですので、そのような場合には、是非とも弁護士をご活用下さい。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
パワハラ案件についても、多数の対応経験を有しており、パワハラ問題に関する、企業側の対応策を熟知していると自負しております。
パワハラ問題でお悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »