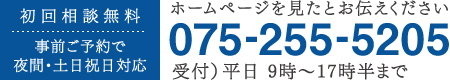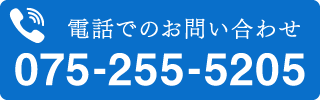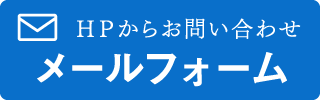コラム
ご依頼者の声5
・ご回答者様
女性
・ご年齢
30代
・ご依頼内容
交通事故
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 ▢納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
事故の状況から、その後のケガや生活状況まで丁寧に聞き取って下さり、親身に相談に乗って頂き、大変心強かったです。
示談成立までの流れ等、その都度説明もして頂き、安心感がありました。こまめにメール等のやり取りもして下さり、こちらの質問への応対、必要書類についてもすぐ送付してもらえました。
全ての対応に好感を持ちました。ありがとうございました。
コメント
ご依頼者に対応や解決結果について大変ご満足頂けたことを、弁護士としてもとても嬉しく感じました。
ご相談者のなかには、弁護士と話をするのが初めてという方も多いので、話しやすい雰囲気をつくったうえで、丁寧に話をお聞きすることを心がけています。
また、依頼後の流れについても、できる限りご説明をして、不安な気持ちを解消できるように配慮しています。
ご依頼者とのやりとりについても、できる限りスピーディーに対応するようにしており、本件のご依頼者にも、その点について大変喜んで頂けました。
ご依頼者の声4
・ご回答者様
女性
・ご年齢
30代
・ご依頼内容
交通事故
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 ▢納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
とても親身に対応して下さりありがとうございました。
また何かあればよろしくお願い致します。
コメント
ご依頼者が交通事故の追突事故を起こしてしまい、ご依頼者自身が怪我をされているとの事件でした。受任前、相手方の任意保険会社は、追突事故なので、ご依頼者が全て悪く、治療費や慰謝料等は一切支払わないとのスタンスでした。
そこで、弁護士受任後、ご依頼者の病院や整骨院への通院が終わるのを待って、治療費や慰謝料等を自賠責保険会社へ請求し、最終的には治療費分に相当する費用は全額返ってきて、慰謝料に相当する金額もご依頼者の期待以上に取得できました。
なお、事故によって、相手方の車両が傷ついたので、その部分は訴訟となりましたが、訴訟においては、証拠に基づき当方の主張を的確に行うことで、結果的に相手方の請求額から一定程度減額した金額での和解が成立しました。
ご依頼者からは、結果及びご依頼者のお気持ちに寄り添って粘り強く丁寧に事件を進めたことについて、大変喜んで頂けました。
ご依頼者の声3
・ご回答者様
男性
・ご年齢
30代
・ご依頼内容
交通事故
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 ▢納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
【コメント】
ご依頼者からは、弁護士が粘り強く交渉して、損害賠償額の増額という結果を得られたことについて、大変満足頂けた事案です。
本件のように、弁護士が交渉することにより、交通事故の損害賠償額の増額という結果を得られる場合もありますので、損害賠償額の増額を希望される方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
セクハラ、パワハラの慰謝料の相場について
セクハラやパワハラが発生すると、被害者は加害者へどの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。慰謝料トラブルをスムーズに解決するため、慰謝料の相場を把握しておきましょう。
この記事では、セクハラやパワハラの慰謝料の相場について、京都の弁護士が解説します。
セクハラ、パワハラの被害に遭ってお困りの方は参考にしてみてください。
1 セクハラとは
セクハラとは、「セクシュアルハラスメント」の略で、簡単にいうと性的な嫌がらせです。
職場で他の人を不快にさせるような性的な言動をとると、セクハラに該当する可能性があります。
より正確にいうと「職場において行われ、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
たとえば、労働者が性的な要求を拒んだために降格や解雇などの不利益を受ける場合や、職場仲間の性的な言動によって職場環境が悪化した場合などにセクハラが成立し得ます。
セクハラの加害者になるのは上司だけではありません。
同僚や後輩などからもセクハラ被害を受ける可能性があります。
2 セクハラで慰謝料請求できる相手
セクハラの被害に遭った場合には、加害者へ慰謝料を請求できるケースが多数です。
まずは、直接の加害者へ慰謝料請求できます。
また、加害者を雇用している会社へも慰謝料請求できるケースがあります。
理由は2つあり、1つには会社には加害者の使用者責任が発生するためです。
2つ目は、会社には労働者が働きやすい環境を用意すべき義務があり、それにもかかわらず漫然とセクハラを放置すると、職場環境配慮義務違反として責任が発生するためです。
3 セクハラの慰謝料相場
セクハラの慰謝料相場は、50~200万円程度です。
ただし、事案によって大きく異なり、ときには300万円を超える案件もあります。
以下で、どういった状況になるとセクハラの慰謝料が高額になるのか、みてみましょう。
セクハラの慰謝料が高額になりやすいケース
- 被害者がセクハラによって退職に追い込まれた
- 被害者がセクハラによってうつ病などの病気にかかった
- セクハラの態様が悪質(強姦した、強制わいせつ行為をしたなど)
- セクハラが長期間、何度も繰り返された
特に被害者に対して強姦や強制わいせつ行為が行われて刑事事件になる場合などには、数百万円という高額な慰謝料が発生するケースもあります。
4 パワハラとは
パワハラは、パワーハラスメントを省略した言葉です。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものです。パワハラといえるには、①から③までのすべての要件を満たさねばなりません。
たとえば、相手に暴力を振るった場合、精神的に攻撃した場合、仲間はずれにした場合、過量な業務を強要した場合や反対に仕事を与えない場合、プライベートに無用に踏み込む場合などにパワハラが成立する可能性があります。
上司による部下へのパワハラが典型ですが、職場の優越的な関係を背景としてさえいれば、部下から上司へのパワハラや同僚同士のパワハラも成立します。
5 パワハラで慰謝料請求できる相手
パワハラで慰謝料請求できる相手には、直接の加害者だけではなく会社も含まれるケースが多くあります。
従業員の行為について使用者責任が発生する可能性がありますし、会社には職場環境配慮義務も課されるからです。
被害に遭っているのに会社がパワハラを漫然と放置した場合、会社への責任追及も検討しましょう。
6 パワハラの慰謝料相場
パワハラの慰謝料相場は、ケースによって大きく変わります。
また、どのようなパワハラが行われたかによっても慰謝料額は変わってきます。
一般的には30万円~200万円程度になる事案が多いでしょう。
たとえば、相手から殴られた場合や暴言をはかれた場合、名誉毀損された場合などです。
一方、被害者が自殺した場合には、2000万円以上もの高額な慰謝料が認められるケースも少なくありません。
パワハラの慰謝料が高額になりやすいケース
- 被害者が暴力を受けて後遺症が残った
- 執拗にパワハラが行わるなど、悪質であった
- パワハラが行われた期間が長い
- 被害者がうつ病などの精神疾患になって働けなくなった
- 被害者が自殺した
被害者がうつ病などの精神疾患にかかると、比較的慰謝料が高額になりやすい傾向があります。
7 セクハラやパワハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
セクハラやパワハラの慰謝料請求を行う場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 相手(加害者や会社)が真摯に対応する可能性が高い
- 有利に交渉して高額な慰謝料を獲得しやすい
- 交渉の手間や時間を節約できる
- 相手と直接交渉しなくて良いのでストレスが軽減される
- 状況に応じて適切なアドバイスをもらえるので、間違った行動により後で不利になるリスクが低下する
セクハラやパワハラのトラブルでお困りの場合、弁護士がアドバイスやサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。
社員が逮捕されたとき、会社がとるべき対応とは
社員(従業員)が逮捕されると、会社としてはどのように対応すれば良いのでしょうか。
逮捕されたからといって、社員をすぐに解雇できるわけではありません。
また、逮捕後はしばらく出勤できなくなるので、休職に際しての取扱い方法なども押さえておきましょう。
この記事では、社員が逮捕された場合に会社がとるべき対応について、京都の弁護士が解説します。
いざというときに慌てないために、ぜひ頭に入れておいてください。
1 社員が逮捕されたときに会社がとるべき対応
ある日突然社員が逮捕されてしまったら、会社としては以下のような対応をしましょう。
(1)事件の内容を確認する
まずは、社員がどのような事件を起こして逮捕されたのか、事実関係を把握すべきです。
業務中に起こした事件かどうかも問題になります。
もし、業務中に事件を起こした場合、会社にも使用者責任が成立し、被害者から損害賠償請求される可能性があります。
(2)身柄拘束場所を確認
次に、社員が身柄拘束されている場所を確認しましょう。
一般的には、逮捕された場合には、どこかの警察の留置施設で身柄拘束されていることが多いです。
警察から連絡が来たときには警察に確認すると良いですし、そうでない場合には親族が知っているケースが多いので、聞いてみると良いでしょう。
(3)本人の認識を確認
逮捕されたからといって、被疑事実が真実とは限りません。
実際には犯罪行為をしていないケースもあります。従業員が逮捕されたら、本人から事情を聞きましょう。
また、逮捕勾留期間には出勤できなくなります。その間に有給休暇を消化する意向があるのかなども確認しなければなりません。
本人が身柄拘束されている留置場へ行き、面会して話を聞きましょう。
ただし、被疑者が逮捕されると、その後「勾留」に切り替わるまでの間は、たとえ家族でも接見(面会)できません。
逮捕後、72時間以内に勾留請求がされるか決定され、勾留に切り替わった時点で、ようやく接見できるようになります。
弁護人以外の場合、面会できるとしても、捜査官の立会つきで時間は10~20分程度です。あまり込み入った話はできないので注意しましょう。
2 社員が逮捕されている間の出勤や給料について
社員が逮捕されると、その社員はしばらく出勤できなくなってしまいます。
具体的には、逮捕から起訴されるまでの最大23日間、出社できません。
その間の給料に関する取り扱いが問題になります。
基本的に休職している間は、給料は出ません。
ただし、本人が有給の消化を希望するのであれば、会社としては受け入れると良いでしょう。
3 社員が逮捕されてもすぐには解雇できない
「社員が逮捕されたら、解雇できるのだろう」と考える方が多いのですが、法律上はそう簡単なものではありません。
以下で、社員が逮捕されても解雇できない理由や正しい対処方法をお伝えします。
(1)すぐに懲戒解雇できるわけではない
多くの企業では、懲戒解雇の理由として「犯罪行為を行ったとき」を挙げています。
そこで従業員が犯罪事実によって起訴され、有罪認定を受けると懲戒解雇できる可能性があります。
しかし、逮捕されただけの段階であれば、まだ犯罪行為をしたと確定的に判断することができません。
逮捕されただけで懲戒解雇すると、後に不起訴となった場合などに不都合が生じる可能性があります。
従業員が逮捕されても、すぐに懲戒解雇としないように注意しましょう。
(2)有罪判決を受けた場合は解雇できることもある
それでは、従業員に有罪判決が確定したら、解雇できるのでしょうか?
実際には、有罪判決が出ても必ず解雇できるとは限りません。
解雇するには、社員の行為が「著しく企業秩序を乱した」ことが必要とされます。
たとえば、犯罪事実が業務内容とまったく関係のない私的なものであれば、犯罪行為によって著しく企業秩序を乱したとまではいえず、解雇できない可能性があります。
一方、社員が会社のお金を横領したなど会社に被害を与えた場合には、懲戒解雇が相当となるでしょう。
4 社員の逮捕後に企業がとるべき対応
社員が逮捕された後は、以下のような対応をしましょう。
(1)社員に対する対処
まずは、本人への対応方法を検討しましょう。
たとえば、有罪判決を受けても解雇しない場合や、有罪判決が出なくても起訴猶予になって犯罪事実が明るみにでた場合などには、何らかの懲戒処分をすべきケースが多々あります。
会社が損害を被った場合には、従業員へ損害賠償請求をするかについて検討をする必要があるでしょう。
(2)再発予防策をとる
今後、従業員による不祥事が再発しないよう、予防措置をとるべきです。
特に、業務と関連して犯罪が行われた場合などには予防措置をとる必要性が高いといえるでしょう。
今回の犯罪の原因を分析し、同様の事件が起こらないように仕組み化しましょう。
たとえば、横領事案があった場合には、複数人で会社のお金を管理するようにしたりして、チェック機能を強化することなどが考えられます。
京都の益川総合法律事務所では中小企業法務に力を入れています。従業員による不祥事にお悩みの際にはお気軽にご相談ください。
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額を約65万円増額することに成功した事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、人身、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、バイクで道路を走行中、前を走っていた自動車の急な左折に巻き込まれ、右尺骨茎状突起骨折等の怪我をしてしまいました。相手方保険会社との交渉をご自身でされてきたのですが、弁護士に任せたいということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方保険会社とは、主に通院慰謝料と過失割合について争いになりました。通院慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)によるべきと主張し、過失割合については、本件事故の具体的な状況を指摘し、主張を行いました。
あわせて、訴訟となった場合のリスクや法的見通し等の観点から粘り強く交渉を行いました。その結果、当初の提示金額より約65万円増額した賠償額を引き出すことに成功しました。
・コメント
弁護士の交渉により、損害賠償額を約65万円増額することに成功した事案です。
また、ご依頼者からは、治療費の打ち切りについて延長を求める交渉に成功した点についても、喜んで頂きました。
本件のように、弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
通院慰謝料については、こちらのページで詳しく解説しています。
離婚成立後に財産分与の請求をする方法について
離婚成立時に財産分与について合意しなかった場合、離婚成立後であっても財産分与を請求できます。ただし、離婚成立後の財産分与請求には期限もあるので、早めに対応しなければなりません。
この記事では、離婚成立後に財産分与請求をする方法について、京都の弁護士が解説します。
協議離婚などで離婚成立時に財産分与の取り決めをしなかった場合、ぜひ参考にしてみてください。
1 財産分与は離婚成立後でも請求できる
夫婦が離婚する際には、財産分与の取り決めができます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に取得した財産について、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
協議離婚の場合、離婚成立時に夫婦が話し合って財産分与の方法を決定するケースが多いでしょう。
もっとも、離婚を急いでいたなどの事情があり、離婚成立時に財産分与の話し合いができない場合もあります。
たとえば、DV事案で相手から逃れて早く離婚したかった場合、財産分与を請求できないこともあるでしょう。
離婚成立時に財産分与を受けられなくても、離婚成立後に財産分与請求できる可能性があります。
離婚成立後、一定期間であれば、基本的に財産分与請求が可能です。
2 離婚成立後に財産分与請求できないケース
ただし、以下のような場合には、離婚成立後に財産分与請求ができません。
(1)相手と「財産分与しない」和解をしている
1つは、相手方との間で「財産分与請求をしない」と約束してしまっているケースです。
財産分与をしない内容で合意してしまっているので、後に財産分与請求ができません。
ただし、相手から騙されたり脅迫されたりして「財産分与請求しない」と合意させられた場合などには、財産分与を請求できる可能性があります。
(2)財産分与の期限を過ぎてしまった
2つ目として、財産分与の期限を過ぎてしまった場合です。。
財産分与には「離婚成立後2年間」という期限があります。
この期間内に財産分与請求しないと、財産分与請求権が失われてしまいます。
離婚成立後に財産分与請求したいのであれば、早めに対応する必要があるといえるでしょう。
3 離婚成立後に財産分与請求する手順
離婚成立後に財産分与請求する手順をご説明します。
(1)相手に協議を持ちかける
離婚成立後であっても、財産分与請求をする場合には基本的に話し合いによって決定します。
まずは、相手方に対し、財産分与についての協議を持ちかけると良いでしょう。
話し合いで財産分与の方法を決定します。
合意ができたら決定内容を「財産分与に関する合意書」にまとめましょう。
財産分与に関する合意書は、できれば公正証書にしておくようおすすめします。
公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、相手が支払いを怠った場合には、スムーズに相手の財産を強制執行することが可能です。
公正証書がない場合には、相手が支払いをしないときにあらためて調停などの手続きをしなければなりません。
(2)財産分与調停を申し立てる
相手に財産分与の協議を持ちかけても応じてもらえない場合には、家庭裁判所で財産分与調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が間に入って話し合いを仲介してくれます。
自分たちだけでは解決できないケースでも話がまとまりやすくなるというメリットがあります。
また、財産分与の2年の期限が過ぎてしまいそうな場合でも、2年が経過する前に調停を申し立てれば調停の係属中に2年が過ぎても権利が守られます。
そこで、離婚成立後2年の除斥期間が過ぎてしまいそうな場合には、相手と話し合うステップを飛ばして財産分与調停を申し立てるケースも少なくありません。
(3)財産分与審判で財産分与の方法が決まる
財産分与調停で話し合っても両者が合意できない場合には、財産分与審判を利用します。
なお、財産分与調停が不成立になると自動的に審判に移行するので、別途審判を申し立てる必要はありません。
審判では、審判官(裁判官)が財産分与の具体的な方法を決定して、審判を下します。
調停と異なり、相手が納得しなくても、裁判所の判断を得ることができます。
4 基準時は離婚時または別居時とする
離婚成立後に財産分与請求するとき、いつの時点の財産を基準にするかという問題があります。
これについては、基本的に離婚時または別居時となります。
離婚前に別居していたら別居時、別居していなかったら離婚時です。
「話し合いをした時点」ではないので、基準時を間違わないように注意しましょう。
5 除斥期間が経過していても財産分与請求できる場合
離婚成立後の財産分与には、「離婚後2年間」の除斥期間が適用されます。
ただし、2年が経過していても、例外的に財産分与請求できる可能性があります。
それは、以下のような場合です。
- 相手から脅迫されて財産分与請求ができなかった
- 相手からだまされて請求すべき財産がないと思わされていた
- 相手が財産を隠していた
上記のような場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、財産分与相当額を請求できる可能性があります。
相手からだまされて2年以内に財産分与を請求できなかった場合などには、2年が経過していてもあきらめずに弁護士へ相談しましょう。
京都の益川総合法律事務所では離婚や財産分与のサポートに力を入れて取り組んでいます。お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
ご依頼者の声2
・ご回答者様
男性
・ご年齢
30代
・ご依頼内容
交通事故
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 ▢納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
親身に相談に乗っていただき、こちらの疑問点なども丁寧に答えていただき非常に助かりました。
相手方との交渉も粘り強くして下さり、解決結果についても非常に満足しています。本当にありがとうございました。
【コメント】
事件に関係して、様々な疑問をお持ちになっていたため、ひとつひとつ丁寧にご説明することを心がけました。
また、少しでもご依頼者にとって良い結果となるよう、相手方と何度も交渉を重ねた末に解決に至った事案であるため、結果にご満足頂け、とても嬉しく思います。
ご依頼者の声1
・ご回答者様
男性
・ご年齢
60代
・ご依頼内容
交通事故
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 ▢納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
小さな案件にもかかわらず、御尽力いただきありがとうございました。
当初、損保担当、損保紹介弁護士とも、小さな案件なのでしょうか、
ぞんざいな対応でした。(甘くはないと痛感しました。)
貴事務所の益々のご発展を、お祈り申し上げます。
【コメント】
当事務所にご相談に来られる前に、保険会社より紹介を受けた弁護士と面談をされたそうですが、その対応にご不満をお持ちでした。
ご依頼者の気持ちや心情に配慮して、丁寧に聴き取りを行ったうえで事件をすすめ、その結果解決に至ったため、ご依頼者には大変満足して頂けました。
内容証明郵便とは?書き方や出し方を弁護士が解説
「内容証明郵便はどのように作成すれば良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
内容証明郵便は、慰謝料請求を行うときや各種の通知書、警告書を送る場合などによく利用されています。
もっとも、日常的に使う郵便ではないので、どうやって作成すれば良いのか、どのような文面にすればよいのかなど迷ってしまう方が少なくありません。
この記事では、内容証明郵便とはどういった郵便で、どのように作成するのか(書き方)、発送方法(出し方)などについて京都の弁護士がお伝えします。
内容証明郵便で請求書や通知書を送りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰に差し出されたかについてを謄本によって証明してくれる郵便です。
内容証明郵便を利用すると、差出人の手元と郵便局に相手に送ったものと全く同じ内容の謄本(控え)が残ります。
したがって、相手から「そのような郵便は受け取っていない」などと主張されることを予防することができ、また、万が一裁判になった場合などにも内容証明郵便の控えを証拠として提出できます。
トラブルになっている場合やトラブルに発展しそうな場合、必ず「送ったこと」を明らかにしなければならない場合などには、内容証明郵便を利用しましょう。
2 内容証明郵便を利用すべき状況
以下のような状況であれば、内容証明郵便を利用するようおすすめします。
- 不倫などの慰謝料請求をする
- 交通事故などの損害賠償請求をする(相手が保険に入っていない場合など)
- 遺留分侵害額請求をする
- 時効援用通知を送る
- 相手に警告文を送る(ストーカー被害を受けている場合、迷惑行為をされている場合など)
3 内容証明郵便の特徴
内容証明郵便には、以下のような特徴があります。
- 書留で手渡し式になる
- 郵便局によって「内容証明」という判が押される
- 文書自体にも郵便局によって証明印が押される
- 形式や文字数が決まっている
4 内容証明郵便の書き方
次に内容証明郵便の書き方をご説明します。
(1)用紙や筆記具、パソコン使用について
用紙や筆記具、パソコン使用については特にルールはなく、どのようなものを使って作成しても問題ありません。ただし文書が2枚以上になる場合、綴じ目に契印をする必要があります。
(2)文字数について
郵便局から差し出す場合の内容証明郵便の場合、文字数には以下のようなルールがあります。
縦書きの場合
1行20字以内・1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内・1枚40行以内
1行26字以内・1枚20行以内
(3)使用できる文字について
内容証明郵便で使える文字は、ひらがな、カタカナ、漢字と数字です。英字は固有名詞の場合にのみ使えます。
かっこや句読点などの記号も使用可能です。
かっこは、「」、()などの1セットを1文字としてカウントします。
(4)訂正に関するルール
内容証明郵便を訂正する場合には、間違えた部分を二重線で消して吹き出しを入れて加筆し、欄外に「○字削除、○字加入」などと記載する必要があります。その上で訂正部分に差出人の印鑑を押します。
5 文書に記載する事項
内容証明郵便には以下のような事項を記載しましょう。
(1)差出人と受取人の氏名、名称、住所、所在地
まずは、差出人と受取人の氏名や名称、住所や所在地を書かなければなりません。
文書の冒頭か末尾の部分に書き入れましょう。
(2)捺印や契印、訂正印
差出人名の横への捺印は、法律上の義務ではありません。
ただし間違いなく本人が作成したと証明するため、捺印するのが一般的です。
契印や訂正をする場合には捺印したのと同じ印鑑を使いましょう。
(3)日付
内容証明郵便を作成した日付も入れましょう。
(4)タイトル
タイトルの記載は法律上の義務ではありませんが、タイトルがある方が文書の趣旨が伝わりやすくなります。
「請求書」や「通知書」などのタイトルをつけましょう。
6 内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、取り扱いのある郵便局から発送しなければなりません。
どこの郵便局でも扱っているわけではないので、注意しましょう。
郵便局へ内容証明郵便を持参する際には、以下のようなものを持っていきましょう。
- 内容証明郵便の文書(同じものを3通)
- 封筒
- 差出人の印鑑
- 郵便料金
(1)配達証明をつける
内容証明郵便を送る場合、配達証明をつけるようおすすめします。
配達証明とは、相手に送達された日を郵便局が証明してくれるサービスです。
配達証明をつけておけば、相手が「受け取っていない」とはいえなくなります。
単に内容証明郵便を出しただけでは「発送したこと」までしか証明できません。
相手に確実に配達されたという事実を証明するためには、配達証明が必要です。
(2)電子内容証明郵便の場合
電子内容証明郵便というサービスもあります。
これは、内容証明郵便のインターネット版です。
24時間いつでもどこからでも送れるというメリットがあります。
郵便局に行く暇がない方などは、電子内容証明郵便を利用すると良いでしょう。
内容証明郵便の文案などは、弁護士に確認しておくと安心です。
京都の益川総合法律事務所では内容証明郵便のレビューや作成、発送業務、相手方との交渉まで幅広く取り扱っています。
内容証明郵便について悩まれたときには、お気軽にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »