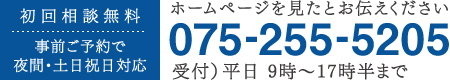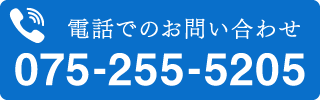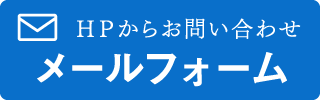コラム
懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか?
社員が問題行動により懲戒解雇となった場合、当然退職金を払わないでよい、又は迷惑をかけられたのだから退職金を払いたくないとお考えになる経営者の方がいらっしゃいます。
では、会社は懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのでしょうか。
この記事では、懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか、京都の弁護士が解説していきます。興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
1.退職金の法的性質
懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか、という問題について考えるにあたっては、退職金にどのような法的性質があるかが関わってきます。
これについては、退職金が就業規則や労働協約によって支給条件が明確に定められている場合、退職金は、賃金の後払い的性格と功労報償的性格が混在しているとされています。
2.退職金不支給条項
このような退職金の法的性質をふまえて、退職金の支給条件として、一定の事由がある場合に退職金の不支給や減額を定めることは認められますが、不支給や減額をするには、労働者のそれまでの功労を抹消また減殺するほどの信義に反する行為があった場合に限られるとされています。
今まで述べてきたとおり、懲戒解雇した社員には当然に退職金を支払わなくてよい、ということにはなりません。
退職金を支払わなくてよい事案であるか、労働者のそれまでの功労を抹消また減殺するほどの信義に反する行為があったか否かについては、慎重な検討が必要です。
京都の益川総合法律事務所では、退職金の不支給などの労働問題(使用者側)についてのご相談に力を入れて取り組んでいます。お気軽にご相談ください。
相続問題は益川総合法律事務所にご相談ください
相続問題が発生した場合には、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。
当事務所にご相談に来られる方の中にも、弁護士に相談する前にご自身の判断で対応してしまい、法的に妥当でない結果となってしまわれている場合もあります。
自己判断で対応してしまうと、思ってもみない結果になってしまうこともあり、後悔が残ってしまいかねません。
京都の益川総合法律事務所では、相続問題にも力を入れています。
当事務所では、初回の法律相談については無料で行っております。
弁護士がじっくりお話を聞かせて頂き、ご相談者の方のご希望や心情についても把握できるように努め、法的な見通し等についてもお伝えさせて頂けます。
また、初回法律相談にて、相談者の方と弁護士との相性が良いか確認頂くことも可能です。
相続問題は、事件終了までの期間がある程度長くなってしまうことが多いため、弁護士との相性が良くなければ、打ち合わせや連絡を取り合うことが苦痛になりかねないので、ご確認頂くことがご相談者の方にとっても安心かと思います。
また、当事務所からも、費用対効果の問題で、弁護士への依頼がおすすめできる案件かについて、率直にご意見をお伝えさせて頂いています。
弁護士に法律相談をしても、必ず弁護士にご依頼頂く必要はありませんので、安心してご相談頂ければと思います。
当事務所では、遺産相続の専門サイトも運営しておりますので、ぜひご覧になってみてください。
相続問題は益川総合法律事務所にご相談ください。
台風による被害について賠償責任はあるのか?
台風などの自然災害により被害が出た場合、賠償責任は発生するのでしょうか。
たとえば、台風により、自分が所有する建物の一部が飛んで、近隣に駐車中の車を傷付けてしまった場合、賠償責任を負わなければならないのでしょうか。
以下、京都の弁護士が解説していきますので、興味のある方は参考にしてみてください。
1.土地工作物責任(民法717条)
土地の工作物(建物など)の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生した場合、その工作物の占有者及び所有者が賠償責任を負うとされています(民法717条)。
ここでいう「瑕疵」とは、工作物が通常備えているべき安全性を欠いていることをいいます。
2.瑕疵と損害との間の因果関係
土地工作物責任が生じるためには、瑕疵と損害との間に因果関係が存在することが必要となります。
では、台風などの自然災害により損害が発生した場合には、どのように考えればよいのでしょうか。
これについては、予想を超えるような強風や大雨などの不可抗力のため、もし工作物に瑕疵がなかったとしても損害が生じたであろう場合には、因果関係がないとして、工作物責任が成立しないとされています。
工作物に瑕疵がある場合には、因果関係がないとされることはありませんが、自然災害の損害発生への寄与度を考慮して損害賠償額が減額されることになります。
京都の益川総合法律事務所では、土地工作物責任についてのご相談も取り扱っております。お気軽にご相談ください。
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額を約110万円増額することに成功した事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、人身、主婦の休業損害、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、自動車に同乗中、対向車がはみ出してきたために正面衝突をし、右手首の骨折等の怪我をしてしまいました。相手方保険会社との交渉については、弁護士に任せたいということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方保険会社とは、主に通院慰謝料と休業損害について争いになりました。通院慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)をベースとした損害賠償額が認められ、休業損害については家事従事者の休業損害及びその金額を主張したところ、請求金額の一部が認められました。
結果、当初の提示金額より約110万円増額した賠償額を引き出すことに成功しました。
・コメント
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額を約110万円増額することに成功した事案です。
大幅増額に成功したため、ご依頼者からは大変喜んで頂きました。
通院慰謝料については、相手方保険会社からの提示金額が弁護士基準(裁判基準)と比べて低くなっていることも多いため、弁護士による増額交渉が役立つことが多くあります。
また、家事従事者についても、事故による傷害のために家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされているため、弁護士が適切な主張をしたところ、休業損害の増額に成功しました。
本件のように、弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
ご依頼者の声6
・ご回答者様
女性
・ご年齢
50代
・ご依頼内容
遺産相続、その他
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
▢非常に納得 ■納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
コメント
相続した土地についてのトラブルがあり、当事務所にて対応し、解決に至ったという事案です。大変複雑な法律関係があったのですが、弁護士が粘り強く対応した結果、無事解決したために、ご依頼者からは大変喜んで頂けました。少しでもご依頼者の利益になるようにと尽力したため、弁護士としても、とても嬉しく感じました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続についても積極的に対応しております。
詳しくは、当事務所の遺産相続のサイトをご覧になってみてください。
契約書のリーガルチェックで確認すべきポイント
会社が事業を行うにあたって、契約書のリーガルチェックが重要であるということが言われます。では、具体的にはどのようなポイントを確認するべきなのでしょうか。
この記事では、契約書のリーガルチェックで確認すべきポイントについて京都の弁護士が解説します。
1 契約書のリーガルチェックとは
契約書のリーガルチェックとは、契約書の内容を法的な観点から調査し、作成・確認することをいいます。
詳しくは、「契約書のリーガルチェックについて弁護士が解説」というページで解説しているので、ご覧になってみてください。
2 契約書のリーガルチェックで確認すべきポイント
契約書のリーガルチェックで確認すべきポイントとしては、以下のようなものがあります。
(1)契約で定める債務の内容
契約で定める債務の内容が明確であるかについて確認します。
目的物がある場合には、目的物を詳細に特定する必要があります。
債務の内容について不明確であったり、疑義が生じやすい内容となっていたりすることが多いので、注意してください。
(2)支払金額、方法、期限
支払金額が重要であることは言うまでもありませんが、十分に確認をしてください。また、支払い条件がある場合には、その内容が明確であるかが重要です。
支払い方法については、振込とする場合には振込手数料がどちらの負担となるかについても確認してください。
また、分割なのか、一括なのか、いつまでに支払うのかが明確に記載されているかについて確認してください。
(3)解除、損害賠償
民法上の契約の解除とは別に、一定の事由が生じた際に解除できる旨を規定する条項を設けることが多くあります。
また、解除の際の損害賠償請求についても規定することが検討されます。
損害賠償の予定について定めると、債権者が損害賠償額を立証する手間を省くことができるため、多く用いられています。
(4)特約
定型の契約書を用いているが、特約で一方当事者に大幅に不利な内容の特約が入っていて、それを見落としてしまっているというようなケースもよくあります。
特約についても、十分に注意をして確認するようにしてください。
契約書のリーガルチェックで確認すべきポイントは、これらの他にも多数ありますので、心配な点がある場合には、弁護士への相談が役に立つでしょう。
京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでいます。
弁護士による契約書のリーガルチェックに興味のある方や顧問弁護士について気になっているという方はお気軽にご相談ください。
使用者責任とは何か、使用者責任の要件などについて
従業員が業務中に会社の車で交通事故を起こしてしまったケースなど、会社の従業員が業務中にトラブルを起こしてしまった場合、トラブルの相手方から会社に対して損害賠償請求をされてしまうことがあります。
使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)を負うとされているためです(民法715条)。
今回は、使用者責任とは何か、使用者責任の要件などについて、京都の弁護士が解説します。
相手方から使用者責任を主張された場合などに、ぜひ参考にしてみてください。
1 使用者責任とは
使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うというものです。
これは、報償責任の原理という、使用者が自分の業務のために被用者を用いることで事業活動上の利益をあげているのであるから、使用者は被用者による事業活動の危険を負担すべきである(「利益の帰属するところに責任も帰属する」)という考え方などに基づきます。
この点、被用者が公務員の場合には、同趣旨の国家賠償法1条が適用されますが、民法715条の場合と違って、判例では、公務員の職務行為について対外的に損害賠償責任を負うのは国や地方公共団体のみで、公務員個人は被害者には直接の賠償責任を負わないとされています。
2 使用者責任の要件
使用者責任の要件は、①被用者の行為が不法行為の要件を充たすこと、②使用関係があること、③被用者の不法行為が事業の執行について行われたこと、④使用者に免責事由がないこととされています。以下、具体的にみていきましょう。
(1)①被用者の行為が不法行為の要件を充たすこと
まず、被用者の行為が不法行為の要件を充たす必要があります。
使用者責任は、被用者の責任を使用者が代わって負担する責任である(代位責任)とされており、被用者の不法行為を前提とするからです。
(2)②使用関係があること
使用者が被用者を使用するという関係が必要となります。
これは、事実上の指揮監督の下に他人を仕事に従事させることを意味するもので、実質的な指揮監督関係があればよく、契約の存否、報酬の有無、期間の長短を問いません。
たとえば、下請人の被用者を元請人が指揮監督しているときは、契約の存否は問われず、元請人が使用者とされます。
実質的な指揮関係があるかについては、作業に当たっての個別の指示が重視されます。争いになった場合には、この点について十分な主張立証ができるかがポイントになるでしょう。
(3)③被用者の不法行為が事業の執行について行われたこと
被用者の不法行為は、使用者の事業の執行について行われたことが必要です。
ここで、「事業」というためには、一時的・継続的、営利・非営利、適法・不適法を問いません。
また、「事業の執行について」といえるかは、行為の外形から観察して、被用者の職務の範囲内とみられればよいとされています。
取引的不法行為(取引が行われる場面で被用者が職務権限を逸脱・濫用する場合)と事実的不法行為(被用者の交通事故・暴行などの場合)に分けて考察されます。
(4)④使用者に免責事由がないこと
使用者は、ⅰ被用者の選任および事業の監督につき相当の注意を払ったことを証明するか、または、ⅱ相当の注意をしても損害が発生していたであろうということを証明すれば免責されます(民法715条1項ただし書)。
しかし、これらの免責が認められた裁判例はほとんどなく、事実上認められていません。
3 被用者と使用者との関係
使用者責任が認められた場合、被害者は、使用者に対する損害賠償請求ができるほか、被用者に対して損害賠償請求をすることもできます。
この場合、使用者が負う損害賠償債務と被用者が負う損害賠償債務は、「不真正連帯債務」の関係になるとされています。なお、使用者責任を負う使用者が複数いる場合にも、各損害賠償義務は不真正連帯債務となります。
「不真正連帯債務」とは、通常の連帯債務よりも各債務者のつながりが薄い連帯債務ですが、通常の連帯債務と同様に、複数の債務者が全額を賠償すべき債務のことをいいます。そのため、もし、被害者が会社に全額を払うよう請求した場合には、会社は、被害者に対して、被用者に請求するよう求めることはできず、全額を支払う必要があります。
今回は、使用者責任について解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れており、相手方から使用者責任を主張される事案についても取り扱っています。特に、相手方から内容証明郵便にて使用者責任を主張されているような事案に関しては、早期の弁護士への相談が役立つことと思われます。
当事務所は、1983年の創業以来、様々な業種の会社の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。顧問弁護士がいれば、このような場合にも、スムーズな対応ができるでしょう。
相手方から使用者責任を主張されて困っている会社の方、顧問弁護士に興味があるという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
顧問弁護士については、「顧問弁護士をお考えの方へ」や「顧問弁護士に依頼できる内容や契約すべきタイミング」というページで詳しく解説しています。
契約書のリーガルチェックについて弁護士が解説
会社が事業を行うにあたって、契約を締結する場面は数多く出てきますが、契約書のリーガルチェックが重要であるということが言われます。
そこで、この記事では、契約書のリーガルチェックの意味、また、契約書のリーガルチェックを行うメリットについて、京都の弁護士が解説します。
契約書のリーガルチェックが気になっているという方は、参考にしてみてください。
1 契約書のリーガルチェックとは
契約書のリーガルチェックとは、契約書の内容を法的な観点から調査し、作成・確認することをいいます。
中小企業間の取引では、契約書のひな形を使っているけれども、そのひな形が取引の実態に合っていない等の問題点があることが多く、リーガルチェックを行うことで、問題点を克服することが重要となります。
2 契約書のリーガルチェックを行うメリット
契約書のリーガルチェックを行うメリットには、以下のようなものがあります。
(1)自社にとって不利益な条項がわかる
契約書のリーガルチェックの1番大きなメリットは、自社にとって不利益な条項がわかるということでしょう。
自社にとって不利益な条項がわかれば、その条項を削除してもらう、修正を行うという対策をとることができます。
また、仮に会社間の力関係上、条項の削除や修正ができない場合には、その不利益を許容したとしても、契約を締結するべきであるかという経営判断を行うことができます。
契約書のリーガルチェックができていなければ、上記のような対策等をとることはできず、会社にとっての大きなリスクとなってしまいます。
(2)取引の実態に合った契約書を作成できる
契約書のひな形を利用している場合、個々の取引の実態に合わない内容となってしまっているという契約書がよく見られます。
契約書の条項をひとつひとつ読み込んで、取引の実態に合致しているかについて検討することが必要です。
取引の実態に合わない契約書を利用した場合、契約当事者間において、契約内容についての認識に齟齬が生じてしまい、トラブルとなってしまうなどのデメリットがあります。
また、会社の希望に応じた内容に契約書の文言を修正することも有用ですので、ひな形をそのまま利用している会社の方は、注意してみてください。
(3)トラブルが発生した際に相談しやすい
弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼する場合、自社の顧問弁護士に依頼することが多くなります。
まだ顧問弁護士がいないという会社の方にとっては、リーガルチェックが顧問弁護士を見つけるきっかけにもなります。
また、顧問弁護士がいる会社の方であっても、セカンド顧問弁護士(現在の顧問弁護士と別の2番目の顧問弁護士)を見つけるきっかけに活用するのもよいでしょう。
弁護士にリーガルチェックを依頼した場合、弁護士が既に当該取引内容を把握しているため、トラブルの内容を的確に理解してもらいやすいといえます。
京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでおり、様々な業種の契約書のリーガルチェックについても取り扱っています。
弁護士による契約書のリーガルチェックを受けてみたいという会社の方は、お気軽にご相談ください。
顧問弁護士については、「顧問弁護士をお考えの方へ」というページで詳しく解説しています。
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額において、兼業主婦の休業損害の請求が認められた事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、人身、休業損害、兼業主婦、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、バイクで停車中、前方のトラックが後退してきたために衝突し、腰椎捻挫等の怪我をしてしまいました。相手方保険会社との交渉をご自身でされてきたのですが、弁護士に任せたいということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方保険会社とは、主に兼業主婦の休業損害と通院慰謝料について争いになりましたが、兼業主婦の休業損害については、こちらの請求が満額認められました。また、通院慰謝料についても、弁護士基準(裁判基準)をベースとした損害賠償額が認められました。
結果、当初の提示金額より約60万円増額した賠償額を引き出すことに成功しました。
・コメント
弁護士の交渉により、兼業主婦の休業損害について、こちらの請求の満額が認められた事案です。
休業損害とは、事故による傷害のために、休業や不十分な就労を余儀なくされ、その治癒や症状固定までの間に得られるはずであった利益を得られなかったことによる損害のことをいいます。
家事従事者についても、事故による傷害のために家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされていますが、本件のように、兼業主婦の方の場合には、相手方保険会社との間で金額等争いになるケースが多くあります。
ご依頼者からは、当初から、お怪我が家事についても支障となっているというお話を聞いていたため、本件ではその点についての請求も認められることとなり、非常に喜んで頂きました。
本件のように、弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
取引先が破産した場合の対応について弁護士が解説
取引先が破産したら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
すでに破産手続きに入ってしまった場合には、強制執行などの手続きを行うことができなくなってしまいます。
その場合、まずは債権届を提出して配当を受けることが考えられますが、それ以外にもいくつかの債権の回収方法があります。
この記事では、取引先が破産した場合にどのような対応をとることができるのかについて、京都の弁護士が解説します。
連鎖倒産などの最悪の事態を回避するため、ぜひ参考にしてみてください。
1 倒産、破産の予兆
会社がいきなり倒産や破産するケースは少数です。一般的には何かしらの予兆があるものです。
倒産や破産の兆候が見えたとき、早期に回収のための方策をとっておけば、破産後よりも効果的な対応が可能となります。
以下では、倒産や破産する企業によくある特徴をみてみましょう。
(1)従業員が減る
会社の経営状況が悪化してくると、給料の支払い遅延などが生じて従業員が不満や不安を抱くケースがよくあります。
そうなると、従業員が退職するなどして動きが生じます。
会社側が人員整理のために従業員を整理解雇するケースもあります。
取引先の従業員の数が急に減ったり異動が激しくなったりすると、要注意の状態といえるでしょう。
(2)資産の売却
会社で保有している資産を売却し現金化している場合にも、会社資金が不足していることを推測させるので、注意する必要があるでしょう。
(3)支払い時期や方法の変更
これまでは順調に支払いができていたのに遅延が生じたり支払期日・方法の変更を申し入れられたりした場合にも、危険信号が点滅している可能性があります。
また、倒産しそうな企業は自社の支払いが遅れる一方で、取引先に対しては「支払期日を前倒ししてほしい」などと要求するケースもよくあります。
2 取引先が破産した場合の対処方法
実際に取引先が破産したら、以下のように対処しましょう。
(1)債権届を提出して破産手続きに参加する
会社が破産すると、各債権者には債権調査票が送られてきます。
後で配当金を受け取るため、債権の資料とともに債権届を破産管財人へ提出しましょう。
ただし、破産手続きによる配当金の金額は高額にならないのが一般的です。
多くの場合、数%程度にしかなりません。
その他の部分については、以下のような工夫によって回収する必要があります。
(2)相殺
取引先に対して反対債務がある場合、破産手続きに入った後であったとしても、相殺によって債権回収ができます。
(3)所有権留保にもとづく商品の引きあげ
相手方に対して商品を納入している場合でも、所有権留保がついていれば商品の合法な引きあげが可能となります。
ただし、所有権留保もなく、かつ、相手方の同意もなしの状況で商品を引き上げてしまうとトラブルになる可能性が高いため、法的な根拠なく商品を引きあげてはなりません。
(4)担保権の実行
売掛債権を担保するために、土地建物に抵当権を設定していた場合には、抵当権を実行して土地や建物を競売にかけられます。
(5)連帯保証人への請求
売掛債権に保証人や連帯保証人をつけている場合、保証人などへ請求して債権回収できる可能性があります。会社が破産しても保証人が破産していない限り、保証人への請求は可能です。
(6)貸倒れの処理
売掛債権が回収不能となった場合には、損金処理をして税額を減らせる可能性があります。
相手方が破産手続きに入った場合や債権放棄した場合などに損金処理をすることが考えられます。
税務署に証拠として提出するため、相手に債権放棄通知書を送る場合には内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
3 取引先に破産されると強制執行ができなくなる
売掛債権について、公正証書で定めている場合には、相手方が支払わないときに公正証書の強制執行認諾条項にもとづいて強制執行ができます。
調停調書や判決書などの他の債務名義がある場合も同様です。
ただし、取引先が破産手続きに入ってしまうと、個別の強制執行はできなくなってしまいます。
強制執行によって債権回収したい場合には、破産の予兆を感じたとき、破産手続きに入られる前に、早めに手続きを実行しなければなりません。
4 倒産・破産されたときの損失を予防する方法
取引先が破産した場合の損失を防ぐには、以下のような方法が有効です。
(1)担保権の設定
まずは、抵当権や保証人などの担保権を設定しましょう。
こういった権利を設定しておくと、取引先が破産手続きに入った後であっても、権利を行使して債権回収ができます。
ただし、保証人などの人的担保の場合には、本人と一緒に破産してしまう可能性があります。
可能であれば、土地建物に抵当権をつけるなど物的担保を利用するようおすすめします。
(2)公正証書の作成
強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成しておけば、相手方が破産する前であれば、速やかに強制執行ができます。
公正証書がない場合と比べ、スピーディーな債権回収が可能となります。
万が一に備えて公正証書を作成しておくと良いでしょう。
京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでいます。
債権回収でお困りごとがある際には、お気軽にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »