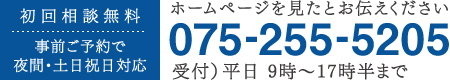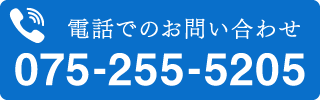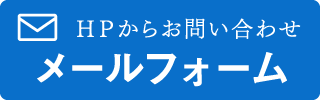コラム
企業が労働トラブルを弁護士に相談するメリット
- 未払い残業代請求
- 不当解雇
- パワハラ、セクハラのトラブル
- 労働災害
- 労働審判や訴訟
企業が労働トラブルに巻き込まれた際には、お早めに弁護士へご相談ください。
益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。お困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
1.会社が弁護士へ相談するメリット
企業の労働トラブル対策は、弁護士に依頼するようおすすめします。
1-1.損失を最小限に抑える
労働トラブルが大きくなると、企業には多大な損失が発生する可能性があります。
- 未払い残業代や退職金の支給
- 遅延損害金や付加金の加算
- 慰謝料の支払い
- 社会における信用の低下
- 他の従業員のモチベーション低下、離職
弁護士に対応を依頼すれば、支払う金額を最小限に抑えられますし、スムーズに解決することで信用低下などのリスクも大きく軽減できます。
企業側の正当性を理解してもらえれば、従業員のモチベーション低下や離職も抑えられるでしょう。
1-2.コンプライアンスを遵守できる
企業が労働問題に対応する際には、コンプライアンスを意識しなければなりません。
たとえば、労働者側の主張が正しいにもかかわらず不当な取り扱いをすると、企業に対する信用が低下するだけではなく企業側の責任が重くなってしまう可能性もあります。
弁護士に相談しながら対応を進めれば、コンプライアンスを遵守できるので安心です。
法改正があった場合にも、改正内容に対応するため御社の就業規則や社内規定を適切に改定するお手伝いができます。
1-3.トラブルを未然に防ぐ
労働トラブルに発展する前に弁護士に相談すれば、未然に防止できるケースが多々あります。
たとえば日頃からきちんと賃金計算をして残業代を支給しておけば、残業代トラブルは発生しにくくなります。万一請求されても、抗弁を出して企業側の正当性を主張できます。
法律手続きに則って解雇手続きを踏んでいれば、不当解雇にはなりません。
いったんトラブルが発生すると、労力と時間、費用がかかってしまうものです。
無駄な損失を避けるため、対応に迷ったときにはすぐに弁護士へ相談しましょう。
1-4.経営に専念できる
労働トラブルが発生すると、経営者や担当者は対応に時間と労力をとられます。
本来なら経営や普段の業務を行うべきであるところ、それが疎かになってしまうでしょう。
弁護士に任せれば、経営者や担当者が自分の仕事を後回しにしてトラブルに対応する必要がありません。
普段通りに経営や業務を行えるので、滞留を防いで企業運営を円滑に進められるメリットがあります。
2.最後に
今回は、会社が労働トラブルを弁護士に相談するメリットについて解説しました。
会社の不祥事が時々、世間を騒がせることがあり、そのたびに、一体何故不祥事を防げなかったというのが話題になります。
しかし、会社代表者や会社の担当者の方がいくら優秀であっても、自分が当事者になってしまった場合には、客観的に正しい判断を下すのが難しくなり、その判断が狂ってしまうことも多いです。
会社の労働トラブルについても同じことが言え、普段優秀な会社代表者や会社の担当者の方が、客観的に見ると誤った判断を下してしまい、トラブルをむやみに拡大させてしまうことも多いです。
京都の益川総合法律事務所は、企業側の労働問題に力を入れて取り組んでいます。
労働問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
問題社員を解雇する方法
- 欠勤や遅刻が多い
- 上司に反抗的な態度をとる
- セクハラやパワハラなどのトラブルを引き起こす
- 経歴を詐称されていた
会社は、問題社員を抱えていると、解雇したいと考えるものです。
もっとも、問題社員を解雇するには、法的に適正な手順を踏まねばなりません。
いい加減に対応すると、「不当解雇」と主張され、解雇の効果が認められない可能性もあるので、慎重に対応しましょう。
今回は、問題社員を解雇する適切な手順を弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1 解雇の要件を把握する
問題社員を解雇したいなら、まずは法律上の解雇の要件を把握すべきです。
労働者は法律によって強く保護されるので、会社側が解雇するのは簡単ではありません。
- 客観的合理的な理由
- 社会的相当性
これら2つの要件を満たさなければ、普通解雇は認められません。
たとえば、以下のような場合であれば解雇できる可能性があります。
- 長期の無断欠勤
- 刑事事件を起こして有罪となり、会社の信用を失墜させた
- 上司に反抗的な態度を取り続け職務怠慢が続き、再三に渡って注意しても改善しない
- 極めて重大な経歴詐称
ただし、上記に該当する場合であってもいきなり解雇すると社員側が納得せず、トラブルにつながる可能性があります。
以下のような手順で解雇を進めるのが良いでしょう。
STEP1 教育指導を行う
遅刻や欠勤が多い、成績が悪い、勤務態度が悪いなどの問題があるなら、まずは教育指導を行って改善を目指しましょう。問題が解消されれば解雇する必要はありません。
どういった教育指導を行ったのかについては資料を残しておきましょう。
後に、「不当解雇」と主張された場合に反論するための証拠となります。
STEP2 人事異動などの工夫をする
セクハラやパワハラ行為、勤務態度などの問題は人事異動によって克服できるケースもあります。
部下のいない部署へ移す、仲の悪い同僚や上司のいない部署へ移す、異なる業務を与えるなどの工夫をして改善を目指しましょう。
STEP3 退職勧奨する
工夫をこらしても問題が解消されない場合には、いよいよ会社を辞めさせることを検討します。
ただし、いきなり解雇するのではなく、退職勧奨するようおすすめします。
退職勧奨とは、従業員へ自主的な退職を促すことです。
従業員が自ら辞めるのであれば、基本的に不当解雇になりません。
ただし、退職勧奨時には「退職強要」にならないよう注意が必要です。
たとえば、上司が数人で本人を取り囲み、退職届に署名押印するまで帰さない、などと告げて脅迫すると強要となってしまうでしょう。
退職はあくまで本人の自主的な意思に委ねるべきです。
2 解雇せざるを得ない場合の対応
退職勧奨をしても本人が応じない場合には、いよいよ解雇の手続きを検討せざるを得ません。
解雇するときには、以下の手順で進めましょう。
STEP1 解雇理由をまとめる
まずは、解雇の理由をまとめておくべきです。
1つには、後に社員側から解雇理由証明書を求められる可能性があるからです。
すぐに正当な理由を付した解雇理由証明書を発行できるよう、用意しておく必要があります。
また、解雇理由が不十分な場合、解雇が無効となってしまうリスクが高まります。
実際に解雇通知を送る前に、客観的合理的な解雇理由を明らかにして、関係者で共有しましょう。
STEP2 解雇予告または解雇予告手当の支給をする
労働基準法により、社員を解雇する際には「30日前に解雇予告」をしなければなりません。いきなり社員を解雇すると、社員にとって影響が大きくなるためです。
ただし、30日前の解雇予告が困難な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支給すれば解雇できます。
STEP3 解雇通知をする
解雇通知を送り、解雇を実行します。
解雇したら労働契約が終了するので、その後は賃金を支払う必要がありません。
STEP4 解雇後の対応
解雇した後、未払いの給料があれば支給する必要があります。
退職金が発生する場合には、きちんと計算して支給しましょう。
社員に名刺やタブレット機器などを支給している場合には、返還させ、私物については持ち帰らせましょう。
社員が退職すると、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」を提出しなければなりません。ハローワークから離職票が送られてきたら、本人へ交付しましょう。
解雇理由証明書について
解雇後、社員からは「解雇理由証明書」の発行を求められる可能性があります。
解雇理由証明書には、会社が「解雇すべきと考える理由」を書かなければなりません。
証明書に記載した理由が不十分な場合、「不当解雇」と主張される可能性が高くなります。
事前に慎重に検討しておいた解雇理由を書き込み、交付しましょう。
3 問題社員を解雇するには弁護士へ相談を
問題社員を適正に解雇するには、弁護士へ相談するようおすすめします。
弁護士であれば、解雇の要件を満たすかどうか、法的に判断できます。
解雇前に退職勧奨を行う場合にも「退職強要」といわれないよう気を付けるべきポイントについて、アドバイスさせていただきます。
仮に、社員が不当解雇として争ってきた場合にも対応ができます。
京都で労使トラブルに詳しい弁護士をお探しの事業者様がおられましたら、お気軽に益川総合法律事務所までご相談ください。
懲戒解雇に納得できないときの対処方法
- パワハラを疑われて懲戒解雇されてしまったが、事実無根なので取り消してほしい
- 「同僚より成績が悪い」と言われて懲戒解雇された
- 懲戒解雇に納得できない
- 弁明の機会も与えられずにいきなり懲戒解雇された
懲戒解雇が無効になるケースは少なからず存在します。
納得できない場合には弁護士までご相談ください。
1 懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、懲戒処分の一種として行われ、使用者が労働契約を一方的に解消するもので、懲戒処分の中では最も重い処分です。
懲戒処分とは、企業秩序違反行為に対する制裁罰であって、労働者の行為によって企業秩序が害されたことが実質的な根拠となります。
懲戒処分には以下のような種類があります。
- けん責・戒告・始末書提出処分…最も軽い懲戒処分で口頭又は文書によって将来を戒めるものです。
- 減給…給料を減らす処分です。
- 出勤停止…一定期間、会社への出勤を停止する処分です。通常、出勤停止期間中は賃金が支給されません。
- 降職・降格…人事制度における役職上の地位や格付けを下げることです。
- 諭旨解雇…退職金の一部又は全部の不支給を伴う懲戒解雇より緩やかな処分です。労働者に退職願や辞表の提出を勧告して、それに応じない場合に懲戒解雇するという形式をとることもあります。
- 懲戒解雇…最も重い懲戒処分で、退職金の不支給などの不利益を伴うことが多いです。
2 懲戒解雇が有効となる条件
懲戒解雇は、常に有効とは限りません。以下の要件を満たす必要があります。
(1)就業規則に定める
まずは、会社の就業規則に懲戒に関する規定を定め、従業員へ周知しなければなりません。
就業規則に懲戒規定がない場合には懲戒解雇はもちろん、懲戒処分そのものを適用できません。
(2)懲戒理由が存在する
次に、懲戒処分をしなければならない理由が必要です。
たとえば、業務上横領を行った、会社の信用を害するような重大な刑事事件で有罪判決を受けた、悪質なパワハラ行為を繰り返して何度注意しても改善しない、などの事情です。
「客観的な事実」が必要なので、会社が疑っているだけで、事実無根であれば懲戒解雇は認められません。
(3)懲戒理由と懲戒解雇のバランスが取れている
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重大な処分であり、労働者に与える影響も大きくなります。
懲戒事由に該当するからといって、常に解雇まで認められるとは限りません。
認められるには、「解雇と問題行動のバランス」が必要です。
たとえば、勤務態度が悪いとしても、戒告で済ませるべきケースもあるでしょう。
そういった軽い懲戒理由しかない事案で懲戒解雇を行うと、無効になります。
(4)適正な手続き
就業規則に懲戒規定を設ける場合、懲戒手続の進め方についても定められるケースがよくあります。
その場合、定められた手続きにそって懲戒処分が行われなければなりません。
たとえば、「労働者に弁明の機会を与える」と記載されているのに、実際には弁明の機会を与えられなかったら、不当解雇になります。
3 懲戒解雇でよくある理由
懲戒解雇が行われるとき、多いのは以下のような理由です。
- 業務上横領
- パワハラ、セクハラ
- 重大な経歴詐称
- 刑事事件で有罪になった
- 長期にわたる無断欠勤
上記のような事情が悪質であれば、懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。
一方、軽度なら懲戒解雇が無効になるケースもあるので、必ずしも解雇を受け入れなければならないとは限りません。
4 懲戒解雇が無効になるケース
以下のような場合には、懲戒解雇は無効になります。
(1)就業規則に規定がない
就業規則に懲戒に関する規定がなければ懲戒解雇は無効です。
(2)就業規則の定める手続きを踏んでいない
就業規則の定める手続きを踏んでいなければ、懲戒解雇が無効になる可能性が高くなります。
(3)懲戒事由がない
パワハラを疑われたけれども、実際にはパワハラを行っていないなど、懲戒事由がない場合には懲戒解雇は無効です。
(4)懲戒解雇が重すぎる
問題行動に対して懲戒処分が重すぎる場合、懲戒解雇は無効となります。
5 懲戒解雇に納得できない場合の対処方法
懲戒解雇に納得できない場合、以下のような対処を検討しましょう。
(1)地位回復を求める
懲戒解雇が無効であれば、労働契約関係は存続しています。
会社へ「従業員としての地位確認」を求めましょう。
(2)未払いとなった賃金を求める
労働者としての地位を失わないので、未払い賃金をまとめて請求できます。
(3)慰謝料を請求する
会社の対応が悪質な場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
(4)解決金を求める
会社に戻りたくない場合には、自主退職を前提に解決金や退職金を求める方法もあります。
(5)弁護士に相談する
懲戒解雇が無効であることを主張するには、会社に対して内容証明郵便を送って交渉すべきですし、場合によっては労働審判や訴訟を起こさねばなりません。
個人で対応するのは困難でしょう。
会社との力の差があるため、不利になりやすいというデメリットもあります。
弁護士に相談すれば、懲戒解雇が無効になる見込みがあるのか、どのように争えばよいのかアドバイスを受けられます。
会社との交渉も任せられるので、自分で対応する労力やストレスがかかりません。有利な条件で解決できる可能性が高まります。
懲戒解雇された場合、退職金も解雇予告手当も受け取れないというケースもあります。
懲戒解雇に納得できないという方は、まずは弁護士までご相談ください。
不当解雇とは 納得できないときの対処方法
「ある日突然、会社から解雇されてしまった」
解雇通知が届いても、それが「不当解雇」であれば会社に戻ることができます。
出社できなかった期間に不払いとなっていた賃金はもちろん、ときには慰謝料も請求できる可能性もあります。
不当解雇になるのはどういったケースなのか、納得できない場合の対処方法もふまえて弁護士がお伝えします。
1 不当解雇とは
不当解雇とは、法令の定める要件や手続きを満たさない違法な解雇です。
解雇の要件を満たさない場合や必要とされる解雇手続きをふまなかった場合に不当解雇となります。
不当解雇は基本的に無効なので、不当解雇された場合には労働者は会社に対し「従業員としての地位」を主張できます。
会社の対応が特に悪質な場合、慰謝料を請求できる可能性もあります。
2 不当解雇になる場合
(1)解雇できない場合に解雇した
法律上「解雇できない」と規定されている場合に解雇すると、不当解雇となります。
たとえば、以下のような場合が該当します。
- 正当な労働組合活動を行ったことを理由とする解雇
- 労基署へ不正の申告をしたことを理由とする解雇
- 女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇
- 女性労働者が妊娠したこと、出産したことを理由とする解雇
- 業務上の傷病による休業期間や休業明け30日間の解雇
- 産前産後休業中や休業明け30日間の解雇
- 産前産後休業の請求・取得を理由とする解雇
(2)解雇の要件を満たしていない
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。
すなわち、解雇するには以下の2つの要件を満たさねばなりません。
- 客観的合理的性
- 社会的相当性
これら2つの要件は極めて厳しく判断されます。
解雇要件を満たさない不当解雇の例
たとえば、以下のような場合、解雇要件を満たさないので不当解雇となる可能性が高いと考えられます。
- 他の従業員と比べて成績が悪い
- 多少の遅刻や欠勤、早退がある
- 周囲との協調性に欠ける
- 業務に直接影響のない小さな経歴詐称
パワハラ行為や頻繁な遅刻欠勤、上司へ反抗的な態度をとるなどの問題がある場合でも、一度も注意せずいきなり解雇をしてしまうと、解雇の要件を満たさず無効となる可能性が高いといえるでしょう。
会社側が社会的相当性の要件を満たすには、十分に教育指導を行い配置転換や降格などの他の対応方法を検討しなければなりません。
それでもなお、解雇しか解決手段がない場合、ようやく解雇が認められる可能性があります。
(3)手続き的な不備がある
解雇をするときには、30日以上前に解雇予告を行うか、予告が間に合わなかった場合には不足日数分の解雇予告手当を払わねばなりません。
解雇予告もせず、解雇予告手当も払わずにいきなり解雇をすると、不当解雇となります。
(4)就業規則違反の解雇
就業規則において解雇できる場合や解雇条件、解雇手続きが規定されている場合には、就業規則にも従わないと不当解雇となります。
懲戒解雇する場合にも、就業規則に懲戒に関する規定が必要です。
3 不当解雇されたときに主張できる内容
不当解雇された場合には、会社に対して以下のような主張ができます。
(1)従業員の地位確認
不当解雇は無効となるので、従業員としての地位を主張できます。
従来のように会社に戻り、賃金を受け取れます。
(2)不払い賃金の請求
解雇通知後不払いとなっていた賃金を請求できます。
(3)慰謝料
解雇が特に悪質な場合には、慰謝料を請求できるケースもあります。
ただし、慰謝料は常に請求できるとは限りません。
- 社長が従業員にセクハラを行い、これに対して反抗されたことを理由として解雇した場合
- 虚偽の解雇理由を社外に示して従業員の名誉を毀損した場合
こういった悪質なケースであれば、慰謝料を請求できる可能性が高くなるでしょう。
(4)会社に戻りたくない場合
会社に戻りたくない場合には、話し合いにより不払い賃金や次に就職できるまでの補償金を解決金として受け取り、解決する方法もあります。
不当解雇を主張したからといって、会社に戻らなければならないとは限りません。
4 不当解雇されたときの対処方法
不当解雇されたら、以下のように対応しましょう。
(1)解雇理由証明書を請求する
まずは、「解雇理由証明書」を請求してください。解雇理由証明書とは、会社の考える解雇理由が書かれている書面です。
労働者が会社へ解雇理由証明書を請求したら、会社は速やかに発行しなければなりません。
解雇理由証明書に書かれている理由が不当なものであれば、後に裁判になったときに不当解雇を認めてもらいやすくなります。
(2)会社へ通知書を送る
会社に対し、解雇が無効になることや従業員としての復帰、不払い賃金の支払いを求める通知書を送りましょう。
内容証明郵便を使って送付するようおすすめします。
(3)弁護士へ相談する
不当解雇を主張する際には、会社と交渉しなければなりません。
法的な知識を持たずに労働者が1人で対応すると、どうしても不利になってしまいやすいでしょう。
自分でも気が付かないうちに、行うべきでないことをしてしまう可能性もあります。
できるだけ早い段階((1)解雇理由証明書の請求を行う前)で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が代理人として交渉すれば、労働者の権利を十分に実現しやすくなるメリットがあります。
会社側も真剣に対応することが予想されます。また、弁護士に労働審判や訴訟も任せられて安心です。
当事務所では、労働関係のトラブルに力を入れて取り組んでいます。
困ったときにはお早めにご相談ください。
離婚に伴う財産分与請求を行い、1億円以上の財産分与を取得した事案【解決事例】
・キーワード
離婚に伴う財産分与、高額所得者との離婚、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、離婚及び離婚に伴う財産分与の請求を行う側です。
ご依頼者は、配偶者が高額所得者であるため、財産分与の対象資産も多く、適切に財産分与を受けることができるかについて心配されていました。
そのため、適切に財産分与を受けることができるよう、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
受任後、相手方に対して速やかに内容証明郵便を送付し、離婚及び離婚に伴う財産分与の請求等についての当方の意向を通知しました。
相手方も弁護士に依頼し、弁護士同士の交渉となりました。
当初、相手方の提示金額は約7000万円でした。
これに対して、当方では、相手方が財産分与の対象資産として挙げていなかった資産を指摘する、対象資産の評価についても争う等して、粘り強く交渉を続けました。
その結果、ご依頼者が1億円以上の財産分与を取得する形で合意することができました。
・コメント
高額所得者との離婚ということで、財産分与の対象資産がすべて挙げられているか、適切な財産の評価がなされているかということが重要なポイントとなりました。
相手方も弁護士が代理人となっていたので、裁判になった場合の見通し等をふまえて交渉を行い、結果として相手方の当初の提示額から約4000万円の増額に成功しました。
大幅な増額に成功したこともあり、ご依頼者に大変満足して頂けました。
また、ご依頼当初、ご依頼者は、離婚にまつわる不安や心配をお持ちになっていましたが、時間が経つにつれて、ご依頼者自身が、離婚後の生活について、前向きに明るく考えるようになられていく姿が印象的でした。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています。
高額所得者との離婚については、こちらのページで詳しく解説しています。
不倫慰謝料の相場と不倫の証拠について
不倫慰謝料を請求するときには、「相場の金額」を把握しておくべきです。
相場がわからなければ、そもそもどのくらいの金額を請求すべきか判断できません。
相手から減額を主張されたときにも、応じてよいものかどうかについての判断がつきかねます。
また、不倫の「証拠」も重要です。
証拠がないのに請求しても、不倫の事実について否定され、「払わない」と言われてしまうでしょう。
今回は、不倫慰謝料の相場や不倫の証拠について、京都で男女問題に積極的に取り組んでいる弁護士がご説明します。
1 不倫慰謝料とは
不倫慰謝料とは、配偶者が「不貞」をしたときに請求できる慰謝料です。
「不貞」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係をもつことをいう法律用語です。
一般用語の「不倫」や「浮気」と近い意味を持ちます。
配偶者に不貞をされると、不貞された側は、配偶者と不貞相手の両方へ慰謝料を請求できます。
この不倫慰謝料の損害賠償債務は、不真正連帯債務となるので、どちらにも全額の請求ができます。
請求のタイミングは、同時でも別のタイミングでもかまいません。
2 不倫慰謝料の金額
不倫慰謝料の金額を話し合いで決める場合、「いくらにしなければならない」という決まりはありません。
高額でも相手が納得すれば支払いを受けられますし、低額でも請求する側が納得すれば有効な取り決めになります。
もっとも、裁判所が慰謝料の額を判断する際には相場があります。
把握して参考にしましょう。
(1)離婚する場合
離婚すると、被害者の受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるので、離婚しない場合より不倫慰謝料の金額が上がります。
慰謝料の算定については、婚姻期間、不貞の回数・期間・程度、配偶者と不貞相手のどちらが積極的であったか等も考慮されます。
一般的には、100万円から300万円の範囲となることが多いようです。
正式に離婚しなくても、別居状態となって夫婦関係が破綻してしまったら、離婚事案に近い慰謝料額が認められやすい傾向があります。
(2)離婚しない場合
離婚しない場合、離婚する場合と比べて慰謝料の金額は低額になり、100万円以下が相場となります。
(3)肉体関係を証明できない場合の慰謝料
法律上の「不貞」というには肉体関係を証明しなければなりません。
ただし、肉体関係が認められなくても、社会常識を超えてあまりに親しい交際関係があると、夫婦生活の平穏が害されるので、夫婦生活の平穏を害して精神的苦痛を与えたとして慰謝料が認められるケースがあります。
3 不倫の証拠について
不倫慰謝料を請求するなら、事前に証拠を集めましょう。
証拠がなければ相手から支払いを拒否されるでしょうし、裁判を起こしても、不貞の証明ができず、こちらの請求が認められません。
以下で、不倫の証拠を集める際のポイント等についてご説明します。
(1)不倫の証拠集めのポイント
不倫慰謝料の証拠を集めるとき、まずは「肉体関係を証明できるかどうか」に注目しましょう。
肉体関係を直接証明できる証拠があれば、それ1つでも十分です。
一方、肉体関係があるか判然としないものは、証拠としての価値が低く、数多く集めても不貞が認められない可能性があります。
以下、集めるべき有効な不倫の証拠と、間接的な証拠の例を挙げます。
(2)有効な不倫の証拠
- 性交渉をしているときの画像、動画
不倫を立証するための強力な証拠になります。
- 性関係をもっていることがわかるLINE、SNSなどのメッセージ、メール
不倫があったことを強く推認させるものであり、有効な証拠となります。
- 不貞(肉体関係)を認める自認書や録音データ
配偶者や不倫相手が「不貞しました(肉体関係を持ちました)」と認めて作成する書面や話したときの録音データです。
自認書を作成させる際には、直筆で署名押印させましょう。
- 相手の日記やスケジュール帳
肉体関係を持ったことがわかるものであれば、有効な証拠になります。
- 探偵の調査報告書について
探偵事務所の調査報告書も、ホテルに入っていくところ、不倫相手の家に宿泊したところなどの写真などがある場合には不貞についての強力な証拠となります。
ただし、探偵の調査が必ずしも成功するとは限りません。
調査回数、調査時間が増えると費用が高額となるので、依頼の際には費用対効果を慎重に検討しましょう。
(3)間接的な証拠
- 肉体関係までは直接わからない親しげなLINEやSNSのメッセージ、メールなど
- デートしているときの写真や動画(キスやハグなど)
- クレジットカードの明細書
- デート代やプレゼント代の領収証
- 相手から贈られてきたメッセージカードやプレゼントの現物
- 交通ICカードやETCカードの記録
- 通話履歴
- 相手の日記やスケジュール帳(肉体関係まではわからないもの)
配偶者や不倫相手へ慰謝料請求する前に、請求する金額や証拠について十分な準備を整えましょう。
当事務所には男性弁護士と女性弁護士の両方が在籍しており、請求金額や証拠について、双方の視点からアドバイスやサポートが可能です。
京都、滋賀、大阪で不倫トラブルに悩まれている方がおられましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
離婚で慰謝料を請求できるケース、できないケース
離婚の際、「相手に慰謝料を払ってもらいたい」と考える方も多数いらっしゃいます。
しかし、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
今回は、慰謝料を請求できるケースとできないケースについて、弁護士が具体的な状況を交えて解説します。
離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1 離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害賠償金のことです。
具体的には以下のような場合、慰謝料が認められる可能性があります。
(1)不貞された
相手が「不貞」した場合は、慰謝料が認められる典型例です。
不貞とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係をもつことを意味します。
親しく交際していても、性的関係がなかったら不貞にはなりません。
ただし、性的関係がなくても、社会常識を逸脱するほど親密な交際を続け、夫婦生活の平穏を害して精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料が認められる可能性もあります。
(2)生活費を払ってもらえなかった
夫婦にはお互いに扶助義務があるため、収入の高い方は低い方へ生活費を払わねばなりません。
たとえば、こちらが専業主婦や兼業主婦などで所得が低いのに、相手が生活費を払ってくれなかった場合、慰謝料を請求できます。
(3)家出された
夫婦には同居義務があります。正当な理由なく家出されたり同居を拒否されたりしたら、慰謝料を請求できます。
(4)暴力を振るわれた
暴力を振るわれた場合もまた、慰謝料が認められる典型例です。
暴力を振るわれた場合には、診断書や暴力を振るわれた直後の部位の写真等が有効な証拠となります。
(5)モラハラ被害を受けた
モラハラは、言葉や態度による精神的な暴力です。
モラハラ配偶者には、大声でどなる、人前で相手を侮辱する、無視して口をきかない、異常に束縛する、実家の親族や友人との交流を制限する、暴れて物に当たるなどの特徴がみられます。
モラハラの場合には、立証が難しいため、慰謝料を認めてもらうことは容易ではありませんが、慰謝料が認められた裁判例もあります。
モラハラ被害を受けた場合には、客観的な資料を残しておくことをおすすめします。
(6)セックスレス
場合によっては、セックスレスの事案でも慰謝料を請求できる可能性があります。
典型的には、健康で若い夫婦であるにもかかわらず、一方が特段の理由なく性交渉を拒否し続けていた場合が挙げられます。
ただし、性交渉がないからといって、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。
ケースバイケースの判断が必要です。
(7)浪費
相手が浪費していた場合にも、事案によっては慰謝料が認められる可能性があります。
たとえば、相手が生活費に手を付けたために家族の生活が困窮した場合、こちらが稼いだお金をギャンブルなどにつぎ込まれて生活が破綻した場合などです。
ただし、相手が浪費したからといって必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。
相手が自分で稼いだお金を余裕のある範囲内で使っていた場合、個人的な借金はしていたけれども夫婦の生活にはさほどの影響が及ばなかった場合などには慰謝料は発生しないと考えられます。
(8)刑事事件で有罪になった
相手が刑事事件によって有罪判決を受けた場合、慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば、相手が強制性交等罪を犯したら「不貞」であり、慰謝料請求をできる可能性があります。
ただし、すべての刑事事件が慰謝料発生原因になるとは限りません。
万引きや暴行、脅迫などの犯罪行為を行った場合でも、必ずしも夫婦関係を破綻させる行為とはいえません。
相手が実刑になっても慰謝料請求できないケースは考えられます。
相手が刑事事件で逮捕されたり有罪になったりしたとき、慰謝料請求できるかどうか迷ったら弁護士へご相談ください。
2 慰謝料請求が難しい場合
以下のような場合には慰謝料請求が難しいと考えられます。
(1)性格の不一致、価値観の相違
離婚理由として最も多いと思われるのが「性格の不一致、価値観の相違」です。
性格の不一致、価値観の相違の場合、有責性が認められるのが難しく、慰謝料は発生しません。
ただし、相手の態度が突然冷たくなった、家庭を顧みなくなったなどの事情がある場合、相手が不貞しているケースがよくあります。
「性格の不一致、価値観の相違」と決めつける前に、本当の離婚原因を探る必要があるでしょう。
(2)思想や宗教の違い
思想や支持政党、考え方や宗教などが異なるため、離婚に至るケースもあります。
家柄や生活習慣が違いすぎて夫婦関係を継続できなくなることもあるでしょう。
こういったケースではどちらが悪いというわけでもないので、慰謝料は発生しません。
(3)相手の実家との不和
相手の実家と反りが合わないので離婚するということも、多くあると思われます。
相手の実家の親族と相手本人は異なるので、相手の実家から嫌がらせをされたからといって相手に慰謝料請求できるわけではありません。
もっとも、義母が度を超えた嫌がらせを行って夫婦関係を破綻させた事案において、義母に慰謝料の支払いを命じた裁判例はあります。
3 解決金の支払いを受けられる可能性も
離婚の際に慰謝料請求権が認められるかどうか明らかでなくても、話し合って協議離婚するなら「解決金」を払ってもらえる場合がよくあります。
「解決金」であれば、相手方としても「慰謝料」といわれるより心理的抵抗が小さく、払いやすくなるものです。
益川総合法律事務所では、離婚事件について、多数の対応経験があります。
離婚の慰謝料請求についても、お気軽にご相談ください。
財産分与で損をしないための8つのポイントを弁護士が解説
財産分与は、離婚後の生活に直結する重要事項です。
損をしないように適正な方法を把握しておきましょう。
今回は、財産分与をなるべく有利に進めるために押さえておくべき8つのポイントについて、京都で離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士がご紹介します。
1 財産をもれなく洗い出し、財産隠しを防ぐ
財産分与で損をしないためには、対象財産を漏れなく洗い出すことが極めて重要です。
漏れがあると、その分は分与してもらえず、受け取り分が減らされてしまうからです。
財産分与対象資産の例
- 現金、預貯金、電子マネー、仮想通貨
- 保険
- 株式、投資信託、債券
- 不動産
- 車
- 退職金(将来支給される退職金も財産分与の対象となる可能性があります)
- 社内積立
- 共済貯金
- 動産類
相手が管理している分についてはすべて開示してもらいましょう。
財産隠しは防がなければいけません。
相手が財産を開示しない場合、弁護士への依頼も有効です。
弁護士会照会という方法を使って、照会先が回答してくれる場合には、相手名義の預貯金や株式について、明らかにできる可能性があります。
どうしても開示を受けられない場合、調停や訴訟になれば裁判所へ申し立てを行い、裁判所を通じて調べてもらえる可能性もあります。
ご自身で財産を調査しきれない場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
2 適正に評価する
不動産や車、株式などの財産がある場合、評価をしなければ財産分与の金額の計算ができません。損をしないために、財産の適正な評価がなされることが極めて重要です。
こちらが財産を取得して代償金を払う場合、評価額が高くなると支払額が大きくなります。
一方、こちらが代償金を受け取る場合、評価額が高いと受け取れる金額が高くなります。
自分の立場により、評価が高い方が得か、低い方が得かが変わります。
相手が不当な評価額を持ち出してきたら、受け入れずに適正な評価額及び評価根拠を提示しましょう。
そのためにも、各財産の評価方法や評価証明書の入手方法を知っておく必要があります。
3 希望を明確にする
財産分与を有利に進めるためには、自分の希望を明確に伝えることが必要です。
特に多種多様な財産がある場合、どの財産を取得したいのか、相手に取得させる場合にいくらの代償金を求めるのか、あるいは売却して現金で分けたいのかなど、メリットやデメリットをふまえてしっかり検討しましょう。
いきあたりばったりな対応をしていると、相手のペースで話が進んで損をしてしまう可能性があります。
4 法的知識をもって対応する
財産分与を有利に進めるためには、法的な知識が必須です。
- 対象となる財産の範囲
- それぞれの財産の評価方法
- 適正な財産分与割合
- ローンがある場合の自宅の分け方
- 借金の財産分与
- 財産分与の進め方(話し合い、調停、訴訟など)
- 財産の使い込みを防止する方法
上記のような知識がないと、自分のペースで話を進めるのは難しくなるでしょう。
もしも知識が足りない場合には、弁護士に相談するようおすすめします。
一度弁護士に相談して基本的な部分についてアドバイスを受けておけば、それをもとに自分で相手と交渉することも可能です。
また、弁護士に交渉を依頼すれば、より有利に解決できる可能性が高くなるケースが多くあります。
5 資料を集める
財産の資料集めも非常に重要です。
具体的な資料がないと、相手から「そんな資産はない」と主張される可能性が高くなり、調停や訴訟でも財産の存在を認めてもらえません。
預貯金通帳、取引履歴、保険証書や証券会社の資料、不動産全部事項証明書や固定資産評価証明書、車検証、給与明細書(積立や保険に関する記載があるもの)など、可能な限りの資料を手元に収集しましょう。
6 財産を勝手に処分されそうな場合には保全を申し立てる
財産分与を行う前に相手が勝手に財産を処分してしまったら、財産分与を受けにくくなってしまう可能性があります。
- 別居中に相手が勝手に自宅を売却してしまう
- 相手が受け取った数千万円の退職金を使い込んでしまう
- 相手が勝手に保険を解約して解約返戻金を使い込んでしまう
こういったトラブルを防ぐには「保全処分」が有効です。
裁判所の命令により、相手方による売却などの処分を仮に禁止したり、相手方の資産を仮に差し押さえたりすることができます。
7 2分の1より多めの分与を求めることも可能な場合がある
財産分与の基本的な清算の割合は、原則として2分の1とされています。
ただし、夫婦双方が納得すれば、2分の1以外の割合で分けてもかまいません。
たとえば、妻側が仕事をしておらず子どもを引き取る場合、自宅を含めて多めの財産分与を受けるケースもあります。
相手が不倫した場合に、慰謝料代わりに高額な分与を受ける事例もみられます。
2分の1より多めの財産分与を受けられる可能性についても考慮しながら交渉を進めましょう。
8 相手が強硬な場合、弁護士に依頼する
相手が強硬なため自分で交渉しても思うように財産分与を受けられそうにない場合、早めに弁護士へ依頼しましょう。
相手から言いくるめられて不利な条件に応じてしまうと、後で覆すのが困難です。
当事務所には女性弁護士と男性弁護士の両方が在籍しており、男女それぞれの視点から離婚や財産分与の支援をいたします。
京都で離婚問題にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
高額所得者と離婚するときの知識~財産分与、養育費、婚姻費用で損をしないように~
医師や経営者、プロスポーツ選手などの高額所得者と離婚するときには、一般的な会社員の離婚の場合とは異なる注意点があります。
財産分与や養育費、婚姻費用なども高額となりますし、相手が会社経営をしている場合には、株式や会社名義の財産も問題となるでしょう。
今回は高額所得者と離婚するときに必須の知識を、京都の弁護士が解説します。
1 財産分与の割合
相手が高額所得者の場合、婚姻中に形成された資産額が多く、財産分与対象資産も高額になりがちです。
一般的な事案における財産分与の割合は「夫婦で2分の1ずつ」ですが、一方が高額所得者の場合、修正される可能性があります。
たとえば配偶者が医師で病院経営をしているケース、会社経営を行って大きく成功しているケースでは、請求者の財産分与割合を減らされるという裁判例もあります。
ただ、相手が医師や経営者だからといって、必ずしも財産分与割合が調整されるとは限りません。
調整するとしても、どこまで割合を減らすべきかについては、ケースバイケースで判断されます。30%とすべき事案もあれば40%、45%などとすべき事案もあります。
相手に財産分与を求めたとき「お前は財産形成に貢献していないから10%しか渡さない」などと言われても、鵜呑みにする必要はありません。
まずは一度、弁護士へ相談して妥当な割合を算定するところから始めましょう。
2 財産分与の対象資産
相手が高額所得者の場合、多種多様な財産を形成しているでしょう。
一般的な預貯金や生命保険などに加えて、株式や投資信託、投資用の不動産なども所有している方も多数います。
また、経営者の方は、退職金代わりに長期平準定期保険や逓増定期保険などの保険に加入している場合があります。こうした保険も財産分与の対象になる可能性があるので、見逃してはなりません。
さらに、相手が株式会社を経営していて、婚姻後に会社株式を取得した場合には、相手が保有する会社株式も財産分与対象になると考えられます。
財産分与の対象となる資産を見逃すと、受け取れる分与額が減ってしまうので、漏れなく調査して洗い出しましょう。
財産分与対象資産の例
- 現金、預貯金
- 保険(退職金代わりの保険を含む)
- 不動産(自宅及び投資用物件)
- 上場株式(投資対象)
- 投資信託
- 自社株式
- 高級時計、絵画、骨董品などの動産
3 会社名義の財産について
個人と会社は別人格なので、会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりません。
ただし、たとえば、夫のいわゆる「一人法人」で実質的には個人事業と同視できる場合、会社の創業時から妻も会社経営に中心的に携わっていて会社財産の形成に貢献している場合などには、会社名義の財産も一部財産分与の対象にできる可能性があります。
どこまでの財産が分与の対象になるかわからない場合、弁護士までご相談ください。
4 財産隠しに要注意
適正に財産分与を受けるためには、財産隠しを防がないといけません。
高額所得者は、さまざまな対象へ資産を分散させており、財産分与を避けるために一部の資産を隠そうとするケースがよくあります。
相手の開示資産を鵜呑みにせず、漏れがないか調査しましょう。自宅に保管されている資料類を探しても限界がありますので、弁護士への依頼も有効です。
弁護士会照会という方法を使って調査できる場合もありますし、調停や訴訟になれば、裁判所からの調査もできる可能性があります。
5 養育費や婚姻費用の計算方法
相手が高額所得者の場合、子どもの養育費や離婚するまでの別居中の婚姻費用(生活費)の計算方法にも工夫が必要です。
一般的に、養育費や婚姻費用は裁判所の定める「養育費、婚姻費用の算定表」を用いて計算します。しかし算定表は「給与所得者の場合に年収2000万円」が上限となっており、それを超える場合の金額が記載されていません。
年収2000万円を超える相手の場合、養育費や婚姻費用は個別に計算する必要があります。
家庭裁判所では、
- 年収2000万円の場合の金額をそのまま適用する方法
- 基礎収入を減らして調整し、個別計算する方法
などの対応がとられます。
具体的にどういった計算をあてはめるべきかについては、事案によって異なるので、相手と養育費や婚姻費用について話し合う際には、弁護士までご相談ください。
6 慰謝料の金額
配偶者が不倫したために婚姻関係が破綻した場合、配偶者から暴力やモラハラ被害を受けたために離婚する場合などには慰謝料を請求できます。
配偶者が医師や経営者などの高額所得者である場合、慰謝料の金額が高額になる可能性もあります。
一般的に、慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、相手の収入や資産が高額なのに、その程度の金額では、被害者の気持ちが慰謝されにくいということもあるかもしれません。
特に話し合いで解決する場合、一般より高額な慰謝料額を定めるケースも多く、慰謝料代わりに不動産の分与を受けること、財産分与割合を増やしてもらうこともあります。
相手と交渉する際には、弁護士が対応することにより、有利な条件を引き出しやすくなることも多く、自分で対応するストレスもかかりません。
益川総合法律事務所には、男性弁護士も、女性弁護士も在籍しております。
医師や経営者などの高額所得者と離婚する際には、お気軽にご相談ください。
離婚に応じてもらえないときの対処方法
「離婚したい」と思っても、相手が応じてくれなければ協議離婚はできません。
日本では、夫婦の双方が離婚に合意しないと協議離婚や調停離婚できないルールになっているからです。相手の承諾なしに勝手に離婚届を書いて提出すると「偽造」になってしまい、離婚自体が無効になる可能性が高いのでやってはいけません。
相手に離婚を拒否されても、正しい手順を踏めば離婚できるケースが大多数です。
今回は離婚に応じてもらえない場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
1 説得する
相手が離婚に応じない場合、落ち着いて粘り強く説得すれば離婚できる可能性があります。
たとえば、相手が「妻(夫)は離婚したいと言っているが、単なる気の迷いだろう。放っておけばそのうち落ち着いて元の状態に戻る」などと軽く考えている場合、こちらが本気であると伝えれば相手も真剣になるものです。
当初は「離婚はしたくない」と言っていても、時間をかけて何度も説得すれば相手も根負けする事例が少なくありません。
説得の際には感情的にならず、できる限りビジネスライクに「離婚すべき理由」や「希望する離婚条件」を伝えましょう。
こちらが感情的になると相手も感情的になり、単なる言い合いになって話し合いが難しくなってしまいます。
2 別居する
相手が頑なに離婚を拒否する場合、別居を検討しましょう。
別居すると「配偶者のいない生活」が日常になるので、お互いに「離婚後の生活」を意識するようになります。「離婚したくない」と言っていた相手でも、配偶者に家を出ていかれたら「離婚するしかないか」と考え始めるケースが少なくありません。
3 婚姻費用を請求する
相手が一家の大黒柱でこちらが専業主婦または専業主夫などの事案では、別居後の婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用とは、夫婦が互いに分担すべき、婚姻生活を維持するために必要な費用です。収入の高い側が低い側へ払わねばならないので、専業主婦・専業主夫や兼業主婦・兼業主夫などで相手より低収入の方は離婚するまで婚姻費用を請求できます。
相手が婚姻費用の支払いを拒否しても、家庭裁判所で婚姻費用の分担請求調停を申し立てれば、最終的に裁判官が審判により結論を出してくれます。
婚姻費用は「離婚するか別居を解消するまで」払う義務が続くので、相手にしてみれば「離婚しないと高額な婚姻費用を毎月払い続けなければならない」状況になります。
婚姻費用の請求はこちらの生活を維持するために重要ですが、それ以外にも相手にプレッシャーをかけて、離婚への動機づけとなるという意味があります。
4 弁護士を代理人に入れて交渉する
相手が離婚に応じないときには、弁護士を代理人に立てて交渉する方法もおすすめです。
弁護士が代理人になると、相手との連絡はすべて弁護士を介するので、相手と直接連絡をとることはなくなります。
弁護士からも「もう離婚するしかないのでは」「離婚して先に進んだほうがよい」「このまま拒否していると調停や訴訟に進むしかなくなる」と伝えて離婚に応じるよう説得するため、相手としても「いよいよ離婚するしかないか」と腹をくくるケースが多数です。
また弁護士を代理人に立てれば、財産分与や養育費などの離婚条件についての希望も叶えやすくなり、有利な条件で離婚しやすくなるメリットもあります。
調停を申し立てる前に、弁護士を入れて交渉してみると、早めに協議離婚できる可能性もありますので、検討してみられてはいかがでしょうか。
5 離婚調停を申し立てる
協議離婚できない場合には、離婚調停を申し立てましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。夫婦が直接顔を突き合わせて話す機会はなく、待合室も別々なので裁判所内では基本的に顔を合わせません。
こちらの離婚意思が固い場合、調停委員としても相手に離婚に応じるよう説得してくれるケースが多数です。そこで、協議段階では離婚を拒否していても、調停になるとあきらめて離婚に応じる人が少なくありません。
調停申立時に婚姻費用についての話し合いができていなければ、婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立てることも可能です。
6 調停が不成立になったときの対処方法
調停でも、相手が頑なに離婚を拒否する場合、調停は不成立になります。
その場合、以下のような選択肢を検討しましょう。
(1)あらためて交渉を継続
調停後、あらためて相手と離婚協議を行う方法です。特に調停前に弁護士を入れて交渉した経緯がない場合、調停後は弁護士を代理人として交渉を持ちかけてみるのがおすすめです。
相手の気が変わって離婚に応じる可能性がありますし、拒否すれば離婚訴訟の提起も検討できます。
(2)時間をおいて再度調停を申し立てる
別居後、時間をおいてあらためて調停を申し立てる方法もあります。
(3)離婚訴訟を提起する
法定離婚事由があれば、離婚訴訟を提起しましょう。
法定離婚事由とは、法律上の離婚原因です。きちんと主張立証して、裁判所がそれを認めてくれた場合には、離婚の請求を認める判決を出してくれます。
法定離婚事由となるのは以下のような事情です。
- 相手の不貞(不倫)
- 生活費不払い
- 家出
- DV
- モラハラ
- 長期間の別居
- 相手が3年以上生死不明
- 相手が回復しがたい精神病
7 最後に
当事務所の弁護士は、離婚に応じない相手とも粘り強く交渉を行い、ご希望に沿った形での離婚を実現するお手伝いを致します。
男性弁護士と女性弁護士が在籍しており、あらゆる方にご安心してご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
Newer Entries »